- いびきをかく人は頭痛が起きやすいのはなんで?
- いびきと頭痛を改善する方法は?
このような疑問やお悩みをお持ちの方も少なくないでしょう。
いびきをかく人はさまざまな原因で頭痛を併発しやすく、日常生活の質に大きく影響します。また、早期に改善しなければ脳の病気を発症する可能性もあるため、注意が必要です。
この記事では、いびきと頭痛が同時に起きる原因や対策、実際の体験談を紹介します。この記事を読むことで、いびきと頭痛を同時に改善することができ、より良い睡眠を得ることができるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
いびきと頭痛が同時に起こる原因とは?
「普段からいびきをかくけど、朝起きた時に頭痛を認める」「起床時から熟睡感がなく、倦怠感や頭痛がある」このように、いびきと頭痛は併発しやすいことが知られており、そのメカニズムは原因によっても異なります。
いびきと頭痛が同時に起こる原因は主に下記の4つです。
それぞれについて詳しく解説します。
睡眠時無呼吸症候群による酸欠
いびきと頭痛が同時に起こる原因として、睡眠時無呼吸症候群による酸欠が挙げられます。
睡眠時無呼吸症候群は何らかの原因で気道が狭窄し、いびきをかくとともに、睡眠中に取り込める酸素の量が低下してしまう病気です。持続的ないびきによって脳や身体は十分な酸素を受け取ることができなくなり、低酸素状態に陥ります。
その際、少ない酸素をなるべく多く脳に供給できるように、代償性に脳血管を拡張させることで血流を増加させ、少ない酸素を少しでも多く脳に供給できるように変化します。
この代償性の脳血管の拡張によって、痛みを感じる三叉神経などの神経を刺激してしまうため、これによって頭痛が生じると考えられているのです。
2日に1回、30分以内に収まるような頭痛を自覚する場合、睡眠時無呼吸症候群に伴う頭痛である可能性が高いため、注意が必要です。
また他にも、睡眠時無呼吸症候群による低酸素のストレスによって、片頭痛や群発頭痛などの一次性頭痛が併発している可能性もあります。
いびきによる睡眠の質の低下と緊張型頭痛
いびきと頭痛が同時に起こる原因として、いびきによる睡眠の質の低下と緊張型頭痛が挙げられます。
先述したように、いびきをかいている状態は気道が狭くなっている状態のため、睡眠中に取り込める酸素量が低下し、身体にとっては大きなストレスです。
このストレスによって緊張型頭痛を併発する可能性が高まるため、いびきと頭痛が同時に起こりやすくなります。
緊張型頭痛とは、ストレスや睡眠障害が誘因となって月に数日、軽度〜中等度の締め付けられるような頭痛が、頭部両側に生じる病気です。(参考文献:MSDマニュアル)
同じ一次性頭痛(脳や体に明らかな原因となる病気がないにも関わらず起こる頭痛)である片頭痛とは異なり、前兆症状や嘔気などの随伴症状も伴わないことが多く、頭痛のみが頻繁に起こります。
また、睡眠障害やいびきによるストレスは、緊張型頭痛だけでなく片頭痛や群発頭痛などの一次性頭痛も併発しやすいため、いびきに伴う頭痛を認める場合、頭痛の性状や前兆症状の有無などから、慎重な診断を要します。
副鼻腔炎(蓄膿症)
いびきと頭痛が同時に起こる場合、副鼻腔炎(蓄膿症)を発症している可能性があるため、注意が必要です。副鼻腔炎(蓄膿症)とは、風邪のウイルスや細菌感染、アレルギーなどの影響で、鼻腔と通ずる副鼻腔と呼ばれる空間に炎症が生じる病気です。
炎症によって粘膜に浮腫が生じ、また鼻汁も増加することで鼻が詰まりやすくなるため、発症すると鼻呼吸が困難となり、睡眠中の口呼吸が増加します。口呼吸の場合、吸気時に開口するため、下顎が後方に移動して気道が狭窄し、いびきが増加します。
さらに、副鼻腔は前頭洞・上顎洞・蝶形骨洞・篩骨洞の4つの空洞で形成されており、鼻腔よりも頭蓋内の深部に位置しているため、ここで炎症が起こると鼻の症状よりも頭痛として認識してしまうため、副鼻腔炎では頭痛を自覚しやすいです。
以上の理由からも、副鼻腔炎ではいびきと頭痛が同時に起こりやすく、他にも顔面痛や嗅覚障害、鼻汁など認めることが多いです。
枕や寝姿勢による血行不良
いびきと頭痛が同時に起こる場合、不適切な寝具の使用や体に負担のかかる寝姿勢による血行不良が生じている可能性があります。
まず、不適切な寝具の使用は睡眠中、頚部の過剰な屈曲を生み、気道が狭くなりやすいため、いびきの原因となります。高すぎる枕、柔らかすぎて腰の沈むマットレスなど、使用されている方はリスクが高いため、注意が必要です。
また、仰向けで寝ると、睡眠中に弛緩した舌が後方に落ち込み、気道が狭窄するため、横向きで寝る人よりもいびきをかきやすくなります。
さらに、不適切な寝具の使用や、長時間同じ寝姿勢を保つ場合、もしくは身体にとって負担の大きい姿勢で寝てしまっている場合、頚部や肩の筋肉に負担がかかり、筋肉の張りによる血行不良が起こることで頭痛を伴いやすくなります。
以上の理由からも、不適切な寝具の使用や体に負担のかかる寝姿勢はいびきと頭痛を併発しやすく、睡眠の質の低下にもつながるため、注意が必要です。
いびきと頭痛が同時に起きる場合の対処法・改善策
いびきと頭痛が続く場合、睡眠の質の低下や頭痛によって日中の活動にも大きな支障をきたす可能性があります。また、多くの場合、いびきと頭痛はセルフケアで改善できるため、早期から原因に合わせて適切に対処することが重要です。
そこで、ここではいびきと頭痛が同時に起きる場合の対処法・改善策を5つ紹介します。
生活習慣を見直す
いびきと頭痛が同時に起きる場合、まずは生活習慣を見直すことが重要です。
実は不適切な生活習慣は気道の狭窄を招き、いびきの発症に大きく関わることが知られています。無意識にいびきをかきやすいような生活習慣を送ってしまっている可能性もあるため、注意が必要です。
具体的に、いびきや頭痛の原因として下記のような生活習慣が挙げられます。
- 就寝直前までの飲酒・喫煙:気道が浮腫んでいびきをかきやすくなる
- 暴飲暴食:肥満になって頸部に脂肪がつくことで、いびきをかきやすくなる
- 仰向け寝:舌根沈下しやすく、いびきをかきやすくなる
- 睡眠薬の常用;舌根沈下しやすく、いびきをかきやすくなる
- 過剰な塩分摂取;気道がむくみやすく、いびきをかきやすくなる
上記のような生活習慣は全て、いびきを引き起こしやすくする原因であり、心当たりのある方は生活習慣を見直すべきです。
また、これらの原因でいびきをかくと、睡眠の質の低下やストレスによって頭痛も同時に発症しやすくなるため、いびき、頭痛両方の改善のためにも、これを機に生活習慣を見直すと良いでしょう。
枕や寝具を見直す
いびきと頭痛が同時に起きる場合、枕や寝具を見直すことも重要です。
先述したように、枕などの寝具は睡眠の質に大きく影響し、身体に合っていない寝具の使用はいびきの増悪や頭痛の発症の原因です。高すぎる枕の使用は、頸部が過度に屈曲し、気道が狭くなることでいびきをかきやすくなります。
一般的に、適切な枕の高さは2〜6cm程度と言われており、7cm以上の高さの枕はいびきの発症リスクが高まるため、注意が必要です。
横向きで寝ることが多い方の場合、仰向けでちょうどいい高さの枕であっても、横向きではフィットしない可能性があるため、普段よく取る寝姿勢にとってフィットするサイズの枕を選びましょう。
また、柔らかすぎるマットレスの使用は腰が沈み、やはり頚部の過度な屈曲を招くため、いびきの原因となります。
一方で、硬すぎるマットレスの場合は寝心地が悪く、頚部や肩に負担がかかることで頭痛が生じやすくなる可能性もあります。このように、身体に合っていない寝具の使用はいびきと頭痛の原因となるため、これを機に見直してみると良いでしょう。
鼻づまりや口呼吸の対策をする
いびきと頭痛が同時に起きる場合、鼻づまりや口呼吸の対策をすることも重要です。
鼻づまりや、それに伴う口呼吸が増加すると、下顎が後方に下がりやすく、舌後方に位置する気道が狭窄するため、いびきをかく原因となります。さらに、本来の鼻呼吸なら取り込んだ空気が鼻汁によって加温・加湿されますが、口呼吸の場合は乾燥・寒冷した空気が気道に入り込んでくるため、気道で炎症が生じやすくなります。
炎症が起こると気道は浮腫み、狭窄することでよりいびきをかきやすくなるため、鼻づまりや口呼吸の改善が重要です。鼻づまりや口呼吸の対策には、鼻腔拡張テープやマウステープなどの市販グッズの使用、もしくは加湿器の使用がおすすめです。
一方で、鼻づまりが原因で生じている口呼吸に対しマウステープを使用すると、呼吸が苦しくなってしまうため、あくまで自然と口呼吸が多い方に対して使用するように注意しましょう。
頭痛への一時的な対処をする
いびきと頭痛が同時に起きる場合、先にまず頭痛への一時的な対処をすることも手段の1つです。
いびきはあくまで睡眠中に起こる症状であり自覚できませんが、頭痛は起床時や日中に自覚できてしまう症状であり、日常生活に与える影響も大きいため、優先して改善すべきです。
例えば、緊張型頭痛の場合、筋緊張を緩和するために頚部や後頭部を温めることで症状を緩和できますが、片頭痛の場合は血管拡張による頭痛であるため、むしろ頭部を冷却することで血管が収縮し、症状の改善が期待できます。
また、寝起き直後の頭痛の場合、寝姿勢による筋肉への負担が原因の可能性が高いため、温めることで緩和できる可能性が高いです。
このように頭痛の原因によってとるべき対処法も異なるため、注意が必要です。他にも、鎮痛剤などの市販薬も必要に応じて活用しましょう。市販で購入できるロキソニンやカロナールには鎮痛効果があるため、頭痛改善が期待できます。
一方で、長期間の常用や過量内服によってさまざまな合併症・副作用を生じる可能性もあるため、あくまで一時的な使用に留め、頭痛が頻発する場合は医師に相談しましょう。
改善しない場合は医療機関を受診する
上記のようなセルフケアを実践してもいびきと頭痛が改善しない場合は、医療機関を受診するのも1つの選択肢です。
多くの場合、いびきやそれに伴う頭痛は上記のようなセルフケアで改善できますが、何らかの病気を発症している場合、セルフケアでの改善は困難です。
特に、睡眠時無呼吸症候群や脳血管障害などの病気はいびきと頭痛を併発する可能性があり、また放置すれば命に関わる事態に発展する可能性もあるため、早期発見・早期治療が求められます。
睡眠中の呼吸停止や日中の強い眠気を認める睡眠時無呼吸症候群の場合、専門の睡眠外来を受診することで、原因を特定できます。
朝方に繰り返す頭痛や後頭部の重さが続く場合、頭痛の原因精査のために脳神経内科などで検査を受けることをおすすめします。
実際に「いびき・頭痛」で悩んでいた方の体験談と改善事例
いびきや頭痛でお悩みの方は、その原因や経過、治療方法など、人によって千差万別です。他の人がどのようなきっかけで自覚し、どのような方法で改善できたかを知ることで、自身のいびきや頭痛の改善にも役立てることができます。
そこで、ここでは実際に「いびき・頭痛」で悩んでいた方の体験談と改善事例を3つ紹介します。
20代女性:レーザー治療で改善した事例
20代女性のAさんは会社員として働いており、これまでいびきなど指摘されたことはありませんでした。日々規則正しい生活を送っており、食事や睡眠も至って健康的だったそうです。
しかし、ある日鼻汁や鼻詰まりを認め、それとともに同居する家族からはいびきを指摘されるようになりました。朝起きると口腔内が乾燥しており、特に左側に強い頭痛を感じたそうです。頭痛は時折激しく、また日中には眠気や集中力の低下も認め、仕事に集中できなくなってしまったため、鼻づまりの影響と判断し、市販の点鼻薬や鼻腔拡張テープを使用して対策しました。
使用当初は症状が改善し、いびきも一時的に緩和されましたが、徐々に点鼻薬の効果も薄れてしまい、すぐにいびきや頭痛が再燃したそうです。
そこで、医療機関に受診したところ、副鼻腔炎に伴ういびき・頭痛と診断され、症状改善のために内服療法とレーザー治療で粘膜を切除しました。
術後数日は鼻汁や痛みが続いたものの、1週間ほど経過した頃には完全に鼻づまりは解消され、いびきや頭痛も解消されました。起床時の口の渇きや日中の集中力低下も同時に解消され、仕事に集中できるようになったそうです。
40代男性:CPAP治療で改善した事例
40代男性のBさんはデスクワークがほとんどで、運動習慣もないため、40代に入ってから体重が増加傾向でした。いびきを以前から妻に指摘されていたものの、最近になってさらに音が悪化したため、ついには別の寝室で寝て欲しいと言われて大変ショックだったそうです。
また、いびきのせいで夜中に目が覚めてしまったり、朝に頭重感を感じることも多く、仕事にも支障をきたしていたため、妻からの指摘を機にいびき改善を目指すことを決めたそうです。
ネットで検索したところ、横向きで寝ることでいびきの改善が図れると知り、実践したところ、確かに少々の改善は認めたものの、横向き寝を維持できないことも多く、根本の改善にならないため、睡眠外来を受診する運びとなりました。
そこでPSG検査を行ったところ、中等度の睡眠時無呼吸症候群を指摘され、CPAP療法を行うことになりました。CPAP療法導入後、顕著にいびきは改善し、頭重感の改善とともに、妻からも褒められたそうです。
60代男性:生活習慣の是正で改善した事例
60代男性のCさんは定年間近のサラリーマンで、普段から深夜に食事することも少なくなく、寝る前は必ず飲酒や喫煙もしていました。一緒に暮らす妻や子供から以前からいびきを指摘されており、特に飲酒量の多い日はいびきがうるさいと文句を言われていました。
また、朝起きると日中まで頭痛を伴うことが多く、日中に強い眠気に襲われることもあり、仕事に集中するのが難しい日も少なくありませんでした。
いびきと頭痛には関連があることを知り、いびき改善のために市販の口閉じテープを購入しましたが、肌に合わずかぶれてしまったため、仕方なく近隣のクリニックを受診したそうです。
そこで、まずは特別な治療よりも前に生活習慣を是正するよう注意され、できるだけ就寝の3時間以上前に食事は終わらせ、過剰な飲酒・喫煙は控え、可能な限り定期的に運動するように指示されました。
それ以降、できる限り医師からの指導を守って生活習慣を是正したところ、開始から2週間経過した頃から徐々にいびきの頻度や音量が低下したそうです。起床時の頭痛や日中の眠気も改善し、快活に仕事に取り組めるようになったそうです。
いびきと頭痛が同時に起きるのは病気のサイン?受診すべきタイミング
いびきと頭痛が同時に起きた場合、もしかして自分は病気かもしれないと不安を抱く方も少なくないでしょう。実際に、何らかの病気を発症している可能性もあり、中には命に関わるような病気の可能性もあるため、早期発見・早期治療が肝要です。
そこで、ここではいびきと頭痛が同時に起きた場合の危険なサインや受診すべきタイミングについて紹介します。
日中の眠気・集中力低下もある場合は要注意
いびきと頭痛が同時に起きている人の中で、日中の眠気・集中力低下も認める場合は要注意です。いびきの程度が重度になっていくと、睡眠中に取り込める酸素量が低下し、脳や身体に大きな負担がかかります。低酸素状態になった脳にできる限り多くの酸素を供給するため、脳血管が拡張することで頭痛が生じます。
しかし、それでも脳に十分な酸素を供給できないと、脳は十分な休息を得ることができず、日中に我慢できないほどの眠気が生じたり、集中力が低下してしまうのです。
つまり、これらの症状を認めるということは、それだけいびきの程度が重く、身体に負担がかかっているということになります。
これらの症状によって日中の学業や仕事にも支障をきたす可能性があり、最悪の場合、異常な眠気が原因で交通事故や転倒・転落を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
上記のような症状を認める場合、事故に至る前に早期に医療機関を受診しましょう。
朝起きたときの頭痛が続くなら睡眠外来へ
いびきと頭痛が同時に起きていて、起床時の頭痛が継続してしまう場合は睡眠外来に受診しましょう。朝起きたときの頭痛が続く場合、原因としては寝姿勢が合っていない・脱水・片頭痛・緊張型頭痛・睡眠不足・睡眠時無呼吸症候群・高血圧・脳腫瘍など、さまざまな疾患の可能性が考えられ、放置すると命に関わるような可能性のある病気もあるため、早期診断・早期対策が重要です。
一時的な頭痛であれば感染症や風邪などの可能性もあり、発症初期は市販薬で改善を目指すのも1つの手です。感染症や風邪であれば市販薬でも改善できる可能性はありますが、それでも改善できない場合や長期的に起床時の頭痛が生じる場合、睡眠時無呼吸症候群や脳腫瘍など、重篤な疾患の可能性があるため、注意が必要です。
睡眠外来であれば、いびきやそれに伴う頭痛の原因を精査でき、原因に合った適切な治療を早期に実行できるため、少しでも不安があれば一度受診してみると良いでしょう。
脳の病気や高血圧の可能性も
いびきと頭痛が同時に起きた場合、脳の病気や高血圧の可能性もあるため、注意が必要です。いびきが重度になって睡眠中取り込める酸素の量が低下すると、身体は持続的な低酸素状態に陥り、そのストレスによって交感神経系が活性化します。その結果、長期的には高血圧や糖尿病、脳血管障害や心不全などの疾患の発症リスクが上昇することが知られており、重度の高血圧や脳血管障害では頭痛が主症状となりうるため、いびきと頭痛を抱えている方は注意が必要です。
また、脳血管障害を実際に発症している場合、舌の運動機能低下や意識障害などによって舌根沈下が起こりやすくなることもあり、いびきが悪化する可能性もあります。
このように、いびきと頭痛が併発している場合、緊急性を要する疾患を発症している可能性があり、対応が遅れて脳梗塞や脳出血が進行すれば、麻痺やしびれなどの後遺症が残ってしまうため、早期発見・早期治療のためにも医療機関に受診しましょう。
【まとめ】いびきと頭痛が同時に起きる場合は軽視せず、原因を見極めて対策を
この記事では、いびきと頭痛が同時に起きる場合の原因や改善策、実際の体験談などについて詳しく解説しました。
いびきと頭痛が同時に出る場合は、寝姿勢や生活習慣など、セルフケア可能な問題が原因であることもあれば、睡眠時無呼吸症候群や副鼻腔炎などの耳鼻科疾患、脳血管障害など、重篤な疾患を発症している可能性もあるため、注意が必要です。
いびきと頭痛を放置すれば日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害を引き起こすリスクも上がってしまうため、たかがいびきや頭痛だと軽視せず、早期に医療機関を受診して、原因を精査することが重要です。
一方で、自身のいびきや頭痛が医療機関を受診すべき程度なのか自信が持てず、医療機関への受診を躊躇してしまう方も少なくないでしょう。
下記の記事では、いびきの危険度をセルフチェックする方法について詳しく解説しているため、ぜひご一読ください。
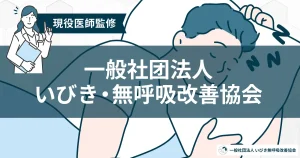
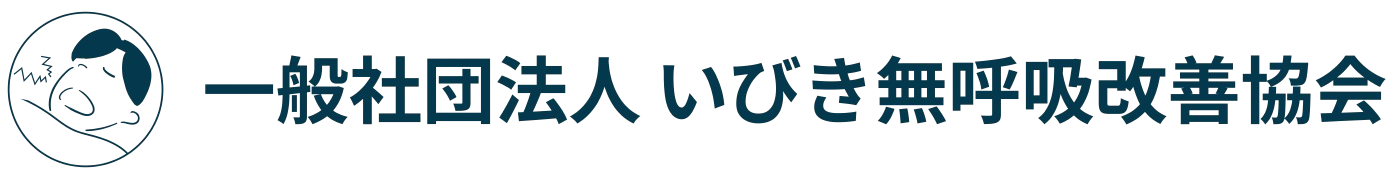
コメント