- うつ伏せ寝でいびきが改善するって本当?
- うつ伏せ寝を実践する際にどのようなことに注意すべき?
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
うつ伏せ寝は仰向け寝よりも気道の狭窄が生じにくく、いびきが改善する可能性が高いです。
一方で、うつ伏せ寝にはさまざまな注意点もあるため、実践する前にリスクを知っておくことも重要です。
そこでこの記事では、いびきにうつ伏せ寝が効果的な理由やうつ伏せ寝の注意点、実際の体験談など詳しく解説します。この記事を読むことで、いびき改善のためにうつ伏せ寝を効果的に実践でき、より良い睡眠を得ることができるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
いびきにうつ伏せ寝が効果的な理由
いびきは気道の狭窄が原因であり、特に仰向けはいびきをかきやすいですが、横向き寝やうつ伏せ寝はいびきが改善しやすいことが知られています。
いびきにうつ伏せ寝が効果的な理由は主に下記の3つです。
それぞれについて詳しく解説します。
舌が喉の奥に落ちにくくなる
いびきにうつ伏せ寝が効果的な理由は、舌が喉の奥に落ちにくくなるためです。
いびきは睡眠中に空気が気道を通過する際に生じる気道粘膜の振動音であり、何らかの原因による気道の狭窄が主な原因です。中でも多い原因は舌根沈下であり、睡眠中は舌の筋肉が弛緩してしまうため、舌自体の重みによって舌根が沈下してしまいます。
仰向け寝の場合、舌が弛緩するとそのまま後方の気道の方向に舌根沈下してしまうため、気道狭窄の原因となりますが、うつ伏せ寝の場合、舌が後方に沈下しにくく、喉の奥に落ちにくいため、最もいびきをかきにくい寝姿勢と言えます。
また、鼻詰まりなどが原因で睡眠中に口呼吸をしてしまう場合も、吸気時に開口する際、下顎が後下方に移動することで舌が喉の奥に落ちやすくなりますが、うつ伏せ寝であれば下顎が後方に移動することを防ぐことができるため、より舌根沈下が起こりにくく、いびき予防に有用です。
重力の影響を受けにくくなる
いびきにうつ伏せ寝が効果的な理由は、重力の影響を受けにくくなるためです。気道は軟骨や筋組織、靭帯などさまざまな構造物で形成されており、気道の前方(腹側)を脂肪組織や血管・神経など、さまざまな組織が覆っています。
気道の形状が保持されるように、気道前面(腹側)には軟骨が存在しており、周囲の組織からの圧排を防いでいますが、仰向けで寝るとこれらの組織が重力によって後方の気道に重くのしかかり、気道を狭窄させる可能性があります。
特に、肥満の方の場合は首周りの脂肪が多く、より気道が圧迫されやすくなるため、注意が必要です。
一方で、うつ伏せ寝の場合は気道が重力の影響を受けにくくなり、組織がのしかかることもなくなるため、気道が開通しやすく、いびきをかきにくくなります。さらに、うつ伏せ寝の場合は舌も重力によって後方ではなく前方に突出するため、後方の気道への影響が少なく、いびきが解消される可能性が高まります。
無呼吸のリスクが減る可能性がある
いびきにうつ伏せ寝が効果的な理由は、無呼吸のリスクが減る可能性があるためです。いびき=気道が狭窄している状態であり、症状が進行すると睡眠中に十分量の空気を肺に取り込めなくなり、この状態は低呼吸、もしくは無呼吸と定義されます。
- 低呼吸:10秒以上持続する気流の低下で、酸素飽和度が3%以上低下、または覚醒反応を伴う状態
- 無呼吸:10秒以上の呼吸停止
仰向け寝の場合、先述したような理由で気道が狭窄しやすく、低呼吸や無呼吸のリスクは増加するため、注意が必要です。
一方で、気道への影響の少ない横向き寝やうつ伏せ寝の場合、無呼吸のリスクが減る可能性があります。
実際に、低呼吸や無呼吸の頻度が増加する病気である睡眠時無呼吸症候群の治療ガイドラインでは、体位療法(体位を変えて低呼吸や無呼吸を軽減する治療)を治療法の1つとしています。特に、重症度が低く、かつ若年者やBMI(肥満度を示す指数で、体重(kg)➗身長(m)➗身長(m)で算出可能)の低い患者においては体位療法が効果を示しやすいそうです。(参考文献:睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020)
一方で、うつ伏せ寝を行うための標準的なデバイスは開発されておらず、現時点では他の治療と比較して、あくまで補助的な治療法として位置付けられていることには留意すべきです。
いびき対策でうつ伏せ寝をする際の注意点
- いびき対策でうつ伏せ寝は安全?
- うつ伏せ寝を実践する際の注意点は?
このような疑問を抱かれる方も少なくないでしょう。
うつ伏せ寝はいびきを改善できる可能性がある一方で、下記のようなリスクもあります。
それぞれ解説します。
首・肩・腰への負担が大きくなりやすい
いびき対策でうつ伏せ寝をする際には、首・肩・腰への負担が大きくなりやすい点で注意が必要です。本来、最も身体への負担を少なく寝ることができる体位は仰向けであり、仰向けの場合は背骨の自然なS字カーブを保ちやすく、頸部や腰部に負担がかかりにくいです。
しかし、うつ伏せ寝の場合、呼吸するために頚部を捻って顔を横に向けるため、頸部の関節や筋肉に負担が生じます。
また、頸部の筋群は肩甲骨に繋がっていたり、肩の筋群と連動して動くことが知られているため、うつ伏せによって頸部に負担がかかる場合、そのまま肩にも負担がかかり、痛みや凝りの原因となるため、注意が必要です。
さらに、仰向け寝の場合は腰が重みによって少しだけ沈みますが、うつ伏せ寝の場合は反対に腰が反ってしまうため、腰椎や腰回りの筋群に負担がかかります。
これらの理由から、うつ伏せ寝は首・肩・腰の骨や筋肉・関節に負担がかかり、骨格の歪みの原因となる可能性もあるため、注意が必要です。
逆に呼吸がしづらくなることがある
いびき対策でうつ伏せ寝をする際には、いびきは生じにくくなる一方で、逆に呼吸がしづらくなることがあります。人は本来、吸気時に胸郭を形成する筋肉が機能し、胸腔を広げることで胸腔内圧を陰圧にし、それによって肺が拡張することで空気が肺の中に流入します。
しかし、うつ伏せ寝の場合は胸郭を形成する筋肉である内肋間筋・外肋間筋などが自重によって押しつぶされてしまうためうまく機能できず、胸郭の拡張運動が制限されてしまうため、胸腔が効果的に広がりません。
その結果、肺も十分に拡張できなくなるため、1回の呼吸で肺に吸い込める空気の量(これを1回換気量と呼ぶ)が減少してしまいます。
この状態が長く続くと十分量の酸素を取り込めなくなり、低酸素状態によって息苦しさを自覚してしまうため、注意が必要です。上気道の開存にとってうつ伏せ寝は有効ですが、胸郭の呼吸運動に対しては抑制的に働いてしまうことを知っておきましょう。
消化器への圧迫や血流の妨げになる可能性がある
いびき対策でうつ伏せ寝をする際には、消化器への圧迫や血流の妨げになる可能性があるため、注意が必要です。胸部の臓器は、胸椎や胸骨・肋骨などで構成されている胸郭と呼ばれる骨格構造によって囲われており、外部からの圧力から守られています。
一方で、腹部の臓器は背中側は厚めの筋肉や脂肪組織、背骨で守られているものの、腹側は比較的守りが薄く、外部からの圧力の影響を強く受けてしまいます。そのため、うつ伏せ寝によって自重が腹部を圧迫する時間が長引くと、腹部臓器である胃や十二指腸、小腸・大腸などの消化管や、肝臓・膵臓などの臓器が直接的に圧迫されてしまう可能性が高いです。
その結果、胃酸の逆流や消化の遷延、便秘など、なんらかの胃腸症状を来す可能性があります。さらに、これらの臓器を栄養する動脈が長期間圧迫されると、臓器への血流が悪化し、壊死や機能障害、血栓形成を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
いびきの根本原因によっては逆効果の場合もある
いびき対策でうつ伏せ寝をする際には、いびきの根本原因によっては逆効果の場合もあります。うつ伏せ寝の場合、舌や下顎が前方に突出しやすい体位のため、基本的には後方の気道が広がりやすいですが、呼吸するためには口を枕に埋めるわけにはいかず、首だけ捻って横向きにする必要があります。
その際、頸部は左右いずれかに90度近く回旋する必要があるため、さらに気道の狭窄が悪化したり、頚部の痛みによるストレスが身体に負担をかける可能性があり、注意が必要です。
例えば、いびきの根本的な原因が咽頭部の腫瘍などの場合、物理的に気道が狭窄している状態のため、うつ伏せ寝によって改善が得られる可能性が低く、さらに頚部の回旋運動によってむしろ狭窄が悪化する可能性すらあります。
そのため、必ずしもうつ伏せ寝ならいびきが改善すると考えず、まずはうつ伏せ寝を行うべきいびきかどうか、しっかりと原因を検索することが重要です。
実際にうつ伏せ寝でいびきが改善した人の体験談
- 実際にうつ伏せ寝でいびきが改善した人はいるの?
- どのようにうつ伏せ寝を実践したの?
このような疑問をお持ちの方に向けて、ここでは実際にうつ伏せ寝でいびきが改善した人の体験談を3つ紹介します。
うつ伏せ+枕変更で劇的に改善した20代男性の例
20代男性のAさんは以前からいびきを家族から指摘されており、特に最近は体重が増加したことでいびきの程度も悪化していました。さらに、起床時の眠気や日中の耐え難い眠気に襲われるようになり、会社員として働く上で業務にも支障をきたすようになったため、改善を試みました。
ネットで検索し、いびきにはうつ伏せ寝が良いと知ったため、実際に取り組んでみたところ、仰向け寝の時には丁度良いと感じていた枕の高さがやや高く感じ、うつ伏せ寝をしても頚部が強く回旋してしまい、思ったようないびきの改善は得られなかったそうです。
そこで、Aさんはもう少し低めの枕を購入して再度うつ伏せ寝を実践したところ、枕の変更前よりも頚部への負担が軽減し、呼吸もしやすくなったそうです。それと同時に、家族からもいびきが劇的に改善していると指摘され、起床時の倦怠感や日中の眠気も顕著に改善が認められました。
今回のことをきっかけに、睡眠中の体位や枕の高さが、いびきの有無や生活の質にとって非常に重要であることを認識できたそうです。
仰向け→横向き→うつ伏せと試して変化した40代女性の例
40代女性のBさんは出産や育児を契機に専業主婦となり、外を出歩く機会も減ったためか、数年で体重が10kg近く増加していました。同居する夫からは「ここ最近いびきがうるさくて一緒に寝るのが辛い」と言われ、その言葉にショックを受けて改善を心に決めたそうです。また、大きく口を開けていびきをかいていたため、起床時の口の乾燥も目立っていました。
ネットで調べたところ、横向きやうつ伏せ寝がいびきの改善に有効であると知り、まずは横向き寝を実践したところ、一定のいびきの改善を認めたそうです。
それ以降は横向き寝を維持できるように抱き枕を購入して寝ていたそうですが、さらに体重が増加すると横向き寝の効果が薄れ、再びいびきの音が大きくなってしまいました。
そこで、更なる改善のためにうつ伏せ寝を実践したところ、横向き寝の時よりもさらにいびきが改善され、口腔内の乾燥も気にならなくなったそうです。
市販のうつ伏せ寝グッズを活用して改善した50代男性の例
50代男性のCさんは会社員として日々多忙であり、夜遅くに夕食を食べたり、就寝直前まで飲酒や喫煙を繰り返していました。
特に深酒をした日はいびきが大きく、家族からは「時折呼吸が止まっている時がある」と指摘されていたそうです。
不安になって調べたところ、うつ伏せ寝がいびき改善のために有効であると知り、実際に実践してみたところ、思った以上に寝苦しく継続できなかったため、市販のうつ伏せ寝グッズを購入しました。
うつ伏せ専用の枕で、うつ伏せ寝でも頚部に過度な負担が掛からず、自然と顔が横向きになることで楽に呼吸できる枕を購入したところ、苦痛なくうつ伏せ寝を継続できるようになったそうです。
うつ伏せ寝を実践したところ、軽度のいびきを認めるものの、深酒しても無呼吸に陥ることはなくなり、家族も安心できたそうです。市販グッズといえど、簡単に購入できて、かついびき改善に効果的であったため、同様のお悩みを持つ方にはぜひ試してほしいと実感されています。
【うつ伏せ寝以外】いびきを根本的に改善するための方法
うつ伏せ寝は確かにいびき改善に有効ですが、上記で紹介したようにいくつかの注意点を認め、また根本的な原因の解決にはならないため、あくまで対症療法です。
そこで、うつ伏せ寝以外でいびきを根本的に改善するための方法を4つ紹介します。
生活習慣の見直しをする
いびきを根本的に改善するための方法として、生活習慣の見直しが最も重要です。生活習慣はいびきの発症に深く関わっており、不適切な生活習慣によって気道の狭窄が進み、いびきが生じてしまいます。
例えば、暴飲暴食によって肥満になると首周りに脂肪が沈着し、気道の狭窄を招きます。また、就寝直前までの飲酒や喫煙は、アルコールやタバコに含まれる薬理作用によって気道の浮腫や舌の弛緩を引き起こし、やはり気道の狭窄を引き起こすため注意が必要です。
他にも、冷房を過剰に効かせてしまうと、吸い込む空気が寒冷・乾燥し、気道における炎症の原因となり、いびきを引き起こしやすくなります。
このように、何気ない生活習慣が実はいびきの原因となることは少なくないため、これを機に改めて見直してみる良いでしょう。
なお、高すぎる枕の使用や腰の沈みすぎるマットレスの使用など、頚部の過度な屈曲を招くような寝具の使用はいびきの原因となるため、生活習慣の見直しとともに、就寝環境の見直しも同時に行なってみると良いでしょう。
鼻づまり・口呼吸を改善する
いびきを根本的に改善するための方法として、鼻づまりや口呼吸の改善もおすすめです。
ヒトは本来、就寝中は鼻呼吸を行い、流入する空気は鼻粘膜で加湿加温され、かつ空気中のゴミが除去されるため、気道にとって優しく綺麗な空気が流入します。
しかし、副鼻腔炎や鼻茸、アレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲症などによって鼻粘膜の腫脹や鼻腔の狭小化が生じると鼻呼吸が困難となり、口呼吸が増加してしまいます。口呼吸の場合、流入する空気は加湿加温されず、ゴミも回収されず、気道の炎症やそれに伴ういびきを招く原因となるため、注意が必要です。
さらに、口呼吸では吸気時に下顎が後下方に下がり、それによって後方の気道が圧迫されるため、さらにいびきを描きやすくなります。
以上のことからも、鼻づまりやそれに伴う口呼吸の増加はいびきの原因となるため、原因に応じて適切な治療を行うことが重要です。特に、鼻中隔湾曲症は鼻中隔の変形に伴う物理的な鼻腔の閉塞が原因であるため、改善のためには点鼻薬や市販グッズでは困難であり、手術が必要となります。
CPAPやマウスピースなどの医療機器を使う
いびきを根本的に改善するための方法として、CPAPやマウスピースなどの医療機器の使用もおすすめです。
CPAPやマウスピースはどちらも睡眠時無呼吸症候群の治療に用いられるデバイスであり、気道の開通性を高めることでいびきの改善が得られます。自身の歯列や骨格に合ったマウスピースを装着することで、下顎が後下方に下がることを避け、前方で固定できるため、気道が狭窄しにくくなります。
また、CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)とは持続陽圧呼吸療法のことで、睡眠中に専用マスクを装着し、マスクから常に気道に空気を流入させることで、特に吸気時に気道が狭窄・閉塞することを防ぐ治療法です。
CPAP療法は、日中の眠気など伴う中等度~重度の睡眠時無呼吸症候群に対しては第一選択の治療法であり、長期的には睡眠時無呼吸症候群に伴う心血管障害リスクを軽減させることが知られています。
なお、これらの治療を受けるためには医療機関での特殊な検査によって、睡眠時無呼吸症候群の診断や重症度判定を受ける必要があります。
レーザー治療や手術を検討する
いびきを根本的に改善するための方法として、いびきの原因によってはレーザー治療や手術療法も検討しましょう。例えば飲酒や喫煙によって一時的に気道の浮腫や舌根沈下を認め、それによって気道が狭窄していびきをかいている場合は、飲酒や喫煙を控えることで気道の再開通が期待でき、症状が改善する可能性が高いです。
一方で、慢性的な副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などによって鼻粘膜の浮腫や炎症を繰り返すと、徐々に鼻粘膜は肥厚し、鼻腔の狭窄が元に戻らなくなってしまいます。その結果、いびきが慢性化してしまい、点鼻薬や抗アレルギー剤にも反応しなくなってしまうため、そこまで症状が進行した場合は肥厚した粘膜をレーザー治療で焼却する必要があります。
また、先述したように鼻中隔湾曲症が原因の場合は、粘膜の問題ではなく、骨そのものの湾曲が原因であるため、仮にレーザー治療を行なって粘膜を焼却しても意味がありません。改善のためには湾曲した骨そのものを切除する必要があるため、適切な治療のためにはいびきの原因をまずは解明することが重要です。
【まとめ】いびきの原因を探って自分に合う寝方や治療法を見つけよう
この記事では、いびきに対するうつ伏せ寝の有効性や注意点、実際の体験談を紹介しました。
うつ伏せ寝によって気道の拡張が期待でき、仰向けでは閉塞していた気道が開通することでいびきの改善が期待できます。一方で、うつ伏せ寝によって、頸部や腰部への負担がかかったり、腹部臓器の圧迫による吐き気など、さまざまな注意点もあります。
また、例えうつ伏せ寝を行なっていびきが改善したとしても、根本的な解決にはならないため、いびきの原因を検索し、その原因にあった適切な治療を行うことがいびき対策の上では何より重要です。
なお、適切な原因検索のためには医療機関での精査が必要不可欠ですが、自身のいびきが医療機関を受診するほどの程度なのか自信を持てないと言う方も少なくないでしょう。
そこで、下記の記事では自身のいびきの危険度を簡単にセルフチェックする方法を紹介しているため、いびきにお悩みの方はぜひご一読ください。
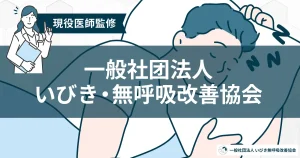
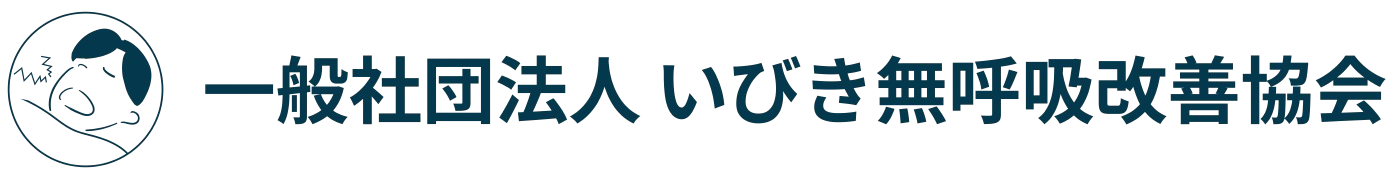
コメント