いびきと歯ぎしりがひどいと、自身や周りの人の睡眠を妨害してしまうため、誰かと寝るのが恥ずかしいと感じている人も少なくないでしょう。
いびきと歯ぎしりが両方ひどい場合、何らかの原因で気道が狭窄し、睡眠中に取り込める酸素量が低下していることで睡眠の質が低下している可能性があります。
放置すればさまざまな健康被害を招く可能性も高まるため、この記事では、いびきと歯ぎしりがひどい原因や自分でできる対策について詳しく解説します。
この記事を読むことで、いびきと歯ぎしり両方の原因を解消でき、質の高い睡眠を取り戻すことができるようになるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
いびきと歯ぎしりがひどい・両方起こる原因は?
実はいびきと歯ぎしりには相関関係が認められ、何らかの原因によっていびきと歯ぎしりがひどくなる、もしくは同時に両方が起こる可能性があります。また、それぞれの原因によって解決方法や対処法も異なるため、注意が必要です。
ここでは、いびきと歯ぎしりがひどい・両方起こる主な原因を3つ紹介します。
ストレスや自律神経の乱れ
いびきと歯ぎしりがひどい・両方起こる原因として、ストレスや自律神経の乱れが挙げられます。
ストレスがかかると自律神経のバランスが乱れ、副交感神経に対して交感神経が優位になりますが、これによって脳は活性化してしまうため、就寝中も脳が十分に休むことができず、睡眠の質が低下することで歯ぎしりの原因となるのです。
また、ストレスがかかっていると、脳はより多くの酸素を吸い込もうとするため、より多くの空気を吸い込むことができる口呼吸の割合が増加します。
口呼吸の際、吸気時には下顎が後下方に移動し、下顎の後方に位置している気道が狭窄しやすくなるため、口呼吸の増加によっていびきもかきやすくなります。
さらに、口呼吸の増加に伴う気道狭窄は低酸素状態を悪化させ、さらにストレスがかかり、交感神経のさらなる活性化につながってしまうため、より歯ぎしりが起こりやすい状態が誘発されるという悪循環に陥る可能性が高く注意が必要です。
噛み合わせや顎の問題
いびきと歯ぎしりがひどい・両方起こる原因として、噛み合わせや顎の問題も挙げられます。噛み合わせが悪いと、上下の顎の筋肉が過剰に緊張してしまうため、歯ぎしりを引き起こす原因となります。
また、歯ぎしりによって歯がすり減ると、それによって噛み合わせが悪化し、さらに歯ぎしりが生まれやすくなるという悪循環に陥るため、注意が必要です。歯ぎしりが続くと顎や舌の位置も不安定になるため、結果として気道が狭まり、いびきが出やすくなる場合もあります。
特に、生まれながらに顎の小さい方は注意が必要です。顎が小さい方は下顎が後方に引っ込んでいる可能性があるため、下顎の後方にある気道がより狭窄しやすく、噛み合わせが悪い場合や歯ぎしりによってさらにいびきをかきやすい状態です。
また、噛み合わせは先天的な問題のみならず、抜歯や虫歯の治療などによっても悪化する可能性があるため、常に悪化するリスクを伴います。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性
いびきと歯ぎしりがひどい・両方起こる原因として、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性も挙げられます。睡眠時無呼吸症候群とは、何らかの原因で気道が狭窄し、睡眠中に取り込める酸素量が低下することでさまざまな健康被害を及ぼす病気です。
狭い気道を空気が通過する際、気道の粘膜には振動が生じるため、その振動音としていびきが鳴ります。また、取り込める酸素量の低下は身体にとってストレスとなり、交感神経が活性化することで中途覚醒の増加や睡眠の質の低下につながります。
睡眠の質やストレスは歯ぎしりを引き起こしやすくするため、結果としていびきと歯ぎしりが同時に出現する原因となるため、注意が必要です。
下記のような症状を認める方は睡眠時無呼吸症候群の可能性があるため、医療機関への受診を検討しましょう。
- 起床時に頭痛・倦怠感など認める
- 日中に激しい眠気を感じる
- 仕事や学業への集中力が低下している
- いびきが大きい
- 夜間途中で覚醒してしまう
- 生活習慣病を発症している
いびき・歯ぎしりがひどいときに自分でできる対策
いびきや歯ぎしりを放置すれば、歯や顎にダメージが蓄積したり、自身や共に暮らすパートナーの睡眠の質の低下を引き起こす可能性があります。
長期的には、生活習慣病の発症リスクが増大することも知られており、早期対策が必要です。
そこで、ここではいびき・歯ぎしりがひどいときに自分でできる対策を3つ紹介します。
どれも今日からでも実践できる内容のため、ぜひ試してみましょう。
生活習慣の改善
いびき・歯ぎしりがひどいときに自分でできる対策として、まずは生活習慣の改善が重要です。生活習慣の乱れはストレスの蓄積や自律神経の乱れ、睡眠時無呼吸症候群の発症に寄与するため、放置することでいびき・歯ぎしりが同時に悪化する原因となります。
特に、下記のような生活習慣を送っている方は注意が必要です。
- 夜間の暴飲暴食を繰り返している
- 過剰な飲酒や喫煙
- 出不精で運動不足
- 睡眠時間が不定期で寝不足
- 睡眠薬を常用している
- 趣味やストレス発散の機会がない
上記のような方は歯ぎしりといびきが同時に出やすいため、早期から是正すべきであり、特に注意が必要なのは過剰な飲酒や喫煙です。
飲酒や喫煙は気道に炎症や浮腫をもたらし、舌根沈下も引き起こされるため、いびきの原因となります。
また、それに伴い睡眠の質の低下も引き起こすため、歯ぎしりが起こりやすくなる原因です。
他にも、動脈硬化の進展や生活習慣病の発症リスク増大など、さまざまなリスクを伴うため、できる限り飲酒・喫煙は控えましょう。
睡眠環境の見直し
いびき・歯ぎしりがひどいときに自分でできる対策として、睡眠環境の見直しも重要です。睡眠環境は睡眠の質と強く関係しており、睡眠環境が劣悪だと睡眠の質が著しく低下し、歯ぎしりが出現したり、いびきを引き起こす原因にもなります。
例えば、高すぎる枕や柔らかすぎるマットレスの使用は、頭部と腰部の高低差が生まれることで頚部の過剰な屈曲を引き起こし、気道の狭窄やいびきの出現、さらには睡眠の質の低下による歯ぎしりにつながります。
逆に硬すぎるマットレスの使用は身体に痛み刺激が加わり、そのストレスで歯ぎしりが起こりやすくなるため、注意が必要です。
また、いびきや歯ぎしりの対策には寝姿勢も重要です。仰向け寝が多い人の場合、重力に伴って舌根沈下が起こりやすく、横向き寝やうつ伏せ寝と比較していびきをかきやすく、睡眠の質が低下することで歯ぎしりのリスクも上がります。
睡眠の質を向上させるためにも、自身の身体に合った寝具の使用や適切な寝姿勢を保ちましょう。
舌のトレーニング
いびき・歯ぎしりがひどいときに自分でできる対策として、舌のトレーニングもおすすめです。舌のトレーニングを行うことで舌の筋力の維持・向上が図れ、舌根沈下を予防することができるため、いびきや歯ぎしりの改善が期待できます。
また、舌の位置が適切でない場合、噛み合わせが悪くなって歯ぎしりが起こったり、口呼吸の割合が増加することでいびきが増える原因となります。
そこで、舌のトレーニングは舌のポジションの適正化も図れるため、舌の位置異常におけるいびきや歯ぎしりの改善に有用です。
具体的な舌のトレーニング方法は主に下記の通りです。
- あいうべ体操:「あー」「いー」「うー」「べー」と口に形を順番に変えて動かす
- 舌の体操:舌を上下左右前後方向に動かす
どちらの体操も舌を動かすことで舌の筋力の維持・向上や、舌の位置の適正化、さらには唾液腺を刺激することで唾液分泌を促進し、口腔内の自浄作用をもたらします。
なお、舌のトレーニングは即効性が高い対処法ではなく、毎日継続的に行ったとしても効果が出るまでに数週間〜数ヶ月の期間を要するため、継続性が重要です。
自力での改善が難しい場合は?病院で治す方法
上記のようなセルフケアを行ったとしても、いびきや歯ぎしりを自力で改善することが困難な場合、何らかの病気を発症している可能性があります。
原因や程度によっては医療機関での専門的な検査・治療が必要となるため、セルフケアで改善困難な場合は必ず医療機関の受診を検討しましょう。
ここでは、病院で治す方法や、各治療を受けるために受診すべき診療科について3つ紹介します。
マウスピース
いびきや歯ぎしりの改善が困難な場合、医療機関でのマウスピース療法が選択肢の1つです。マウスピースの装着によって下顎が前方に固定されるため、下顎や舌の後方に位置する気道の狭窄を予防することができ、いびきの改善を目指せます。
特に口呼吸が原因でいびきをかいている人で、起床時の口渇感を認める人やいびきの音が大きくて低い人には向いている治療法です。また、気道が広がれば睡眠の質も改善し、歯ぎしりが生じるリスクを間接的に軽減できる可能性もあります。
さらに、仮に歯ぎしりがあったとしても、マウスピース装着によって歯の損傷を予防することもできます。
一方で、自身の顎や歯列の骨格に不適切なマウスピースの装着は、口内炎や歯の痛み、虫歯や歯周病の増加、歯根吸収、顎関節への悪影響など、さまざまな副作用を引き起こす原因ともなるため、必ず歯科や口腔外科で自身用に作製したものを使用すべきです。
CPAP
いびきや歯ぎしりの改善が困難な場合、医療機関でのCPAP療法も選択肢の1つです。CPAP療法とはContinuous Positive Airway Pressure(持続陽圧呼吸療法)の略であり、専用のマスクから持続的に空気を気道に送ることで、気道の狭窄を予防し、いびきの改善を図ります。
CPAPによって気道の開通性が向上すれば、いびきが改善するだけでなく、睡眠の質の向上も目指せるため、同時に歯ぎしりの出現を予防する効果も期待できます。
実際に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020において、睡眠時無呼吸症候群によって日中の眠気症状など強い場合や、中等度〜重症例の治療法として、CPAP療法は第一選択です。
実際にCPAP療法を導入する場合には、耳鼻咽頭科や呼吸器内科、睡眠外来などで実施されているPSG検査(ポリソムノグラフィー)を実施し、睡眠中の低呼吸や無呼吸の頻度を測定し、重症度を判定する必要があります。
レーザー治療
いびきや歯ぎしりの改善が困難な場合、医療機関でのレーザー治療も選択肢の1つです。人は本来睡眠中は鼻呼吸を行いますが、慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎、鼻茸などの耳鼻科疾患を発症した場合、鼻づまりによって鼻呼吸が困難となるため、口呼吸の割合が増加していびきや歯ぎしりが増悪します。
通常は点鼻薬などによって鼻づまりは解消しますが、症状が長期化すると徐々に鼻粘膜の肥厚が悪化し、点鼻薬でも十分な通気性を維持できなくなってしまいます。そこで、レーザー治療によって肥厚した鼻粘膜を焼却することで、物理的に鼻腔の通気性を改善させることができるのです。
特に、鼻汁や鼻づまりなどを認める方や、起床時の口渇感など強い方の場合、レーザー治療でいびきや歯ぎしりが改善できる可能性が高いです。実際に治療を受ける際には、原因や適応を判断するためにも、近隣の耳鼻咽喉科を受診する必要があります。
いびきと歯ぎしりで悩んでいた方の体験談と改善事例
- いびきや歯ぎしりは本当に改善するの?
- 実際に治った人はどのような方法で治したの?
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
いびきや歯ぎしりは原因によって改善方法も異なり、またその経過も個人差が大きいです。
ここでは、いびきと歯ぎしりで悩んでいた方の体験談と改善事例を3つ紹介します。
ぜひ自身のいびきや歯ぎしりの改善のヒントにしてみてください。
20代男性:マウスピース装着で改善した事例
20代男性のAさんはこれまで大きな病気もなく、至って健康に育ってきた会社員ですが、昔から滑舌が悪いことを気にしていたそうです。ある日、泊まりに来た彼女に「夜、大きく口を開けて、いびきや歯ぎしりがすごかった」と指摘され、初めて自身のいびきや歯ぎしりを自覚してショックを受けたそうです。
実際に自身のスマホで録音した音を聞くと、かなり大きな音に驚き、Aさんはそのショックから早期改善を心に決めました。そこで、近隣のいびき外来を受診したところ、いびきの原因は顎の骨格の影響が大きく、自身の歯列にあったマウスピースを作製する必要があると言われ、歯科を紹介されました。
歯科で作製したマウスピースを装着すると、下顎が前方に固定されることでいびきが改善し、マウスピースによって歯が保護されているため、歯ぎしりの音も緩和されたそうです。彼女の前で寝ることの不安や心配もなくなり、早期にいびき外来を受診して原因を解明できてよかったと感じたそうです。
40代男性:生活習慣の改善で改善した事例
40代男性のBさんはいわゆるサラリーマンとして日々多忙に働き、仕事柄夜に飲み歩くことも少なくなく、遅くまで飲酒や暴飲暴食をする機会も多い状態でした。これまで特に健康診断などでは異常を指摘されておらず、自身は健康だと思ってその生活を続けていましたが、40代に入ってから体重が徐々に増加していたそうです。
ある日、妻から「お酒を飲んだ日は特にいびきや歯ぎしりがうるさい」と指摘され、初めて自身のいびきや歯ぎしりを自覚しました。妻が夜間に起きてしまうくらいうるさく、何度か怒られたことから、いびき改善のために市販グッズ(口閉じテープ)を購入するも、寝苦しくなって途中で剥がしてしまったそうです。
そこで、近隣のいびき外来を受診したところ、生活習慣の改善とダイエットが最優先と指示され、暴飲暴食や過剰な飲酒は控えるようにしました。その3ヶ月後には徐々に体重が減少し、同時にいびきや歯ぎしりも改善したため、妻の機嫌も良くなり、今後も規則正しい生活を心がけようと自身に誓ったそうです。
60代男性:CPAP療法で改善した事例
60代男性のCさんは自営業で働いており、以前から検診で高血圧や糖尿病の指摘を受けていたため、生活習慣に気をつけながら生活していました。また以前から妻からはいびきを指摘されており、特にここ最近は歯ぎしりや無呼吸の頻度も悪化してきたため、医療機関を受診する運びとなりました。
睡眠外来を受診したところ、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いとのことで、入院して行うPSG検査を勧められたそうです。実際に検査を受けたところ、AHI(睡眠1時間あたりに起こる無呼吸(10秒以上の呼吸停止)と低呼吸(呼吸が浅くなる)の合計回数)が40回/時間と、重症の睡眠時無呼吸症候群であることが判明し、早期からCPAP療法を行う運びとなりました。
装着開始直後からいびきや歯ぎしりが顕著に改善し、以前は得られなかった熟睡感や起床時の爽快感を得られるようになったそうです。さらに、CPAP導入後、血圧値や血糖値も改善傾向にあり、もっと早くから治療すればよかったと、効果を実感できたそうです。
【まとめ】いびき・歯ぎしりがひどい場合は病院に相談しよう
この記事では、いびき・歯ぎしりがひどい場合の原因や対処法について詳しく解説しました。
いびきと歯ぎしりには相関性があり、いびきをかくような睡眠の質が低い方の場合、歯ぎしりも増え、また歯ぎしりによって口腔内の構造が変化することでいびきをかきやすくなることもあります。
どちらも放置すれば、睡眠の質の低下やさまざまな健康被害を及ぼすため、この記事で紹介したような生活習慣の改善・就寝環境の見直し・舌のトレーニングなど、セルフケアに努めましょう。
なお、セルフケアでも改善困難な場合は、何らかの病気が隠れている可能性もあるため、必ず医療機関に相談しましょう。
「いびきや歯ぎしりで病院に行くのは大袈裟?」と病院への受診を渋ってしまう方も少なくないと思いますが、放置してもいいことはありません。
自身のいびきの危険度を簡単にセルフチェックできる方法を下記の記事では詳しく解説しているため、まずはセルフチェックしてみましょう。
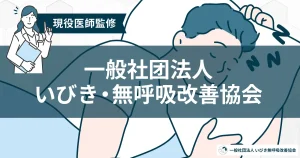
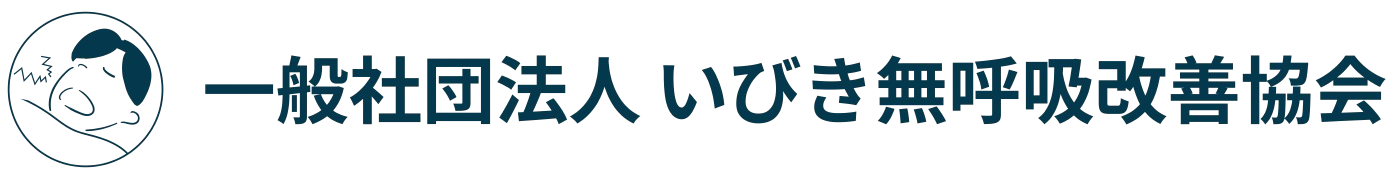
コメント