- 枕を変えることはいびき対策として効果なし?
- 枕でいびきが改善しない場合はどう対処すればいい?
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
使用する枕は睡眠の質やいびき対策において重要であり、枕の高さが身体にあっていないと、睡眠の質の低下やいびきが生じる原因となります。
一方で、枕の高さや硬さを適切化しても、原因によっては睡眠の質やいびきが改善しない可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、いびき対策としての枕の効果やそのほかの対処法、実際の体験談について詳しく解説します。この記事を読むことで、いびきに対して枕以外の適切な対処法も知ることができ、より良い睡眠を目指せるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
枕はいびき対策として効果ある?ない?
結論から言えば、枕はいびき対策として、根本的な改善にはあまり効果がありません。
枕の高さによって頚部の屈曲度合いが変わり、過剰な屈曲によって気道が狭窄するといびきが誘発されるため、過剰な屈曲は避けるべきです。
しかし、枕の高さを改善したとしても、下記のような要因を認める場合、いびきは改善されません。
それぞれ詳しく解説します。
枕では解決できない根本的な原因がある
枕では解決できない根本的な原因がある場合、枕の高さや硬さを調整してもいびきは改善されません。そもそも、いびきの原因は気道の狭窄であり、気道が狭窄することで通過する空気が粘膜を振動させていびきが生じます。
そのため、枕が高すぎると頚部が過剰に屈曲し、気道が狭窄することでいびきをかきやすくなるわけですが、それはいびきの原因となりうる1つの要因にしか過ぎず、他に何か異なる原因がある場合、枕を調整したとしてもいびきが改善されない可能性が高いです。
例えば、アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎などの鼻詰まりによる鼻いびきの場合、枕の高さを調整して頚部の屈曲を解除しても、鼻腔の狭窄は解除されないため、効果はありません。
他にも、顎が小さい、舌が落ち込んでいる、肥満など内因性の原因や、SAS(睡眠時無呼吸症候群)などの病気が隠れている可能性もあるため、枕の高さを最適化すれば必ずいびきが改善するというわけではありません。
枕の高さや硬さが合っていない
枕の高さを変えたとしても、枕の高さや硬さが合っていない場合、いびきが改善されない可能性があります。先述したように、枕の高さが高すぎる場合、頚部が過度に屈曲して気道が狭窄し、いびきをかきやすくなります。
一般的に、枕が7cm以上の高さの場合はいびきのリスクが高まることが知られているため、枕選びの際には寝心地と高さの両方に注意して選定すると良いでしょう。
また、枕の高さが7cm未満であったとしても、マットレスが柔らかすぎる場合、胸部や腰部が沈んでしまい、相対的に枕の高さが高くなってしまう可能性があるため、枕の高さだけでなく、マットレスの反発性も同時に見直すことが重要です。
一方で、枕が低ければ低いほど良いというわけでもありません。枕が身体に合わないほど低い場合、逆に肩や首が痛くなるなどの症状が出る可能性もあるため、あくまで自身の身体や骨格にフィットする高さや硬さの寝具を選ぶことが重要です。
生活習慣に原因がある
いびきの原因として生活習慣の乱れを認める場合、枕を変えてもいびきの改善が得られない可能性が高いです。
いびきは、枕による頚部の過度な屈曲が原因となることよりも、むしろ何らかの生活習慣によって生じている可能性が高く、生活習慣を改善しない限り是正されない可能性があります。
例えば、暴飲暴食や栄養バランスの偏った食事摂取は肥満を招き、首周りに多量の脂肪が蓄積することで気道が圧迫されるため、枕を変えたところで改善しないいびきの原因となります。
また、就寝直前までの過剰な飲酒は気道に浮腫をもたらし、またアルコールの筋弛緩作用によって舌根沈下も生じやすくなるため、これも気道狭窄によるいびきの原因です。
他にも、過剰な喫煙もいびきのリスクであり、喫煙によって気道に炎症が生じるため、炎症に伴う浮腫によって気道が狭窄することでいびきをかきやすくなります。
以上のように、日常生活の些細な行動や習慣が実はいびきの発症の原因となっていることは少なくなく、枕の高さや硬さを最適化しても、これらの原因が解消されていない場合はいびきは改善しないため、注意が必要です。
いびき対策として枕が効果がなかった場合の対処法
上記で紹介したように、いびきはさまざまな原因で生じるため、枕の最適化によって改善できるいびきには限りがあり、いびき対策としての枕の効果は限定的です。
そのため、いびき対策として枕が効果がなかった場合は下記のような対処法を実践することでいびきの改善を目指せます。
それぞれについて詳しく解説します。
鼻腔拡張テープやスプレーを使う
いびき対策として枕が効果がなかった場合、鼻腔拡張テープやスプレーを使うことも対処法の1つです。
枕を変えることで気道の屈曲を解消できたとしてもいびきが改善しない場合、鼻腔の狭窄がいびきの原因となっている可能性が高く、それに伴う鼻いびきは枕を変えても改善されません。
特に、アレルギー性鼻炎や慢性鼻炎、慢性副鼻腔炎などの病態では、鼻腔の鼻粘膜に炎症が生じ、それに伴う浮腫によって鼻粘膜が肥厚したり、鼻汁を伴うことで鼻いびきが生じるため、鼻腔拡張テープや抗炎症作用を持つ鼻スプレーを用いることで鼻腔を拡張でき、いびきの改善が期待できます。
一方で、鼻いびきの原因が重度の鼻茸や鼻中隔湾曲症の場合、物理的な鼻腔の閉塞が高度であり、鼻腔拡張テープやスプレーでは十分な拡張が得られず、思ったような効果が得られない可能性が高いです。
さらに、そもそもいびきの原因が鼻腔の狭窄でない場合、鼻腔拡張テープやスプレーの使用は意味がないため、使用する上では事前に原因を明らかにしておくことが重要です。
生活習慣を改善する
いびき対策として枕が効果がなかった場合、自身の生活習慣を見直すことでいびきを改善できる可能性があります。
先述したように、生活習慣はいびきの発症と密接に関わるため、枕を変えても効果がない場合は生活習慣の見直しが重要です。
いびきの最大の原因は肥満であるため、肥満を予防するためにも摂取カロリーや摂取する成分、摂取する時間帯には気を遣い、また1回30分以上の有酸素運動を週に3日以上、定期的に実施することもいびき対策の上では重要です。
また、過剰な飲酒や喫煙はもちろんのこと、睡眠薬の常用も舌根沈下を招く原因となるため、控える必要があります。
さらに、生活習慣以外にも就寝環境の見直しも重要です。
寝室の室温や湿度が寒冷・乾燥している場合、その空気が気道を乾燥させ、空気中の小さなチリやゴミを回収できなくなってしまうため、炎症が生じやすくなり、気道狭窄やいびきが起こりやすくなります。エアコンや加湿器などを用いて、気道に優しい適切な室温・湿度を保つことが重要です。
横向き寝を習慣にする
いびき対策として枕が効果がなかった場合、横向き寝を習慣にすることでいびきを改善できる可能性があります。
枕を最適化したとしても、顎が小さい・舌が大きい・肥満などの要因を認める場合、舌がその後方にある気道を圧迫しやすく、いびきをかきやすい状態です。
睡眠中は舌の筋肉が弛緩し、重力に伴って移動するため、特に仰向け寝の場合は舌が後方に移動しやすく、最もいびきをかきやすい状態です。
一方で、横向き寝であれば重力に伴って舌は左右いずれかの側方に移動するため、後方に位置する気道は守られやすくなり、いびきをかきにくくなります。
実際に、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020」でも睡眠中の体位を横向き寝に変える体位療法が治療法の1つとして推奨されており、特に軽症の患者やCPAP導入もしくは維持が困難な患者においては有効な治療法となりうるとしています。
市販の抱き枕などを用いることで横向きを維持しやすくなるため、ぜひ試してみると良いでしょう。
耳鼻科・睡眠クリニックで検査を受ける
いびき対策として枕が効果がなかった場合、耳鼻科・睡眠クリニックで検査を受けることも選択肢の1つです。
いびきの原因は多岐に渡り、自分のいびきのタイプやそれにあった対処法を実践しない限り、効果的な対策にはなり得ません。
そのため、耳鼻科・睡眠クリニックで専門家に原因を精査してもらい、その原因にあった適切な対処法を教えてもらうことが1番の近道なのです。
例えば、原因が睡眠時無呼吸症候群の場合、その診断には医療機関で「PSG検査(ポリソムノグラフィー)」と呼ばれる特殊な検査が必要となり、その重症度によって適切な治療法も変わってきます。
また、鼻中隔湾曲症や生まれながらの骨格、アデノイドや扁桃肥大などの耳鼻科疾患が問題となっていびきが生じている場合は、場合によっては手術しないといびきを改善できない可能性もあるため、やはり専門家による適切な診断と治療法の選択が求められます。
セルフケアで改善困難な場合は、早期に医療機関の受診を検討しましょう。
枕がいびき対策として効果がなかった方の体験談と改善事例
「いびきの原因が枕にあると思って枕を変えたけど、いびきが改善しない」このような方はいびきの原因が枕以外にあり、取るべき対策も枕以外にある可能性が高いです。
そこで、ここでは枕がいびき対策として効果がなかった方の体験談と、その後の改善事例を3つ紹介します。
10代男性:耳鼻科での治療で改善した事例
10代のAさんは日々部活動や勉強に励む高校生で、これといった病気や持病もない健康な青年です。以前から若干の鼻詰まりを認めていましたが、特に生活に支障はなく、鼻汁なども伴わないため放置していたそうですが、年々鼻詰まりが増悪傾向であったそうです。
それと同時にいびきをかくようになったようで、母親からは「ここ最近とても大きないびきをかくようになった」と指摘され、初めて自分のいびきが大きいことを自覚しました。
いびきを改善したいと考えたAさんは、両親に相談してネットで高評価の「いびき防止専用枕」を購入し、実際に使用したところ、いびきは特に改善を認めず、むしろ身体に合っていないせいか首や肩が痛くなってしまったそうです。
そこで、鼻詰まりがいびきの原因と考え耳鼻咽頭科に受診したところ、頭部CT検査で鼻中隔湾曲症を認め、それによって鼻いびきが生じていることが判明しました。
症状改善のためには手術が必要とのことで手術を受けた結果、術後1~2週間で鼻詰まりなどの症状は著明に改善し、それとともにいびきも改善されたそうです。いびきをかいていることに恥ずかしさを感じていたため、早期に改善できて安心できたそうです。
40代男性:生活習慣の見直しで改善した事例
40代男性のBさんは工事現場で働いており、仕事柄昼夜逆転してしまう日も少なくなく、仕事終わりであれば深夜でも飲酒や暴飲暴食を繰り返すような生活習慣を送っていました。
そのような生活習慣を繰り返していた結果、40代に入ってから急速に体重が増加し、それとともに夜間のいびきが悪化し、妻からは「いびきがうるさくて眠れない」と文句を言われるようになったそうです。
同時に熟睡感が薄れ、日中に我慢できないほどの眠気に襲われて事故を起こしそうになったため、自身や妻の健康を守るためにも改善しようと考えたそうです。
そこで、口コミで「高評価」と書かれていたいびき対策用枕を購入し使用し始めたところ、多少の改善は認められたものの、依然としていびきは大きく、思ったような効果は得られませんでした。
そこで、睡眠外来を受診し検査を受けたところ、軽度の睡眠時無呼吸症候群と診断され、改善のためには生活習慣の改善とダイエットが必要と言われました。
以降、食事内容や摂取時間に注意し、できる限り暴飲暴食や過剰な飲酒を控えたところ、減量に成功し、体重低下とともにいびきも改善したそうです。
妻から「夜ぐっすり眠れるようになった」と感謝され、自分自身も朝スッキリ起きられるようになり、仕事の集中力が上がったため、事故が起きる前に治療に取り組んで良かったと感じたそうです。
50代女性:CPAP療法で改善した事例
50代女性のCさんは専業主婦として日々家事に取り組んでいましたが、子供が家を出てからは家事の負担も減り、生活にメリハリがなくなったからか、体重も増加傾向でした。体重の増加とともに徐々にいびきが悪化し、夫からは「時折呼吸が止まっていてひどく心配になる」と言われてショックを受けたそうです。
そこで、いびき改善のためにネットでいびき防止専用枕を購入し、使用を試みたものの、枕の高さがフィットせず、首や肩が痛くなったり、寝返りのたびに違和感があり、熟睡できなくなったそうです。
やはり専門家のもとで治療をしっかり受けたいと考えたCさんは、近隣の病院の耳鼻咽喉科を受診し、検査を受けたところ、重度の睡眠時無呼吸症候群と診断され、CPAP療法を行う運びとなりました。
CPAP療法を始めた初期はマスクのフィットに違和感があったものの、比較的早期に慣れ、以降はいびきの改善とともに、熟睡感を取り戻すことができたそうです。
いびきを放置するリスク
いびきは発熱などの症状と異なり、つい軽視されがちで、人によっては長期間放置してしまう方も少なくありません。
しかし、実はいびきを放置すると短期的・長期的にさまざまな健康被害が生じることが知られており、早期対策が必要である症状のため、注意が必要です。
ここでは、いびきを放置するリスクを3つ紹介します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)による健康リスク
いびきを放置した場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が進行することによるさまざまな健康リスクがあります。
睡眠時無呼吸症候群とはその名の通り、睡眠中に気道が狭窄してしまい、低呼吸(睡眠中に10秒以上、呼吸が著しく浅くなり、換気量が通常の半分以下になる、または血液中の酸素飽和度が低下する状態)や無呼吸(10秒以上の呼吸停止)を認める病気です。
睡眠時無呼吸症候群によって身体が低酸素状態に陥り、その状態が長期化すると、身体にとって大きなストレスとなり、交感神経が持続的に活性化します。
その結果、血圧や脈拍・血糖値の上昇、心不全や心房細動などの心疾患リスク上昇、脳血管障害の発症リスク上昇など、命に関わるような病気の発症リスクが増大することが知られています。
そのため、いびきが遷延している方は睡眠時無呼吸症候群の可能性を疑い、専門の医療機関で早期発見・早期治療に努めるべきです。
日中の眠気や集中力低下による事故リスク
いびきを放置した場合、日中の眠気や集中力低下による事故リスクが上がるため、注意が必要です。
いびき=気道が狭窄している状態のため、睡眠中に取り込める酸素の量が低下し、脳や身体は十分量の酸素を取り込むことができなくなります。
また、気道狭窄によって吸気時には胸腔に過剰な陰圧がかかってしまうため、その陰圧が脳幹の覚醒中枢を刺激し、睡眠中の中途覚醒の頻度も増加します。
その結果、睡眠時間を確保しているにも関わらず、睡眠の質が著しく低下し、熟睡感の喪失や起床時に倦怠感、頭痛、日中の我慢しきれないほどの眠気、集中力の低下など、さまざまな症状をきたす可能性があり、注意が必要です。
特に、日中の我慢しきれないほどの眠気は車の運転や高所での作業において大変危険な症状であり、交通事故や高所からの転倒・転落のリスクが増大することが知られています。
実際に、睡眠時無呼吸症候群の発症者の交通事故発生率は睡眠時無呼吸症候群のない人の約7倍、一般ドライバーの約2.5倍といわれ、重症度に比例して事故率も高くなることが知られているため、やはり早期改善が肝要です。
家族やパートナーへの負担
いびきを放置した場合、家族やパートナーへの負担も増加してしまうため、注意が必要です。
いびきは程度にもよりますが、一般的に音の大きさは50〜60dB(デシベル)と言われており、より大きい人では70dBにも達すると言われています。
50dBの騒音は繁華街の騒音やエアコンの室外機と同等の騒音であり、70dBにも達すると、その音の大きさはご近所の騒音トラブルになるレベルで、大型の音響機器と同程度の音量です。
50dB以上の騒音は共に暮らすパートナーの健康に悪影響を与えることが知られており、この状態が長期的に続くと睡眠障害を引き起こし、高血圧や心臓病、脳卒中のリスクを高めることが報告されています。
以上のことより、大きな音のいびきはいびきをかく本人の健康のみならず、共に暮らすパートナーの健康や睡眠も脅かすことが知られているため、やはり早期に原因を調べ、適切な対応を取ることが重要です。
【まとめ】枕がいびきに効果なしと感じたら、医療機関への相談も検討しよう
この記事では、枕がいびきに効果なしと言われる原因や、効果が得られない場合の他の対処法について詳しく解説しました。
枕を身体にあった適切な高さや硬さに変えることで、気道の狭窄を予防する事ができ、いびきを改善できる可能性があります。
一方で、いびきの原因は肥満や生活習慣の乱れ、骨格的な問題や耳鼻科疾患の発症など多岐に渡り、必ずしも枕を変えたからといっていびきが改善する保証はありません。
改善しない場合は、この記事で紹介したように生活習慣を見直したり、医療機関に受診して詳しい検査を受ける必要があります。対処が遅れれば自身や共に暮らす家族に健康被害をもたらすため、放置せずに早期から対策する事が重要です。
下記の記事では自身のいびきの危険度を簡易的にセルフチェックできるため、これを機にぜひご一読ください。
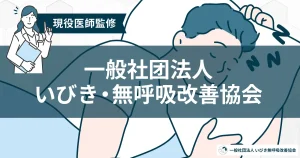
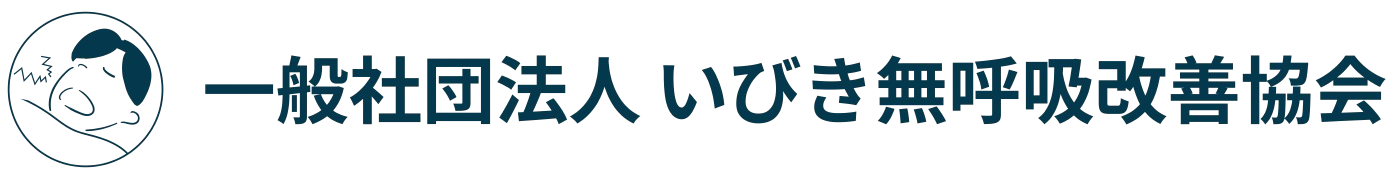
コメント