- 横向きでもいびきが止まらないのはなんで?
- 横向きでいびきが止まらない場合はどうすればいい?
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
一般的に、横向きになると仰向けよりも舌が後方の気道を圧迫しにくくなるため、いびきをかきにくくなるはずですが、それでもいびきが止まらない場合、何らかの病気や解剖学的問題を抱えている可能性があります。
そこでこの記事では、横向きでもいびきが止まらない原因や可能性のある病気、対策などについて詳しく解説します。この記事を読むことで、横向きでも止まらないいびきに適切に対処できるようになり、快眠を取り戻すことができるようになるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
横向きでもいびきが止まらない理由とは?考えられる5つの原因
いびきは睡眠中、空気が気道を通過する際に生じる粘膜の振動音であり、気道が狭くなればなるほど、いびきをかきやすくなります。そのため、仰向けで寝ると弛緩した舌が重力に伴って舌後方に移動するため、気道を圧迫しやすく、いびきをかきやすくなります。
一方で、横向きで寝る場合は舌が側方にずれ込むため、本来であれば仰向けよりもいびきをかきにくいはずです。
にも関わらず、横向きでもいびきが止まらない場合、下記のような理由が考えられます。
そもそも「横向き=改善」ではないケースがある
横向きになれば必ずいびきが止まると思っている方もいるかもしれませんが、そもそも「横向き=改善」ではないケースがあるため、注意が必要です。
睡眠中、舌は弛緩することで重力の影響を受けて位置が変わり、横向きであれば側方に、仰向けであれば後方に位置が移動します。そのため、横向きと仰向けの体位の違いがいびきに与える影響は、あくまで舌の位置のみであり、舌の位置以外の要因で生じているいびきには効果がありません。
例えば、鼻づまりによって鼻呼吸が障害されている場合や、体位に関係なく気道を狭窄させる原因疾患を認める場合、舌の位置に関わらずいびきが生じています。そのため、これらの原因によって生じているいびきは横向きになったところで改善しない、もしくは改善が十分でない可能性があるため、注意が必要です。
舌が大きい・喉の構造による気道の閉塞
横向きでもいびきが止まらない場合、舌が大きい・喉の構造による気道の閉塞の可能性があります。
そもそも舌が大きい場合や、喉が構造的に狭い場合、舌の位置に関わらず気道が狭い状態であるため、たとえ横向きになったところでいびきが改善しない可能性があるため、注意が必要です。
舌が大きい原因としてはBeckwith-Wiedemann症候群などの遺伝性疾患による生まれつき、リンパ管腫や血管腫などの腫瘍、浮腫、肥満、甲状腺機能低下症などが挙げられます。
また、特に日本人は欧米人と比較して顎が小さい傾向にあるため、咽頭部の構造が狭く、気道が狭くなりやすいです。さらに、近年では美容整形手術で顎を小さくする方も少なくなく、その結果、医原性に気道が狭窄し、いびきをかきやすくなることもあります。
これらの要因の場合、舌の位置に関係なく常にいびきをかきやすい状態であるため、横向きでも改善しない可能性があり、注意が必要です。
鼻詰まり・アレルギー性鼻炎による口呼吸
横向きでもいびきが止まらない場合、鼻詰まり・アレルギー性鼻炎による口呼吸が原因となっている可能性が考えられます。
ヒトは本来、睡眠中は鼻呼吸を行い、流入する空気に対し鼻の粘膜の鼻汁などによって加湿・加温、もしくは空気中の小さなゴミの除去をおこなっています。そのため、鼻呼吸の場合は綺麗で湿潤した気道に優しい空気を取り込めるのです。
しかし、鼻詰まりやアレルギー性鼻炎などによって鼻粘膜が肥厚すると、鼻呼吸が困難となり、口呼吸の割合が増加しますが、これこそいびきの原因となるため、注意が必要です。
口呼吸の場合、口の開閉によって下顎が後方に移動するため、吸気時になると気道が狭くなりやすく、いびきをかきやすくなります。
さらに、口呼吸では流入する空気に対して十分な加湿・加温が行えないため、乾燥・寒冷した空気が気道に流入し、炎症を引き起こしやすくなり、浮腫が生じることでさらにいびきをかきやすくなるため、注意が必要です。
舌などの喉の周囲の筋肉の低下(加齢・運動不足)
横向きでもいびきが止まらない場合、加齢や運動不足によって舌などの喉の周囲の筋肉が低下している可能性があります。
咽頭部や喉頭部の気道は、さまざまな筋肉や骨・軟骨などで構成されており、周囲を脂肪組織に覆われています。
加齢や運動不足などによって気道を形成する筋力が低下してしまうと、周囲の脂肪組織の重みから気道内腔を守ることができず、圧排されてしまうことで気道が狭窄するため、いびきの原因となるのです。
また喉の筋肉だけでなく、舌も筋肉の豊富な組織であり、加齢によって筋力低下することで舌根沈下しやすくなるため、いびきの原因です。
日頃から、舌の出し入れや口周りの運動を行うことで喉の筋力低下を予防できるため、意識的に行っておくと良いでしょう。
痩せ型でも起こる睡眠時無呼吸症候群(SAS)
横向きでもいびきが止まらない場合、痩せ型でも起こる睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症している可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群とは、その名の通り睡眠中に低呼吸(換気が30%以上低下し、10秒以上持続する状態、もしくは動脈血酸素飽和度がベースラインから3%以上低下した状態、あるいは覚醒反応を伴う状態)や無呼吸(10秒以上の呼吸停止)が増加する病気です。
一般的に、睡眠時無呼吸症候群の原因は肥満であり、肥満度に比例して睡眠時無呼吸症候群の程度も悪化し、いびきを伴います。
一方で、日本人の場合は顎が小さく、骨格的に気道が狭窄しやすいなどの理由から、痩せ型でも睡眠時無呼吸症候群を認める割合が多いため、注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020によれば、特に重症度が低く、若年、かつBMIが低い患者では、睡眠中に側臥位から仰臥位に変えることで低呼吸や無呼吸の割合が2倍になるため、逆に言えば横向けになることでいびきが改善する可能性も高いです。
一方で、中高年や肥満を伴う睡眠時無呼吸症候群患者の場合、体位に関わらず低呼吸や無呼吸を認めやすく、横向きになってもいびきをかきやすい可能性があります。
横向きでもいびきが止まらないときのセルフ対策
程度の重いいびきが長期的に継続する場合、睡眠中に脳や身体は十分な酸素を受け取ることができず、睡眠の質や身体の回復度が低下する恐れがあります。
そのため、早期からの対策が重要であり、今日からでも実践可能なセルフ対策は主に下記の5つです。
それぞれについて詳しく解説します。
横向き用枕・抱き枕で「より良い横向き姿勢」にする
横向きでもいびきが止まらない場合、横向き姿勢が身体や気道に負担をかけていないかチェックしましょう。
普段から使用している仰向け寝用の寝具を使用して横向き寝をする場合、枕の高さが合わなかったり、寝心地が悪くて無意識に横向き寝を維持できない可能性があるため、効果的にいびきを改善させることができません。
そこで、横向き寝に適した寝具を使用することで姿勢を維持しやすくなり、いびきを効果的に改善できます。特に枕の高さは寝心地において重要であり、横向きの場合は頭から背中にかけてまっすぐな一直線になるような高さの枕を選ぶべきです。肩幅や頭のサイズによっても適切な高さは異なりますが、一般的に約4〜10cm程度の高さが理想的であると言われています。
横向きの頭の高さに適した横向き用枕のほかにも、横向き姿勢を維持しやすくなる抱き枕、腰の沈み込まない反発感のあるマットレスなど、より良い横向き姿勢を維持できるための寝具を揃えると良いでしょう。
口呼吸防止にマウステープや鼻呼吸サポーター
横向きでもいびきが止まらない場合、口呼吸防止や鼻呼吸を促進できる市販グッズを試してみるのも1つの手段です。
先述したように口呼吸は下顎が後方に移動し、また気道に炎症を引き起こすリスクも増大するため、鼻呼吸と比較して気道狭窄のリスクが高く、いびきをかきやすくなります。そのため、口が自然と開かないようにするマウステープを使用することで口呼吸を防止でき、いびきを解消できる可能性があります。
しかし、口呼吸が増加している原因がアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎・鼻茸などの耳鼻科疾患に伴う鼻づまりの場合、マウステープによって口も塞いでしまうと窒息してしまうため、注意が必要です。
鼻づまりを伴う場合は、むしろ鼻腔拡張テープなどの鼻づまり解消グッズの使用によって自然と口呼吸も減少するため、口呼吸が増加している原因に応じて適切なグッズを使い分けると良いでしょう。
いびき軽減のための舌・喉トレーニング
横向きでもいびきが止まらない場合、いびき軽減のための舌・喉トレーニングを行うことも対策の1つです。舌や喉の筋肉をトレーニングすることで、気道の形状を保ちやすくなり、周囲からの圧迫を受けにくくなるため、いびきを改善できる可能性が高まります。
舌のトレーニングとしては下記のような運動が効果的です。
- 舌を口の中で回す
- 舌を口の外に出して上下左右に動かす
- 舌で歯の根本をなぞる
次に、喉のトレーニングとしては下記のような運動が効果的です。
- パタカラ体操:口を大きく開け閉めしたり、舌を前後に動かすことで、口周りの筋肉を鍛える
- アイウベ体操:「あー」「いー」「うー」「べー」と口を大きく動かすことで、口輪筋や舌の筋肉を鍛える
特に加齢や運動不足の方は、知らず知らずのうちに徐々に咽頭や喉頭、舌の筋力が低下していき、いびきをかきやすくなっていくため、上記で紹介したトレーニングを定期的に実践すると良いでしょう。
アレルギー・鼻炎の治療で口呼吸を改善
横向きでもいびきが止まらない場合、アレルギー・鼻炎などの病気を治療し、口呼吸を改善させることも1つの手段です。
先述したように、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、鼻茸、鼻中隔湾曲症などの耳鼻科疾患を発症している場合、ヒトが本体睡眠中に行う鼻呼吸が困難となり、口呼吸が増加します。口呼吸の増加に伴い、吸気時に下顎が後方に移動することで気道が狭くなるため、いびきをかきやすくなります。
そのため、これらの耳鼻科疾患を治療することで鼻の通気性が改善し、口呼吸の割合が減少することでいびきを改善できる可能性があるのです。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎が原因の場合は、主に鼻粘膜の浮腫が鼻づまりの原因であるため、点鼻薬による浮腫の改善によっていびきも改善できる可能性が高いです。
一方で、鼻茸(鼻腔内のポリープ)や鼻中隔湾曲症が原因の場合、解剖学的に鼻腔内が狭窄しているため、症状が進行してしまうと手術などによって切除しないと通気性の改善が見込めない場合もあります。
就寝前の習慣(アルコール・スマホなど)の見直し
横向きでもいびきが止まらない場合、就寝前の生活習慣の見直しも必要です。
何気なくルーティン化している生活習慣も、実は気道の構造に変化を及ぼすことが知られており、結果としていびきの原因となります。
例えば、就寝直前まで飲酒や喫煙を行う場合、アルコールの血管拡張作用やタバコに含まれる有害物質による炎症によって気道に浮腫が生じ、いびきをかきやすくなります。
また、アルコールには筋弛緩作用が含まれており、舌が弛緩して舌根沈下を起こしやすくなるため、注意が必要です。さらに、長時間のスマホやPCの操作は、どうしても首が前方に俯いて操作することになるため、頸部が前方に倒れる、いわゆるストレートネックになってしまいます。
ストレートネックになると、寝た時により頸部が屈曲しやすくなるため、気道も狭窄しやすくなっていびきの原因となります。上記のような生活習慣は今日からでも簡単に是正できるため、ぜひ実践してみると良いでしょう。
横向きでもいびきが止まらなかった人の体験談と改善事例
横向きでもいびきが止まらない場合、十分な質の睡眠を確保することができず、学業や仕事など、日常生活のさまざまなシーンに支障をきたします。
また、上記で記したように原因によって取るべき対策も異なるため、自身の症状・原因にあった方法で改善を目指すことが重要です。
ここでは、実際に横向きでもいびきが止まらなかった人の症状や対策などを踏まえて、体験談を3つ紹介します。
20代女性:レーザー治療で改善した事例
Aさんは特にこれまで大きな病気もなく、健康的な痩せ型の女性で、一般企業で事務職として働いている20代女性です。ここ数ヶ月、急速にいびきをかくようになり、家族からは「すごい音を出しながら寝ているけど大丈夫?」と心配されるほどでした。
横向きで寝ると改善すると聞き、抱き枕を使って横向き寝に挑戦したものの、いびきは一向に改善せず、むしろ時間の経過とともに悪化していったそうです。このいびきのせいで彼氏との同棲や宿泊も拒否せざるを得ないような状況でした。
市販のいびき対策グッズで鼻腔拡張テープなど使用しても症状に改善が見られなかったため、近隣の耳鼻科を受診したところ、鼻腔の奥の粘膜が浮腫状に腫脹しており、それがいびきの原因の可能性が高いと指摘されたそうです。
そこで、いびき改善のためにレーザー治療を行い、肥厚した粘膜を焼却したところ、術後数日は痛みや出血、鼻汁を認めたものの、それらの症状の改善とともに、術後1週間頃からいびきも著明に改善を認めたそうです。
改善後は熟睡感も増加し、また彼氏や友人との旅行にも気兼ねなく参加できるようになったため、Aさんからは「同じようなお悩みを抱える読者の方には悩みを抱え込まず、まずは医療機関を受診してほしい!」とのことです。
40代男性:マウスピースで改善した事例
40代男性のBさんは自営業を営んでおり、普段から多忙な日々を過ごしてたため、夜遅くに食事や飲酒をする機会も多い生活でした。若い頃から奥さんからいびきを指摘されており、年々いびきがひどくなっていると言われていたそうですが、仕事が多忙で放置していたそうです。
しかし、奥さんが不眠になるほどのいびきをかくようになり、流石に改善しようと調べたところ、横向きで寝ると改善すると知り、実践したそうですがほとんど改善を認めませんでした。同時に、日中に激しい眠気を感じたり、朝の起床時に倦怠感を自覚するようになったため、仕事にも支障がで始めたそうです。
就寝直前までの飲酒がよくないことを知り、節酒するも著明な改善は見られなかったため、セルフケアは諦めて近隣の医療機関に受診したところ、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと診断されました。そこで、睡眠時無呼吸症候群診断のためにPSG検査を実施したそうです。
PSG検査は睡眠中の呼吸状態をモニタリングする検査で、その結果、中等度の睡眠時無呼吸症候群と診断されました。
下顎を前方に固定するため、同じ病院の歯科でマウスピースを作製したところ、装着からすぐにいびきの改善を認めました。
一緒に寝ていた奥さんもいびきの改善によって安眠できるようになり、Bさんは奥さんのためにももっと早く治療すればよかったと感じたそうです。
そして、これを機に「いびきでお悩みの方は、放置すれば仕事や学業に支障が出るだけでなく、大切な家族の健康も害してしまうため、放置せずに早期から対策してほしい」とBさんは強く実感したそうです。
60代男性:生活習慣の見直しで改善した事例
60代男性のCさんは年齢の割に痩せ型で、運送業に従事しており、勤務時間が不定期であることから、若い時から暴飲暴食や深夜までの飲酒・喫煙を繰り返しており、生活習慣が乱れがちでした。以前から家族にいびきを指摘されており、子供からもうるさいと文句を言われる機会が増えたため、横向きに寝ることでいびき改善を目指しましたが、改善は認められませんでした。
また、とくにいびきがひどい日の翌日は起床後から倦怠感が強く、日中は激しい眠気によって運転中事故を起こしそうになったため、命の危険を実感して病院を受診したそうです。
そこで、医師からは生活習慣、特に過剰な飲酒や喫煙がいびきに強く関係している可能性を指摘され、是正するように指示されたそうです。急には止まられなかったものの、喫煙本数や飲酒量を減らすと、録音していたいびきの大きさが顕著に小さくなっていったため、効果を実感して継続したところ、病院受診から2週間経過した頃には子供からも「いびきがかなり減った」と褒められるようになったそうです。
日中の眠気も改善し、仕事にも集中できるようになったため、Cさんは「もし同じようにいびきに悩む方がいれば、飲酒や喫煙の量を見直してみてほしい」と実感したそうです。
横向きでもいびきが止まらない場合は病気の可能性はある?
「横向きでもいびきが止まらない場合、何かの病気なの?」「いびきを放置すると危険なの?」このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
横向きでもいびきが止まらない場合、特に注意すべき病気は睡眠時無呼吸症候群であり、さまざまなリスクを含む病気です。ここでは、睡眠時無呼吸症候群のリスクや症状など、下記の3点について詳しく解説します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の特徴とリスク
横向きでもいびきが止まらない場合、最も考えられる病気は睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。睡眠時無呼吸症候群の特徴として下記のような症状が挙げられます。
- 睡眠中の大きないびきや、突然「がっ」と大きな音の出るいびき
- 睡眠が浅く、中途覚醒が増加する
- 夜間、呼吸が止まる時間がある
このような症状を認める場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いです。
睡眠時無呼吸症候群は睡眠の質の低下によってさまざまな症状をきたす疾患ですが、特に最もリスクの高い点は命に関わるような病気の発症率を上昇させてしまう点です。睡眠時無呼吸症候群を発症すると、睡眠中に取り込める酸素の量が低下するため、身体は持続的な低酸素状態に陥ってしまい、そのストレスによって持続的に交感神経の活性化が引き起こります。
その状態が長期にわたると、交感神経の刺激によって高血圧や糖尿病、脳血管障害、心不全、心房細動などの発症リスクが増大してしまうことが知られています。特に、脳血管障害や心疾患は場合によって死に至る可能性もある病気のため、睡眠時無呼吸症候群に対しては早期からの適切な対応が必要不可欠です。
日中の眠気・起床時の頭痛がある人は要注意
横向きでもいびきが止まらない方で、日中の眠気や起床時の頭痛・倦怠感がある方は、特に睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いため、注意が必要です。
「いびき=気持ちよく深い睡眠」と思われる方もいるかもしれませんが、実は睡眠時無呼吸症候群では睡眠の質が低下し、中途覚醒も増加するため、むしろ浅い睡眠が増えている状態です。
そのため、起床直後から倦怠感や頭痛を自覚し、日中に我慢できないほどの眠気に襲われるケースや著しく集中力の低下するケースも少なくありません。
実際に睡眠時無呼吸症候群患者では居眠り運転による事故の報告が絶えず、特に一人運転中、高速道路や郊外などの直線道路、渋滞中の低速走行などでは事故が起きやすいと報告されています。また、アメリカでの調査結果では、睡眠時無呼吸症候群患者の事故率は健常者の約7倍と報告されており、十分注意が必要です。(参考文献:国土交通省)
受診すべき診療科と検査内容
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、まずは耳鼻咽頭科に受診しましょう。
睡眠時無呼吸症候群の原因はこの記事でも紹介したように多岐に渡りますが、多くの場合、鼻腔や咽頭・喉頭に存在する何らかの原因によって気道が狭窄しているため、その領域の専門家である耳鼻咽頭科であれば多くの場合、原因解明や適切な治療の提案が可能です。
一方で、原因が下顎の位置異常などの場合は耳鼻咽頭科よりも歯科や口腔外科が専門であるため、これらの診療科で睡眠時無呼吸症候群に対応しているクリニック・病院であれば、こちらを受診するのも選択肢の1つです。
実際に睡眠時無呼吸症候群を診断するためには、一晩入院して「PSG検査」を受ける必要があります。PSG検査は、脳波・眼球運動・心電図・筋電図・呼吸曲線・いびき・動脈血酸素飽和度などの生体活動を、一晩にわたって測定する検査です。
これによって測定されたAHI(睡眠1時間あたりの無呼吸・低呼吸の合計回数)によって睡眠時無呼吸症候群の診断や重症度分類がなされ、その重症度に応じて治療法も変わってきます。そのため、睡眠時無呼吸症候群を強く疑う場合は、PSG検査も一緒に実施できる耳鼻咽頭科に受診するのが最適です。
【まとめ】横向きでもいびきが止まらないときの原因・対処法
この記事では横向きでもいびきが止まらないときの原因・対処法について詳しく解説しました。
横向きでもいびきが止まらない場合は耳鼻科疾患の発症や生活習慣に問題がある可能性が高く、早期から原因に合った適切な治療を行うことが重要です。
対処が遅れれば命に関わるような病気の発症リスクも増大するため、横向きでもいびきが止まらないという方は、まずは自身のいびきの危険度を自覚することが重要です。下記の記事では、自身のいびきの危険度を簡単にセルフチェックできるため、ぜひご一読ください。
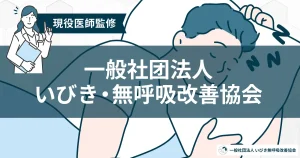
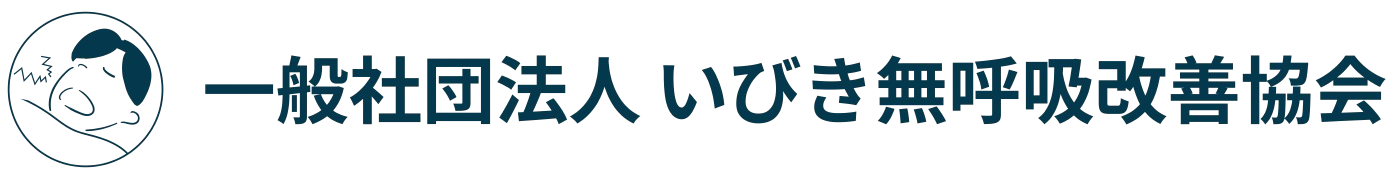
コメント