- お酒を飲む時にいびきをかきやすくなるのはなぜ?
- お酒によるいびきのリスクは?
このような不安や疑問を抱く方も少なくないでしょう。
お酒に含まれるアルコールの薬理作用によって気道の狭窄を招き、いびき症状が出やすくなったり、睡眠の質が大きく低下することが知られています。放置すればさまざまな健康被害を招くため、飲酒によるいびきが継続する場合は何らかの対策が必要です。
そこで、この記事ではお酒を飲むといびきがうるさい原因や対策、リスク、実際の体験談について詳しく解説します。
この記事を読むことで飲酒に伴ういびきの改善が得られ、より良い睡眠を目指すことができるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
お酒を飲むといびきがうるさいのはなぜ?
自身では飲酒後のいびきを自覚しにくいですが、家族やパートナーなどと同居している場合、お酒を飲んだ夜にいびきがうるさくなったり、普段いびきをかかない人でもいびきをかくようになることがあります。
お酒を飲むといびきがうるさくなる理由は主に下記の3つです。
それぞれについて詳しく解説します。
喉や舌の筋肉がゆるんで気道が狭くなる
お酒を飲むといびきがうるさくなる原因は、喉や舌の筋肉がゆるんで気道が狭くなるためです。お酒に含まれるアルコールには筋弛緩作用があり、全身の筋肉が普段よりも弛緩しやすい状態にあるため、喉や舌の筋肉がゆるんでしまい、気道が狭窄しやすくなります。
例えば、舌は喉の奥の方から口の外の方向に向かって伸びていますが、睡眠中は舌の筋肉が弛緩することで喉の奥の方向に沈下してしまい、さらに後方に位置する気道が狭窄しやすくなってしまいます。
これに加え、アルコールを飲んでいると筋弛緩作用が強まるため、より舌根沈下が起こりやすくなり、気道狭窄も悪化するわけです。
いびきは、空気が狭窄した気道を通過する際に生じる粘膜の振動音であるため、アルコールによって気道が狭窄することでいびき症状が悪化します。
また、舌以外にも気道を形成する咽頭部の筋肉もアルコールによって弛緩するため、周囲の脂肪組織からの圧迫も受けやすくなり、やはり気道狭窄の原因となります。
睡眠が浅くなって呼吸が乱れる
お酒を飲むと睡眠が浅くなって呼吸が乱れる可能性があり、これもいびきがうるさくなる原因の1つです。緊張や不安によって夜に寝れない人の中には、お酒を飲むことで入眠しようとする方もいると思いますが、それはかえって逆効果です。
アルコールには確かに一時的な鎮静作用があるため、飲酒によって眠気が惹起され、入眠しやすくなる効果がありますが、一方で、アルコールの代謝産物であるアセトアルデヒドには中枢神経系の覚醒作用があり、入眠後にアルコールが代謝されるにつれて徐々にアセトアルデヒドの血中濃度が増加し、その覚醒作用によって途中で覚醒する可能性が高まります。
さらに、飲酒する際に過剰に水分や塩分を摂取すると、舌や気道を形成する組織が浮腫み、さらに気道が狭窄しやすくなるため、やはりいびきの悪化する原因です。
気道狭窄によってうまく空気を吸い込めなくなると、呼吸が乱れてしまい、途中で「ガッ」という音を立てて中途覚醒してしまうため、注意が必要です。
太り気味だとさらに悪化する
お酒を飲むといびきをかきやすくなる原因の1つに、飲酒による肥満の可能性が挙げられます。お酒の中のアルコールはカロリーが高く、また飲むお酒の種類によってはサワーやビールなど、糖質が豊富でより高カロリーなお酒も含まれます。
さらに、お酒には胃の血流促進による消化促進、血糖値の低下、満腹中枢の抑制、空腹感の増強など、さまざまな薬理作用を持つため、結果的に食事量や摂取カロリーが増加し、肥満に陥りやすくなります。
肥満になると首周りの脂肪が増加し、その脂肪によって気道が外側から圧迫されてしまうため、気道狭窄に伴ういびきの原因となります。
特に、肥満度を表すBMI【体重(kg)➗身長(m)➗身長(m)】が25kg/㎡以上の肥満の方はいびきや睡眠時無呼吸症候群の発症リスクが高く、注意が必要です。
アルコールによる肥満と筋弛緩作用の両方の影響でいびきが悪化しやすくなるため、体重が増加傾向の方は特に飲酒量や摂取カロリーには注意しましょう。
お酒を飲む時のいびき対策5選
お酒を飲む時は上記のような理由からいびきをかきやすく、放置すれば睡眠の質の低下やさまざまな健康被害を引き起こす可能性もあるため、早期から対策することが重要です。
ここでは、お酒を飲む時のいびき対策を5つ紹介します。
それぞれについて詳しく解説します。
寝る直前にお酒を飲まない
お酒を飲む時のいびき対策として、寝る直前にお酒を飲まないことが重要です。お酒を就寝直前まで飲むことで、アルコールによる筋弛緩作用が睡眠中に強く表面化してしまい、舌根沈下を引き起こしやすくなります。
また、就寝直前まで飲酒と共に食事をすることで過剰な塩分や水分摂取となり、気道に浮腫が生じやすく、舌根沈下しなくても気道の浮腫によっていびきをかきやすくなるため、注意が必要です。
アルコールの代謝にかかる時間は、飲酒量やアルコール代謝能の個人差にもよりますが、概ね3-4時間はかかると言われています。
そのため、飲酒から3-4時間は筋弛緩作用が出やすいと考えられるため、寝る直前までの飲酒は控え、就寝の3-4時間前までには飲み終えておくと良いでしょう。
また、飲酒の際に塩辛いおつまみや塩分の高い食事をたくさん摂取してしまうと、アルコールによる筋弛緩作用が解消されても、浮腫による物理的な閉塞でいびきが止まらなくなるため、飲酒時間と共に、摂取する食事内容にも注意しましょう。
水を一緒に飲む
お酒を飲む時のいびき対策として、水を一緒に飲むことも重要です。これを聞くと、「飲酒中・飲酒後に水を飲むことで、体内に吸収したアルコールが水によって中和され、血液中のアルコール濃度が希釈される」と思われる方も少なくないと思いますが、これは科学的に否定されています。
大分大学医学部と三和酒類株式会社が共同で行なった実験において、お酒の強い人を対象にお酒と水を定量飲んでもらい、呼気中のエタノールとアセトアルデヒドの濃度を測定したところ、水を飲んでも呼気中の濃度は思ったような低下を認めなかったのです。
一方で、お酒と水を一緒に飲んだ群は、水を飲まなかった群と比較し、摂取後の集中力が著しく低下しており、「お腹がパンパンで気分が悪い」との訴えが多かったそうです。以上のことから、水を飲む効果はアルコール濃度の希釈ではなく、胃が充満することでアルコール摂取量そのものが低下することが主であるということがわかります。
そのため、もし水を飲むなら特に飲酒中に一緒に水を飲むほうが、よりアルコール摂取量を下げられるため、おすすめです。
横向きで寝る
お酒を飲む時のいびき対策として、仰向けではなく横向きで寝ることもおすすめです。飲酒によって気道が浮腫んだり、アルコールによる筋弛緩作用によって舌が後方の気道を圧排するため、いびきが生じます。
特に仰向けの場合、弛緩した舌は重力に従って後方に落ち込んでしまうため、飲酒後にいびきをかきやすくなる体位と言えます。一方で横向きで寝る場合はアルコールによって舌の筋肉が弛緩したとしても、重力の影響で舌は後方ではなく側方に移動するため、舌後方に位置する気道への影響は少なく、いびきの改善が目指せます。
実際に、睡眠時無呼吸症候群の診療ガイドラインでは比較的軽症の患者やCPAP装着困難な患者などに対しては体位療法を治療の選択肢の1つとしています。
一方で、その推奨度はD(とても弱い:効果の推定値がほとんど確信できない)に分類されており、人によっては効果が得られにくい可能性があることには留意すべきです。
いびき対策グッズを使う
お酒を飲む時のいびき対策として、いびき対策グッズの使用もおすすめです。市販で購入できるいびき対策グッズは、それぞれさまざまなアプローチで気道を拡張・開通させ、いびきの改善に寄与します。
例えば、飲酒によって微粘膜の毛細血管は拡張し、血管から血管外に水分が漏出することで鼻粘膜に浮腫が生じ、いびきの原因となります。そのため、市販の鼻腔拡張テープやノーズクリップなどの使用によって物理的に鼻腔を拡張させることで、いびきの改善が目指せるのです。
また、睡眠中に口呼吸を行ってしまう方の場合、吸気時に下顎が後下方に下がり、より舌が後方に落ち込みやすくなるため、いびきをかきやすくなります。そこで、市販の口閉じテープを使用することで口呼吸を制限でき、飲酒に伴ういびきの改善を予防することができます。
これらのグッズは市販で容易に購入できるため、ぜひ一度試してみると良いでしょう。
普段から適度な運動をする
お酒を飲む時のいびき対策として、普段から適度な運動を行うこともおすすめです。普段から適度な運動を行うことでストレスが発散・解消でき、普段ストレス解消のために飲酒してしまうような方の飲酒量の軽減効果が期待できるためです。
また、適度な運動を行うことによってダイエット効果を得ることができ、気道周囲の脂肪や舌の肥大を軽減できるため、気道狭窄を解消することができます。
ここで重要なのは、あくまで適度な負荷の運動に留めることです。過度な負荷の運動は逆に心身にとってストレスとなってしまい、飲酒量が増加する原因となるため、注意が必要です。
具体的には、成人の場合は息が弾み汗をかく程度(3METs以上)の運動を週60分以上、筋力トレーニングを週に2〜3日程度行うことが推奨されています。(参考文献:健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023)
ランニングやウォーキング、水泳、ゴルフ。ピラティスなど、自身の好みに合った運動を見つけて、継続的に行うことがいびき予防のためにも重要です。
放置すると危険?お酒といびきの健康リスク
結論から言えば、お酒を飲んでいびきをかく状態を放置するのは大変危険であり、早期から対策することが重要です。
過度な飲酒やそれに伴ういびきを放置すると、中途覚醒の増加や睡眠の質の低下はもちろんのこと、長期的に見てさまざまな健康被害が生じることが知られています。
お酒といびきの健康リスクは主に下記の3つです。
それぞれについて詳しく解説します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスク
お酒を飲むことによって生じるいびきを放置してしまうと、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクが増大するため、注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、その名の通り、何らかの原因で気道が狭窄し、睡眠中の呼吸が低呼吸や無呼吸に陥ってしまう病気です。お酒を飲むことで舌根沈下や気道の浮腫が生じやすくなり、その結果、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすくなります。
睡眠時無呼吸症候群を発症すれば、睡眠中に十分量の酸素を脳に取り込めなくなってしまうため、睡眠時間を確保しても脳や身体は十分な休息を得ることができなくなります。
その結果、起床時の頭痛や倦怠感、熟睡感の喪失、さらには日中の我慢できないほどの眠気や集中力の低下など、さまざまな症状が生じ、これによって交通事故や転倒・転落の可能性が増大することも知られており、注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群の原因が飲酒である場合、アルコールに含まれる中枢神経の覚醒作用によって睡眠の質がさらに低下するため、より危険な状態といえます。
高血圧や心臓病のリスク
お酒を飲むことによって生じるいびきを放置してしまうと、高血圧や心臓病のリスクも増大するため、注意が必要です。先述したように、お酒を飲むことによって生じるいびきが続くと、身体は十分な酸素を取り込めなくなるため、持続的な低酸素状態に陥ります。
低酸素状態は体にとってストレスとなり、そのストレスによって交感神経系が持続活性化することで、心拍や血管収縮、ホルモン分泌など、さまざまな生理機能に影響を与え、高血圧や高血糖、心不全や心房細動などの心血管系リスク、脳梗塞や脳出血などの脳卒中リスクが増大することが知られています。
また、その背景に飲酒がある場合、アルコールの代謝産物であるアセトアルデヒドが交感神経を活性化させてしまうことが知られており、やはり高血圧や糖尿病、脳梗塞・脳出血・心不全・不正脈・心筋梗塞などの発症リスクが増大するため、注意が必要です。
以上のことからも、飲酒による睡眠時無呼吸症候群は低酸素状態とアルコールの両方が高血圧や心臓病のリスクを増大させるため、お酒によるいびきがいかに危険かがわかります。
家族やパートナーへの影響
お酒を飲むことによって生じるいびきを放置してしまうと、家族やパートナーにもさまざまな悪影響を及ぼします。飲酒時はより高度に気道が狭窄しやすく、狭窄度合いが強ければ強いほど、いびきの音も大きくなるため、隣で寝ている家族やパートナーにとっては、ほとんど騒音のようなものです。
一般的に、睡眠中の騒音レベルは40dB(デシベル)以下が睡眠に適していると言われており、40〜50dBでは半数以上の人が睡眠を阻害され、50dB以上ともなると軽度の睡眠障害が生じる可能性が出てきます。
一方で、いびきは平均で50dB、重度のいびきの場合は80dBにも達すると言われており、かなりの確率で家族やパートナーの睡眠を阻害します。
睡眠時間の短縮、睡眠の質の低下、熟睡感の低下、中途覚醒の増加など、家族やパートナーの睡眠にさまざまな悪影響を及ぼすことを知っておくべきです。
この状態が続けば、夫婦や家族関係の悪化、ストレスによる心身の健康被害にもつながるため、やはり早期から適切に対処することが重要です。
実際に「お酒を飲んだ後のいびき」で悩んでいた方の体験談と改善事例
お酒を飲んだ後にいびきをかく場合、それによって生じる症状や悪影響、さらには改善方法など、十人十色です。さまざまな事例を知ることで、お酒を飲んだ後のいびきに悩まれる方の症状改善のきっかけになるかもしれません。
ここでは、実際に「お酒を飲んだ後のいびき」で悩んでいた方の体験談と改善事例を3つ紹介します。
20代男性:飲酒中の水分摂取で改善した事例
20代男性のAさんはこれまであまり飲酒する機会はありませんでしたが、会社に就職してからは付き合いもあって毎日のように飲酒する生活が続いていました。同棲している彼女からは、以前はいびきを認めなかったものの、飲酒するようになってからいびきがうるさくて迷惑と言われ、初めていびきを自覚したそうです。
実際に、飲酒した翌朝は熟睡感が乏しく、日中に眠気を感じたり、仕事に十分集中できなくなることも少なくなく、仕事で大きなミスをしてしまったことから、改善を決意したそうです。
仕事の付き合いもあって飲酒の機会は簡単に減らせないため、飲酒の際にはなるべく水分摂取をして、アルコールの摂取量を減らすように努めたところ、取り組み開始から顕著にいびきの改善を認めました。
それとともに、飲酒翌朝も以前のような熟睡感を得られるようになり、仕事にも集中できるようになったそうです。
さらに、彼女からも「ようやく私も安眠できるようになった」と言われ、水分摂取に取り組んで良かったと実感したそうです。
40代女性:飲酒時間の調整で改善した事例
40代女性のBさんは、会社員として普段から規則正しく生活していましたが、会社での役職が上がるにつれてストレスが溜まることも多く、日に日に飲酒量や食事量が増えていきました。また、寝る直前まで深酒してしまうことが習慣化していったそうです。
その結果、飲酒した日の夜は必ずと言っていいほど大きないびきをかくようになり、家族からは「いびきがうるさくて私たちは眠れない」と指摘されたことに大変ショックを受けたそうです。
実際に、飲酒すると夜間に途中で目が覚めてしまい、自身の睡眠の質が低下していることも自覚していたため、自身や家族の睡眠を守るためにもお酒の飲み方を変えることを決意しました。
そこで、飲み終わる時間を就寝の4時間以上前にするようにルールを決めて飲酒したところ、寝る時には比較的酔いも覚め、これまでにはない熟睡感を取り戻すことができました。
さらに、飲酒時間が短くなったことで飲酒量も自然と低下し、自然と体重も落ちたそうです。
身体が以前より軽くなり、朝もスッキリ目覚めることができるようになったため、これまで以上に仕事に集中できるようになったそうです。
60代男性:生活習慣の改善で改善した事例
60代男性のCさんは、元々はサラリーマンとして規則正しい生活を送っていましたが、定年してからは家でお酒を晩酌する機会が増え、ほとんど運動もしないため、急激に体重も増加していました。
妻からも健康面で心配され始め、さらにはいびきが最近うるさくなっていることを指摘され、仕方なく医療機関を受診したところ、高血圧や糖尿病を認め、睡眠時無呼吸症候群の可能性があると指摘されたそうです。
医師からは、医学的な治療よりも前に、現在の生活習慣の改善が最優先であると言われ、食事内容や飲酒量、飲酒時間を見直すように指示されました。
さらに、ほとんど運動をすることもなかったため、最低でも週に3回はランニングやウォーキングをするように生活を変えたそうです。飲酒量や飲酒時間を制限したところ、比較的早期にいびきが改善し、その後数ヶ月かけて徐々に体重が減少していくにつれて、いびきもさらに改善していったそうです。
半年後には高血圧や糖尿病の値も改善しており、睡眠と健康が密接に関わっていることを強く実感できたそうです。
【まとめ】お酒を飲んだ後のいびきの原因・対策
この記事では、お酒を飲んだ後のいびきの原因や対策、実際の体験談について詳しく解説しました。
お酒を飲むことで舌根沈下や気道の浮腫、肥満など、さまざまな影響によって気道が狭窄しやすくなるため、いびきをかきやすくなります。お酒に伴ういびきを放置すれば、睡眠時無呼吸症候群の発症による睡眠の質の低下、日中の眠気などの症状により、学業や仕事に支障をきたす可能性があります。
さらに、長期に及べば高血圧や糖尿病、心血管疾患、脳血管障害のリスク増大につながるため、早期からこの記事で紹介したような方法で対処することが重要です。
一方で、自身のいびきがどの程度危険かわからず、なかなか治療や対策に前向きになれない方も少なくないでしょう。
下記の記事を読むことで、自身のいびきの危険度を簡単にセルフチェックできるため、ぜひご一読ください。
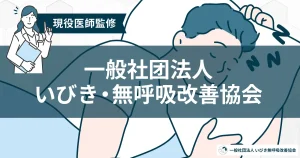
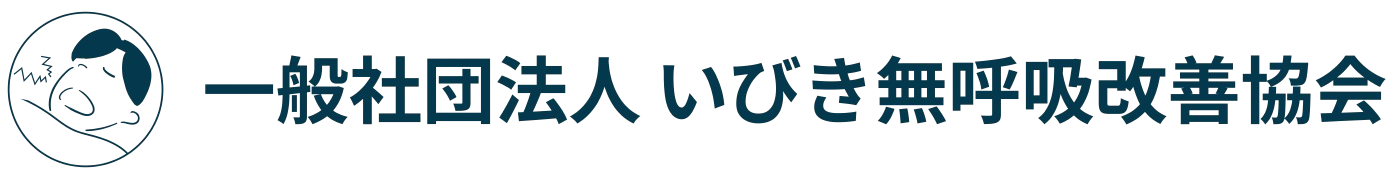
コメント