- 口を閉じてもいびきが改善しない
- 口を閉じてもいびきが出る場合どのように対処すべき?
このような疑問や悩みを抱えている方も少なくないでしょう。
口を閉じればいびきが改善することもありますが、原因によっては口を閉じてもいびきが改善しないことがあります。特に、いびきの原因が鼻腔や口腔の奥の狭窄の場合、口を閉じても十分な改善が得られない可能性が高いです。放置すれば睡眠の質の低下やさまざまな健康被害を及ぼすため、早期から適切に対応することが重要です。
そこでこの記事では、口を閉じてもいびきが出る原因や対策・治療法を解説します。この記事を読むことで、口を閉じても改善しないいびきに適切に対処でき、快眠を目指すことができるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
口を閉じてもいびきが出る原因は?
いびきとは鼻腔・咽頭・喉頭・気管などによって形成される気道のいずれかが狭窄し、そこを通過する空気が粘膜を振動させることで生じる振動音です。
口が開いていると吸気時に下顎が後下方に移動するため、後方の気道が狭窄しやすくなり、いびきをかきやすくなるため、口を閉じることでいびきが改善する可能性があります。
一方で、下記のような原因の場合は口を閉じてもいびきが改善しない可能性があるため、注意が必要です。
鼻の通りが悪く「鼻いびき」になっている
口を閉じてもいびきが出る原因として、鼻の通りが悪く「鼻いびき」になっている可能性があります。ヒトは通常、睡眠中は鼻呼吸を行うことで鼻汁によって加温・加湿された空気を吸い込みますが、何らかの原因で鼻腔が狭くなると、そこを通過する空気が粘膜を振動させていびきをかきます。
具体的には、アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎による鼻づまり、鼻茸、鼻中隔湾曲症などが主な原因です。これらの原因によって鼻粘膜が肥厚したり、鼻中隔が湾曲して鼻腔が狭くなることでいびきをかきます。
また、症状が進行して鼻呼吸が困難になると、十分な酸素を取り込むことができず、口呼吸の割合が増加するため、やはり気道狭窄を引き起こす原因です。
また口呼吸が増加すると、吸い込む空気が加湿加温されず、寒冷・乾燥した空気が気道に流入するため、炎症を引き起こしやすくなります。気道に炎症が生じると浮腫が生じ、さらに気道が狭窄していびきをかきやすくなるため、注意が必要です。
舌の付け根が喉に落ち込んでいる
口を閉じてもいびきが出る原因として、舌の付け根が喉に落ち込んでいる可能性があります。舌は咽頭の奥から口腔内の前方に向かって突出している器官であり、味覚や嚥下・構音、発話などさまざまな機能に関わっています。
しかし、睡眠中は舌を構成する筋肉が弛緩することで、前方に突出していた舌が後方(舌の付け根方向)に落ち込んでしまい、その奥にある気道を狭窄させる可能性があるため、口が閉じていても注意が必要です。
弛緩した舌は重力の影響を強く受けるため、特に仰向けで寝ている場合は舌が後方に落ち込みやすく、最もいびきをかきやすくなります。一方で、横向き寝やうつ伏せ寝であれば舌は側方や前方に移動するため、後方の気道が狭窄しにくく、いびきを引き起こしにくい寝姿勢です。
また、舌は筋肉以外にも脂肪なども付いているため、肥満の方の場合舌に脂肪が多量に沈着し、さらに喉に落ち込みやすくなるため、注意が必要です。
喉の奥のたるみや振動
口を閉じてもいびきが出る原因として、喉の奥のたるみによって振動が生じている可能性があります。気道は鼻腔・咽頭・喉頭などを形成する軟骨・骨・筋肉など、さまざまな組織によって複合的に形成されたスペースであり、これらの組織が支持する事で周囲からの圧迫を予防しています。
しかし、加齢による筋力の低下や深い睡眠による筋弛緩作用、アルコールや睡眠薬の常用に伴う筋弛緩作用などによってこれらの支持組織の力が弱まり、たるんでしまうと、周囲の脂肪などから圧迫を受けやすくなり、気道狭窄を招くため、注意が必要です。
これらの要因によって気道が狭窄すれば、そこを通過する空気が気道の粘膜を振動させ、いわゆる喉いびきをかきやすくなる原因となります。口の奥の組織のたるみによって生じるいびきであり、鼻呼吸によって流入した空気が粘膜を振動させていびきが生じるため、仮に口を閉じていても改善されない可能性が高いです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性
口を閉じてもいびきが出る原因として、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。睡眠時無呼吸症候群とは、その名の通り、睡眠中に低呼吸(30%以上の気流低下、かつ動脈血酸素飽和度が3%以上低下した状態、あるいは覚醒を伴う状態が10秒以上継続)や無呼吸(10秒以上の呼吸停止)の頻度が増加してしまう病気です。
睡眠時無呼吸症候群の原因は肥満や耳鼻科疾患の発症、舌が大きい、顎が小さい、生活習慣の乱れなどさまざまであり、どのような原因にせよ、気道が狭窄することでいびきが生じます。仮に口を閉じても、これらの原因によって喉の奥や鼻腔の狭窄が解消されない限り、いびきが改善する可能性は低いです。
また、睡眠時無呼吸症候群に陥ると著しく睡眠の質が低下し、そのストレスによってさまざまな健康被害を及ぼすことが知られているため、早期から原因を精査し、原因に合わせて適切に対応することが重要です。
顎や歯並びの形状
口を閉じてもいびきが出る原因として、顎や歯並びの形状が原因となっている可能性があります。先述したように、口呼吸によるいびき増加のメカニズムは、吸気時に下顎が後下方に移動し、後方に位置する気道が狭窄するためです。
そのため、口を閉じれば気道の狭窄が予防でき、いびきを改善できる可能性がありますが、生まれながらに顎が小さい場合や奥に引っ込んでいる場合は、口を閉じても気道が狭く、いびきをかいてしまう可能性があります。
また、顎の形以外にも歯並びもいびきの発症に深く関わっており、歯並びが悪いと舌が正常の位置に収まることができず、後方に落ち込みやすくなるため、やはりいびきをかきやすくなります。
また近年では、美容目的で顎を小さくする手術を受ける方も増えていますが、この手術では顎を後方に移動させて固定するため、後天的に気道狭窄やいびきを引き起こす可能性があり、注意が必要です。
口を閉じてもいびきが出る場合の対策
口を閉じてもいびきが出る状態を放置すれば、睡眠中に十分な酸素を取り込むことができず、疲労した脳や体は十分な回復が得られないため、日中の強い眠気や集中力の低下など、さまざまな支障をきたす原因となります。
さらに、長期化すればストレスが溜まり、高血圧や脳血管障害などの発症リスクも上がることが知られており、早期対策が重要です。
ここでは、口を閉じてもいびきが出る場合の対策を5つ紹介します。
鼻腔拡張テープ・ノーズクリップの活用
口を閉じてもいびきが出る場合の対策として、市販で購入できる鼻腔拡張テープ・ノーズクリップの活用が挙げられます。口を閉じてもいびきが出る場合、いびきの原因が鼻腔の狭窄である可能性が考えられ、鼻腔拡張テープやノーズクリップを使用することで狭窄した鼻腔を拡張させ、いびきの改善が期待できます。
具体的には、アレルギー性鼻炎や慢性鼻炎、慢性副鼻腔炎などの疾患による鼻づまりや花粉症による鼻づまりが良い適応です。
一方で、粘膜の重度な肥厚に伴う鼻茸や、鼻腔を左右に隔てる鼻中隔が湾曲して鼻腔の狭窄を引き起こす鼻中隔湾曲症などの疾患に対しては、鼻腔拡張テープ・ノーズクリップの効果は限定的、もしくは効果がない可能性があり、根治的な解決にならない可能性があります。
鼻腔拡張テープ・ノーズクリップは市販で簡単に購入でき、使用することに伴う大きな合併症や副作用も少ないため、病院を受診する前に一度試してみると良いでしょう。
舌トレーニングで舌と喉を鍛える
口を閉じてもいびきが出る場合の対策として、舌トレーニングで舌と喉を鍛えることもおすすめです。舌トレーニングとは、その名の通り舌を定期的に動かすことで舌の筋力を維持・向上したり、舌の位置異常を正常に戻すことのできるトレーニングです。
具体的には下記のようなトレーニング方法が挙げられます。
- あいうべ体操:口を「あ~」「い~」「う~」「べ~」の発声の際と同様に動かし、舌や口・顔面の筋肉を鍛える体操
- 舌を上下左右に大きく動かす運動:舌を上下方向と左右方向に動かすことで、舌や口周囲の筋肉を鍛える体操
- 舌を前に突き出す運動:舌を前に突き出すことで舌の筋力増強や口周囲・顔面全体の筋肉を鍛える体操
これらの運動を日々定期的に行うことで舌の筋力が向上し、睡眠中の舌根沈下を予防することができ、いびきの改善を目指せます。
また、舌の位置が適正化されることで、位置異常における舌根沈下が予防されるため、やはりいびきに効果的な運動です。特にお金もかけず、今日からでも自宅で簡単に実践可能なため、ぜひ試してみると良いでしょう。
寝室の湿度と温度を最適化する
口を閉じてもいびきが出る場合の対策として、寝室の湿度と温度を最適化することも重要です。寝室の温度・湿度は気道の状態に大きく影響し、不適切な設定で寝てしまうと、気道に炎症を引き起こし、いびきが悪化する原因となります。
例えば、寒冷乾燥した空気を吸い込むと気道は乾燥し、空気中のゴミをうまく回収できなくなるため、気管支炎などを発症する可能性が高まり、いびきを引き起こす可能性が高まります。
一方で、高温多湿な寝室環境ではダニやカビが繁殖しやすく、これらを吸い込むことでアレルギー性鼻炎や喘息などのアレルギー疾患を引き起こす可能性が高まるため、注意が必要です。これらのアレルギー疾患を発症すれば、やはり気道のいずれかに浮腫が生じて狭窄するため、いびきを引き起こす原因となります。
まずは寝室の湿度や温度を湿度計や温度計を用いてチェックし、必要に応じて加湿器や除湿機、エアコンなどを使用して快適な寝室環境を目指しましょう。
寝る姿勢・枕の高さを見直す
口を閉じてもいびきが出る場合の対策として、寝る姿勢や枕の高さを見直すことも重要です。実は寝る姿勢や使用する寝具はいびきの発症に深く関わっており、姿勢や寝具次第で口を閉じてもいびきが出てしまう可能性があります。
先述したように、寝る姿勢によって舌の位置が移動する方向が変わり、横向き寝やうつ伏せ寝の場合は側方、もしくは後方への移動なので舌根沈下を予防できますが、仰向け寝の場合は舌が後方に移動するため、後方に位置する気道を最も圧迫しやすく、注意が必要です。
また、枕の高さが高すぎる場合、具体的には7cm以上の高さの枕を使用している場合、頭部と体幹部に高低差が大きく生まれ、結果として頚部が過剰に屈曲してしまうため、気道狭窄を引き起こしていびきをかきやすくなります。
また枕以外にも、柔らかすぎるマットレスの使用も腰が沈み、頚部が過剰に屈曲する原因となるため、注意が必要です。心当たりのある方は、今日からでも寝姿勢や寝具を見直してみると良いでしょう。
体重管理・生活習慣の改善
口を閉じてもいびきが出る場合の対策として、適切な体重管理や生活習慣の改善も重要です。いびきの最大の原因は肥満であり、肥満の方は首周りに脂肪が多量に沈着するため、その脂肪によって気道が圧迫されやすくなり、いびきをかきやすくなります。
特に、肥満度を表す指数であるBMI「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」が25以上の方はいびきを発症するリスクが高まるため、注意が必要です。
肥満を予防するためには、規則正しくバランスの良い食事摂取や定期的な運動習慣を身につけることが肝要です。就寝直前までの暴飲暴食は腹部を膨満させ、気道抵抗が上がることでいびきをかきやすくなるため、控えましょう。
他にも、就寝直前までのアルコール摂取や睡眠薬の常用は舌を過剰に弛緩させ、気道狭窄を引き起こす原因となるため、控えるべきです。このように、日々の生活がいびきの発症に関わるため、これを機に見直してみると良いでしょう。
口を閉じてもいびきが出る場合、病院での治療法は?
上記のようなセルフケアで改善できれば良いですが、原因によってはセルフケアでの改善が困難ないびきであることも少なくありません。セルフケアで改善できない場合は、医療機関を受診し、いびきの原因にあった適切な治療を行う必要があります。
ここでは、口を閉じてもいびきが出る場合における、病院での治療法を5つ紹介します。
耳鼻咽喉科・睡眠外来で検査をする
口を閉じてもいびきが出る場合、まずは耳鼻咽喉科・睡眠外来でいびきの原因を調べるための検査を受けましょう。セルフケアでも改善できないいびきの場合は何らかの病気を発症している可能性があり、病気や原因次第で選択すべき治療法も変わるため、まずは各種検査を行うことが重要です。
いびきは鼻腔や咽頭・喉頭などの気道狭窄が原因であることがほとんどのため、鼻腔や咽頭・喉頭の疾患を専門とする耳鼻咽喉科を受診するか、いびき症状の治療に特化した睡眠外来への受診がおすすめです。
これらの診療科では、いびきの発生状況やいびきの音、睡眠の質などを問診し、各種身体診察、CTやMRIなどの画像検査を行い、総合的にいびきの原因を評価します。
さらに、睡眠時無呼吸症候群を強く疑う場合は、睡眠中の低呼吸や無呼吸の頻度を一晩中モニタリングする「PSG検査(ポリソムノグラフィー)」が実施されることもあります。
医療機関への受診を渋って、不適切なセルフケアを継続する方が身体にとってよくないため、お悩みの方はまずは医療機関に受診することが重要です。
鼻づまりを改善する治療
口を閉じてもいびきが出る場合、耳鼻咽喉科で鼻づまりを改善する治療を行うことが選択肢の1つです。
特に原因がアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎、鼻茸、鼻中隔湾曲症などの耳鼻科疾患の場合、口を閉じてもいびきは改善せず、また重症度によっては市販の点鼻薬や市販のグッズ(鼻腔拡張テープなど)でも改善困難であるため、耳鼻咽喉科で専門的な治療を受ける必要があります。
例えば、鼻粘膜がキノコのように肥厚して鼻腔を狭窄させる鼻茸の場合、レーザー治療による鼻粘膜の焼却が必要となります。また、鼻腔を左右に隔てる鼻中隔が湾曲して鼻腔を狭窄させる鼻中隔湾曲症が原因の場合、レーザー治療での粘膜焼却は意味がなく、原因となる鼻中隔そのものを切除する必要があるため、手術療法が必要です。
他にも、難治性の慢性副鼻腔炎に対して内視鏡下鼻内副鼻腔手術(ESS)が必要となることもあり、原因疾患や程度によって行われる術式も異なります。
マウスピース治療
口を閉じてもいびきが出る場合、マウスピース治療も選択肢の1つです。
マウスピース治療とは自身の顎の骨格や歯列に合わせてマウスピースを作製し、装着することで下記のような効果を得る治療法です。
- 下顎を前方に固定し、後方の気道狭窄を改善させる
- 舌の位置を適正化し、舌根沈下を改善させる
マウスピースを装着することで下顎を前方に固定することができるため、元々の小顎によるいびきでお悩みの方にとっては良い適応となります。
また、舌の位置が低く、口を閉じた時に舌が上顎につかない方(これを低舌位という)の場合、舌が後方に沈下しやすく、マウスピース装着によって正しい位置に矯正できるため、舌根沈下やいびきを改善できる可能性があります。
市販でもマウスピースは購入できますが、市販のものは自身の顎や歯列に合わせて作製されていないため、フィットせずに顎や歯の痛みが生じる可能性があり、歯科や口腔外科で作製する方が安全です。
CPAP療法
口を閉じてもいびきが出る場合、CPAP療法も選択肢の1つとなります。CPAP療法とは「Continuous Positive Airway Pressure(持続陽圧呼吸療法)」の略で、睡眠中に特殊なマスクを装着し、吸気時も呼気時も持続的に気道に空気を送り込むことで陽圧をかけ、特に吸気時における気道狭窄を予防する治療法です。
CPAPによって鼻腔から空気が送られて気道に陽圧がかかれば、気道を押し広げることができるため、口を閉じてもいびきが出るケースでも効果が期待できます。
実際に、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020」におけるCPAP療法のエビデンスレベルはA(効果の推定値に強く確信がある)であり、睡眠時無呼吸症候群によって日中の眠気などの臨床症状を認める場合や、中等度〜重症の症例に対して推奨されています。(参照:睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020)
CPAP療法を保険適応で受けるためには耳鼻咽喉科や呼吸器内科でPSG検査を受ける必要があるため、まずはこれらの診療科を受診すると良いでしょう。
レーザー治療
口を閉じてもいびきが出る場合、原因次第ではレーザー治療も選択肢の1つとなります。レーザーを当てて気道の狭窄の原因となっている構造物を焼却・破壊することで、気道の開通性を改善し、いびきの改善を目指す治療法です。
代表例としては重度のアレルギー性鼻炎などが挙げられます。アレルギー性鼻炎の発症初期は一時的に粘膜に浮腫が生じるため、薬物療法などで浮腫を軽減させれば症状も改善しますが、症状が進行すると粘膜が徐々に肥厚し、不可逆的に鼻腔が狭窄してしまいます。そこで、肥厚した粘膜をレーザーで焼却することで鼻腔の開通性を改善させ、いびきを改善させます。
一方で、レーザーでは骨は焼却できないため、骨が湾曲して鼻腔が狭窄する鼻中隔湾曲症などの治療には不適切です。
また最近では、扁桃肥大に対してレーザー治療を行うケースも増えています。口腔内のリンパ組織である扁桃が肥大すると、気道が狭くなっていびきの原因となりますが、腫大した扁桃をレーザーで焼却することでいびきの改善が目指せます。
口を閉じてもいびきが出る症状で悩んでいた方の体験談と改善事例
- 口を閉じてもいびきが出る症状は本当に治るの?
- 治った人はどのように改善させたの?
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
実際に口を閉じてもいびきが出る症状は原因によって改善方法も異なり、人によってその効果にも差があります。
ここでは、実際に口を閉じてもいびきが出る症状で悩んでいた方の体験談と改善事例を3つ紹介します。
自身の改善策を見つける糸口にもなるため、ぜひ参考にしてください。
20代男性:レーザー治療で改善した事例
20代男性のAさんは、花粉症や季節性の鼻炎を認めるくらいで、これまで大きな病気も認めない健康的な会社員です。
春になると例年花粉症が悪化し、鼻水や鼻詰まりに悩まされていましたが、同棲した彼女に「いびきがとてもうるさくなった」と指摘されて、初めていびきがあることも自覚したそうです。
それにショックを受けて市販の口閉じテープを購入して使用したところ、口は閉じたもののいびき自体は改善されず、寝苦しさだけ悪化してしまいました。
そこで、近隣の耳鼻咽喉科を受診したところ、いびきは鼻いびきで、口閉じテープでは改善できないため、鼻の治療を行うことを勧められたそうです。
最初に点鼻薬や内服での治療を勧められ、実際に使用すると症状は多少緩和するものの、いびき自体はあまり改善を認めなかったそうです。
そこで、次の治療ステップとしてレーザー治療を勧められ、実際に行ったところ、術後数日で鼻の通気性が格段に改善し、鼻詰まりやいびきも改善しました。同棲する彼女の隣でも安心して眠れるようになり、早期に治療に踏み切って良かったと感じたそうです。
40代女性:生活習慣の見直しで改善した事例
40代女性のBさんは総合職として日々多忙に働いており、病気などは認めないものの、食事の時間が不定期であったり、運動不足に陥るなどの生活習慣の乱れによって、40代に入ってからは徐々に体重も増加傾向でした。
夫からは「口を閉じているのに唸り声のようないびきをかいている」と指摘され、自身のいびきを自覚したそうです。
またいびきと同時に、日中に激しい眠気に襲われたり、集中力が低下するなど、仕事にも支障が出始めていました。
そこで、睡眠外来を受診したところ、肥満によって首回りに脂肪が蓄積し、その脂肪によって喉いびきが生じていると指摘を受けました。いびきや日中の眠気改善のためにダイエットが必要であると指示され、そこからは規則正しい食習慣と定期的な運動習慣を身につけるようにしたそうです。
糖質や脂質の高い食費は控え、野菜や果実をメインにして、できる限り毎日同じ時間に3食摂取するように意識したそうです。平日の早く帰宅した日や土日はできる限りランニングやウォーキングを行い、3ヶ月で10kgほどの減量に成功しました。
体重減少とともにいびきも改善し、日中の眠気も解消されたため、仕事で大きなミスを犯す前に対策に取り組んで良かったと実感したそうです。
60代男性:CPAP療法で改善した事例
60代男性のCさんは以前から検診で肥満や、高血圧・糖尿病などの生活習慣病を指摘されており、生活習慣の改善を指導されていましたが、自営業が多忙でなかなか改善することができませんでした。
妻からは以前から「口は閉じているのに大きないびきをかいていて、途中で呼吸が止まったりして心配になる」と指摘されており、熟睡感が得られなくなったり、日中に眠気で仕事に手がつかなくなるなど、さまざまな悪影響が出ていたそうです。
そこで近隣の睡眠外来を受診したところ、すぐにPSG検査が必要と言われ、実際に検査を行ったところ重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されたそうです。
症状改善のためにCPAP療法を行う運びとなり、実際にCPAPを導入したところ、いびきや日中の眠気は早期に改善しました。また同時に、検診で指摘されていた血圧や血糖値もやや低下したため、CPAP療法を導入できて良かったと実感したそうです。
【まとめ】セルフケアでいびきが改善しない場合は専門医に相談を
いびきは気道の狭窄によって生じるため、鼻腔や喉頭(喉の奥の部分)が狭窄していれば口を閉じても改善しない可能性が高いです。口を閉じてもいびきが出る場合、まずは市販のグッズや寝具の見直し、生活習慣の改善など、簡単にできるセルフケアでの改善を目指しましょう。
一方で、これらのセルフケアで改善困難な場合、何らかの病気を発症している可能性が高いため、注意が必要です。実はいびきを長期間放置すると、高血圧や糖尿病・脳血管障害などの発症リスクが増加することが知られているため、たかがいびきと放置せず、早期から適切な対処・治療を行うことが重要です。
「いびきなんかで病院に行っていいのかわからない」と思われる方に向けて、下記の記事では自身のいびきの危険度を簡易的にチェックできる方法を紹介しているため、ぜひこちらもご一読ください。
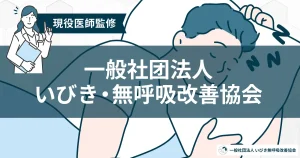
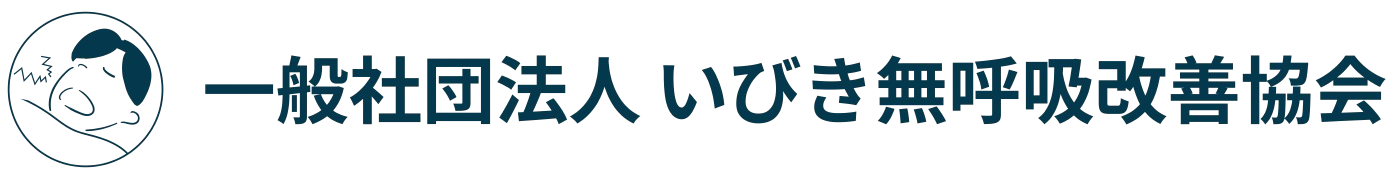
コメント