- 肥満だといびきをかきやすいって本当?
- 肥満といびきの関係は?
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
いびきはさまざまな原因で生じますが、中でも肥満はいびきの最大の原因であり、どちらも放置すればさまざまな健康被害をもたらすため、早期から対策することが重要です。
この記事では、肥満によっていびきをかきやすくなる原因や、いびきと肥満の関係、取るべき対策などについて詳しく解説します。この記事を読むことで、肥満に伴ういびきに対して適切に対策することができ、より良い睡眠や健康を取り戻すことができるようになるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
いびきと肥満の関係性|太るといびきをかきやすくなる原因は?
「いびき=気道が狭窄した状態」であり、その原因は多岐に渡りますが、中でも肥満は最大の原因と言われています。
実際に、肥満度を表すBMI【体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)】が高くなればなるほど、いびきをかきやすくなることが知られており、特にBMI25以上の方はリスクが高まります。
太るといびきをかきやすくなる原因は主に下記の5つです。
喉や首まわりの脂肪が気道を圧迫する
太るといびきをかきやすくなる原因として、喉や首まわりの脂肪が気道を圧迫することが挙げられます。
気道は咽頭や喉頭の筋肉・軟骨・粘膜などによって構成されており、周囲を脂肪組織によって覆われています。
そのため、肥満によって喉や首まわりの脂肪が増加すると、気道が圧迫されやすくなり、いびきの原因となるため、注意が必要です。
また、気道を形成する舌や唾液腺、軟口蓋などの組織そのものにも肥満によって脂肪は蓄積しうるため、これらの組織の脂肪が増加することで内部から気道が圧迫され、いびきをかきやすくなります。
Jenniferらの報告によれば、いびきの原因となる睡眠時無呼吸症候群を引き起こしやすい身体的特徴の1つとして“頸部周囲径”が挙げられており、男性で43cm、女性で40.5cm以上の頸部周囲径の場合はリスクが高いとされています。(参照:Obstructive Sleep Apnea – StatPearls – NCBI Bookshelf)
また、姿勢が悪い人は頚部に脂肪がつきやすいことが知られており、BMIが低くても気道狭窄を招く可能性があるため、注意が必要です。
舌が肥大化して奥に落ち込みやすくなる
太るといびきをかきやすくなる原因として、舌が肥大化して奥に落ち込みやすくなることも挙げられます。そもそも舌は咽頭の後方から口の前方に向けて伸びている組織であり、筋肉や脂肪などさまざまな組織によって構成された組織です。
肥満になるともれなく舌にも脂肪が蓄積するため、舌は肥大化しますが、口腔内は顎や軟口蓋などによって作られた閉鎖空間であるためスペースが限られており、肥大化した舌は咽頭の奥の方に落ち込みやすくなります。
特に、睡眠中は舌の筋肉が弛緩し、重力の影響を受けやすくなるため、仰向けで寝る場合は重力によって舌がさらに後方に落ち込みやすくなるため、いびきをかきやすくなります。
一方で、横向き寝やうつ伏せ寝の場合は、重力の影響を受けても舌は側方もしくは前方に移動しやすく、いびきをかきにくいです。また、生まれつき舌が大きい人の場合や顎が小さい人の場合、相対的に舌が後方に落ち込みやすく、肥満の影響をより強く受けやすくなるため、注意が必要です。
内臓脂肪が睡眠時の呼吸に影響する
太るといびきをかきやすくなる原因として、内臓脂肪が睡眠時の呼吸に影響することも挙げられます。
本来、ヒトは呼吸の吸気時に横隔膜や呼吸補助筋(肋間筋など)が拡張し、胸腔を押し広げることで陰圧にし、それによって肺も拡張することで肺内も陰圧になり、空気が肺内に流入します。
しかし、肥満で内臓脂肪が腹部に多い場合、横隔膜が十分に拡張できなくなるため、大きくて深い呼吸様式が困難となり、1回の呼吸で吸い込める空気量が減るため、代償性に呼吸回数が増加し、結果的に小さくて速い呼吸様式に変化してしまうのです。
さらに重症の肥満の場合、肺容量の低下により気道径が縮小し、気道抵抗増大を示すことも知られており、これもいびきの増悪につながります。(参照:肥満の息切れの機序とそれに対するリハビリテーション|高橋珠緒)
これらの呼吸機能に与えるさまざまな悪影響の結果、気道を通過する空気の流速が上がり、気道周囲の粘膜は振動しやすくなるため、いびきの音が大きくなる原因となります。
ホルモンバランスの変化
太るといびきをかきやすくなる原因として、特に女性の場合はホルモンバランスの変化が影響するため、注意が必要です。女性ホルモンの1つである「プロゲステロン」には、上気道の筋肉を活性化させる作用があり、気管の拡張作用があることが知られています。
また、女性ホルモンのもう1つである「エストロゲン」には肥満を防止する働きがあるため、エストロゲンが盛んに分泌されている時期は太りにくく、いびきをかきにくいです。
しかし、40〜50代に入って更年期を迎えるとこれらの女性ホルモンの分泌量が低下していくため、気道は狭窄しやすくなり、また体重も増加しやすくなるため、よりいびきをかきやすい身体に変化していきます。
また、更年期以外にも毎月の月経周期や妊娠など、女性ホルモンは経時的に変化しやすく、特に妊娠中は体重増加や酸素需要の増加に伴い口呼吸の割合が増加するため、やはりいびきをかきやすくなります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性
太るといびきをかきやすくなる原因として、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症している可能性があり、注意が必要です。睡眠時無呼吸症候群とはその名の通り、何らかの原因で気道が狭窄して睡眠中の低呼吸や無呼吸の頻度が増加する病気で、睡眠中に取り込める酸素量が低下することでさまざまな健康被害をきたします。
気道狭窄を伴うため、睡眠時無呼吸症候群発症者では大きないびきをかいたり、呼吸が停止した後に「ガゴッ」と大きな音のいびきを伴う点が特徴です。
特に肥満は睡眠時無呼吸症候群の最大のリスクであり、国内で報告された研究によれば、睡眠時無呼吸症候群でない患者群の平均BMIが22.7±1.4kg/m2であったのに対し、睡眠時無呼吸症候群を認める患者群の平均BMIは26.1±1.5kg/m2と有意に高値でした。(参照:睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疫学|佐藤 誠)
また、体重が10%増加すると睡眠時無呼吸症候群の重症度が約32%悪化し、体重が10%減少すると睡眠時無呼吸症候群の重症度が約26%低下するという報告もあります(参照:Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered breathing – PubMed)
以上のことからも、肥満によって睡眠時無呼吸症候群は発症リスクが大きく高まり、その結果いびきをかく可能性が高まるため、注意が必要です。
肥満によるいびきを改善するために今すぐできる対策
いびきを放置すると身体は低酸素状態に陥り、そのストレスによって高血圧や糖尿病、脳血管障害、不整脈などの心疾患など、さまざまな健康被害をもたらすことが知られています。
さらにその原因が肥満ともなると、肥満そのものもこれらの疾患の発症リスクを増大させる要因であるため、二重の意味でリスクが高いです。
そこで、肥満によるいびきを改善するために今すぐできる対策を5つ紹介します。
食事は寝る3時間前までに済ませる
肥満によるいびきを改善するために今すぐできる対策として、食事は寝る3時間前までに済ませることが重要です。就寝直前まで暴飲暴食を行うと、その後身体を動かす機会がないため、摂取したカロリーを消費する時間や機会が少なく、余分な脂質や糖質が身体に脂肪として蓄積してしまうため、肥満の原因となります。
特に脂質やタンパク質の豊富な食事は消化に3〜4時間ほどの時間がかかるため、高カロリー食ほど早い時間帯に食べ終えることが重要です。
また、就寝直前まで食事を摂ることで腹部が膨満し、横隔膜が広がりにくくなるため、浅く早い呼吸様式に変化してしまい、よりいびきをかきやすくなります。そのため、就寝直前までの食事は控え、最低でも寝る3時間前までに済ませることが重要です。
どうしても食事摂取の時間が遅い時間帯になる場合は、消化に時間のかかる肉や揚げ物は控え、うどんや魚類など消化に良い食べ物を摂取することで、脂肪の蓄積を予防でき、いびきの発症を抑える効果が期待できます。
アルコールを控える
肥満によるいびきを改善するために今すぐできる対策として、アルコールを控えることも重要です。
アルコールを摂取すると、主に下記の3つの作用機序でいびきをかきやすくなります。
- アルコールによる筋弛緩作用
- 過剰な水分・塩分摂取による浮腫
- 睡眠の質低下によるストレス蓄積
アルコールには筋弛緩作用があるため、就寝直前までのアルコール摂取によって舌の筋肉が弛緩し、舌根沈下を引き起こしやすくなることでいびきをかきやすくなります。
また、飲酒によって過剰に水分摂取し、おつまみなどの塩分高めの食事を好んで食べることで、気道に浮腫が生じやすく、それによっていびきをかく可能性も高まるため、注意が必要です。
さらに、アルコールの代謝産物であるアセトアルデヒドには中枢神経系の覚醒作用があり、アルコールの代謝の過程で中途覚醒(睡眠中に途中覚醒してしまうこと)が増加してしまい、睡眠の質の低下によってストレスが蓄積します。ストレスが溜まると、より多くの酸素を身体に取り込もうと口呼吸の割合が増加することで、結果的にいびきをかきやすくなるため、注意が必要です。
適正体重を目指す
肥満によるいびきを改善するために今すぐできる対策として、適正体重を目指すことも重要です。先述したように肥満はいびきにとって最大の原因であり、肥満であるほどいびきをかきやすくなることが知られています。
そこで、無理のない程度の継続的な運動と、規則正しい食事管理を徹底することで、適正体重に戻していびきの改善を図れます。
学会やガイドラインによって推奨される運動負荷は若干異なりますが、概ね「軽度〜中等度の運動を1回30分以上、最低週に3日以上」実施することを推奨しており、軽度〜中等度の運動とは具体的にランニングやウォーキング、水泳などです。(参照:肥満症の治療と管理|GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF OBESITY DISEASE 2022)
次に、いびきはBMI25以上で生じやすくなるため、仮に身長が170cmの人であれば、約72kgが目標体重となり、1日の摂取カロリーの上限は目標体重×25kcalに留めるべきです。(この例だと1,800kcal/日)
なお、食事内容も可能な限り脂質や糖質は抑えて、野菜や果実などを豊富に摂取するとより良いでしょう。
寝姿勢を工夫する
肥満によるいびきを改善するために今すぐできる対策として、寝姿勢を工夫することも重要です。寝姿勢はいびきの発症に深く関わっており、姿勢によって舌が重力を受ける方向が変わるため、舌による気道圧迫の程度も変化します。
例えば、仰向け寝の場合は舌が重力の影響で後方に落ちていくため、舌の後方に位置する気道が最も狭窄しやすく、いびきをかきやすい体位であるため、注意が必要です。
他方で、横向き寝の場合は舌が側方に、うつ伏せ寝の場合は前方に移動するため、舌後方の気道はむしろ開在しやすく、仰向け寝と比較していびきをかきにくい体位です。
実際に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020では、体位療法を治療法の1つとして挙げています。
一方で、体位療法にはその効果が標準化されたデバイスなど開発されておらず、あくまでエビデンスレベルはD(効果の推定値がほとんど確信できない)に位置付けられています。(参照:睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020)
舌トレーニングを行う
肥満によるいびきを改善するために今すぐできる対策として、舌トレーニングを行うことも重要です。舌トレーニングとはその名の通り、舌を鍛えることで舌の位置を正常化したり、舌の筋力の維持・向上によって舌根沈下を予防するトレーニングです。
特に、低舌位の方では、口を閉じている際に舌が上顎に付いておらず、下顎を押し下げることで口呼吸が起こりやすくなり、いびきの原因となるため、舌トレーニングによって舌の位置を正常化することによっていびきの改善が期待できます。
舌トレーニングの代表例としては、口を「あ~」「い~」「う~」「べ~」の形に大きく動かす、「あいうべ体操」が挙げられます。
- 「あ~」:大きく口を広げて、その状態で1秒間キープする。
- 「い~」:思いっきり口を横に広げて、その状態で1秒間キープする。
- 「う~」:唇を前方に思いっきり突き出して、その状態で1秒間キープする。
- 「べ~」:舌を前方ではなく顎先方向に伸ばし、その状態で1秒間キープする。
舌トレーニングは今日からでも簡単に実践できるため、ぜひ試してみると良いでしょう。
セルフケアで改善しないときは?いびき治療の選択肢
肥満によるいびきは必ずしも上記のようなセルフケアで改善できるわけではなく、肥満の程度やいびきの要因を他にも認める場合、医療機関での専門的な治療を行う必要があるため、注意が必要です。また、いびきに対する専門的な治療は原因によっても異なります。
セルフケアで改善しない場合のいびき治療の選択肢は主に下記の5つです。
耳鼻咽喉科・睡眠外来で検査を受ける
セルフケアで改善しない場合のいびき治療の選択肢として、まずは耳鼻咽喉科・睡眠外来で検査を受けることをおすすめします。
いびきの原因としては肥満が最も代表的ですが、気道は鼻腔・咽頭・喉頭・気管などさまざまな部位で構成されており、そのいずれかで狭窄が起こればいびきをかく可能性があるため、まずは肥満以外のいびきの原因も検索することが重要です。
そのためには、鼻腔・咽頭・喉頭・気管を総合的に評価することに長けた耳鼻咽喉科・睡眠外来を受診することが何よりの近道です。
また、これらの診療科では原因検索のために詳しい問診や身体診察、CT検査などの画像検査を実施し、総合的に評価して適切な治療法を決定します。
特に、睡眠時無呼吸症候群を発症している場合は、診断のために一晩中低呼吸や無呼吸の頻度を評価するために「PSG(ポリソムノグラフィー)検査」と呼ばれる専門的な検査を受ける必要があるため、耳鼻咽喉科・睡眠外来への受診が必要です。
マウスピース治療
セルフケアで改善しない場合のいびき治療の選択肢として、マウスピース治療も選択肢の1つです。マウスピースを装着することで下顎や舌の位置が適正な位置に矯正され、気道の狭窄が改善する可能性があります。
例えば、肥満の方は酸素需要が高いため、より多くの酸素を吸うために自然と口呼吸の割合が増加しますが、口呼吸の吸気時には下顎が後下方に下がるため、下顎の後方に位置する気道が狭窄しやすくなります。
さらに、低舌位(口を閉じた時に舌が上顎天井につかない方)の場合、舌の位置が正常でないことから下顎を押し下げてしまい、結果として口呼吸が増加するため、同様の理由で気道狭窄しやすく注意が必要です。
マウスピースを装着すれば下顎を前方に固定でき、舌の位置も矯正できるため、結果として口呼吸の割合を減らすことができ、いびきの改善が期待できます。
実際に、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020」でもマウスピースを用いた装具療法は推奨されており、そのエビデンスレベルはB(効果の推定値に中程度の確信がある)です。CPAP治療の適応とならない軽〜中等度の症例、あるいはCPAP治療が使用できない症例が良い適応となります。
CPAP療法
セルフケアで改善しない場合のいびき治療の選択肢として、CPAP治療も選択肢の1つです。CPAP治療とは特に睡眠時無呼吸症候群の代表的な治療法であり、Continuous Positive Airway Pressure(日本語で持続陽圧呼吸療法)の略です。
特殊なマスクを睡眠中に装着し、機器を通して持続的に気道に陽圧をかけて気道を開在させておく治療法であり、これによって気道狭窄やそれに伴ういびきを予防できます。
「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020」におけるCPAP療法のエビデンスレベルはA(効果の推定値に強く確信がある)であり、睡眠時無呼吸症候群によって日中の眠気などの臨床症状を認める場合や、中等度〜重症の症例に対して推奨されています。
特に睡眠時無呼吸症候群は睡眠の質の低下による日中の眠気、集中力の低下、さらに長期的には高血圧や心血管障害、脳血管障害の発症リスクが上がることが知られており、中等度以上の方は早期からCPAP療法を取り入れることが重要です。(参照:睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020)
レーザー治療
セルフケアで改善しない場合のいびき治療の選択肢として、レーザー治療も選択肢の1つです。
肥満だからといって必ずしもいびきの原因が肥満だけとは限らず、同時に耳鼻科疾患も発症している場合、鼻腔が狭窄することで鼻いびきをかきやすくなります。その場合、上記のようなセルフケアを行なっても鼻腔の狭窄は改善されないため、レーザー治療が必要となる可能性があります。
特にレーザー治療の良い適応となる疾患は、アレルギー性鼻炎、慢性鼻炎、慢性副鼻腔炎などです。
これらの疾患では鼻粘膜に炎症・浮腫が生じ、慢性化することで徐々に肥厚し、鼻腔の狭窄を招くため、鼻呼吸で空気が鼻腔を通過する際、いびきをかきやすくなります。そこで、レーザー治療によって肥厚した鼻粘膜を焼却することで、鼻腔の通気性を高めることができます。
一方で、鼻中隔湾曲症(鼻腔を左右に隔てる骨が湾曲して鼻腔が狭窄する病気)が原因で生じている鼻いびきの場合、どんなに粘膜を焼却しても骨自体の湾曲を治せないため、レーザーでの改善は困難であり、手術が必要となるため、いびきの原因に対して適切な診断が必要です。
内科的な肥満治療の併用
セルフケアで改善しない場合のいびき治療の選択肢として、内科的な肥満治療の併用も選択肢の1つです。重度の肥満を認める場合、セルフケアで改善するのは困難であり、また仮にダイエットを始めたとしてもすぐに体重が落とせるわけではありません。
そこで、食事療法や運動療法、さらには薬物療法を用いた内科的な肥満治療を医師の指導のもと行うことで、より効率的、かつ効果的な減量が見込めます。食事療法では、医師や管理栄養士の指導のもとで、摂取カロリーを制限した上で、栄養バランスの良い食事を摂取することが重要です。
また、食事療法と並行して運動療法を行うことで消費カロリーを上げることができるため、より効果的なダイエットが実践できます。
それでも減量が難しい場合は、食欲を減退させる薬や、摂取した糖質を吸収せずに尿に排出させる薬を内服や注射で投与し、ダイエットの効果を強化する方法もあります。もちろん、さまざまな副作用もあるため、肥満外来などを受診し、医師の指導のもとで治療していくことが重要です。
肥満によるいびきで悩んでいた方の体験談と改善事例
- 実際に肥満によるいびきはどう改善させるの?
- 肥満によるいびきは本当に改善するの?
このような疑問を持たれる方も少なくないでしょう。
実際に、肥満によるいびきを改善させる過程は人によっても異なり、経過や方法は千差万別です。
ここでは、肥満によるいびきで悩んでいた方の体験談と改善事例を3つ紹介します。
20代男性:耳鼻科受診で改善した事例
20代男性のAさんは社会人になってから食生活が乱れ、飲み会に参加する機会も増えていたことから、3年で体重が20kgも増加していたそうです。体重の増加とともに家族からはいびきを指摘されるようになり、「うるさくて隣の部屋にいても眠れない」と文句を言われたそうです。
いびきの悪化とともに熟睡感を得られなくなり、日中の強い眠気や集中力の低下によって仕事にも支障が出たため、改善を目指すと決めました。そこで食事制限と運動によるダイエットを始めたところ、比較的早期に体重は減少し、半年で10kgほどの減量に成功しました。
しかし、体重が低下してもいびきは改善を認めず、むしろ症状は悪化傾向にあったため、近隣の耳鼻咽喉科に受診したところ、いびきは鼻いびきであり、鼻茸がいびきの原因である可能性が高いと指摘されたそうです。
そこで、レーザー治療を行うこととなり、手術から数日するといびきは明らかに改善したそうです。いびきの改善とともに熟睡感も戻り、仕事のパフォーマンスも上がりましたが、医師からは太ると再発リスクがあると言われたため、その後も規則ただしい食事や運動習慣は継続するようです。
40代女性:いびき外来で改善した事例
40代女性のBさんは2人の子育てに励む専業主婦であり、子供の登校時間や帰宅時間に合わせて家事を行っているため、日々規則正しい生活を営んでいました。
しかし、40代に入ってから徐々に体重が増えてきており、ここ数年で体重が15kgほど増えたそうです。体重増加に伴いいびきをかくようになり、子供からうるさいと文句を言われたことに大変ショックを受けたそうです。
また、朝起きた時に口の中が渇き、口臭が気になり始めたため、いびきを改善しようと心に決めたそうです。ネットで検索したところ、いびき防止テープが効果的と知り、市販で購入しましたが、寝ている間にテープを剥がしてしまい、思ったような効果は得られませんでした。
そこで、近隣のいびき外来を受診したところ、いびきの原因は肥満が疑わしく、ダイエットをまずは行うように指導されたそうです。育ち盛りの子供に合わせて油分や糖質の高い食事が多かったため、野菜や果物などを増やして総カロリーを抑え、可能な限り日中は運動したり、買い物も徒歩で行くように生活習慣を変化させました。
その結果、徐々に体重は減っていき、体重の低下とともにいびきや起床時の口渇感・口臭も改善したそうです。健康的な生活を手に入れられたため、今後も生活習慣に気を遣って生活しようと教訓を得たそうです。
60代女性:CPAP療法で改善した事例
60代女性のCさんは夫とともに自営業を営んでおり、仕事が多忙で食事が不定期であったり、短時間で食事を済ませてしまうなど、健康的と言える食生活は送れていませんでした。
また更年期にさしかかり、急に体重が増加傾向にあり、ここ数年で15kgほど太ってしまったそうです。同時に、いびきの悪化も認めており、夫からは「時折呼吸が止まっている時がある」と心配されていました。
さらに、日中激しい眠気に襲われる機会が増え、車の運転中に事故を起こしかけたため、ネットで検索したところ、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いことを知り、医療機関を受診したそうです。病院でも同様の可能性を指摘され、PSG検査を実施したところ、重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されました。
ダイエットとともにCPAP療法をすぐに実施することとなり、装着当初は違和感もあったものの、すぐに慣れていびきも顕著に改善を認めました。日中に激しい眠気も解消され、交通事故を起こす前にしっかり治療できて本当に良かったと安心したそうです。
【まとめ】肥満によるいびきは早めに病院に相談しよう
肥満はいびきの最大の原因であり、特にBMIが25以上の方は気道の狭窄リスクが高いため、注意が必要です。肥満によるいびきを放置すれば睡眠時無呼吸症候群を発症し、睡眠の質の低下や高血圧・心疾患・脳血管障害など、さまざまな重篤な病気を発症するリスクを上げてしまうため、早期対策が必要となります。
まずはダイエットや使用する寝具の見直し、生活習慣の見直しなどが必要不可欠ですが、それでも改善できない場合は早期に医療機関を受診し、改めていびきの原因を特定し、その原因にあった適切な治療を行うことが重要です。
「いびきで病院に受診するなんて大げさ?」と思われる方も少なくありませんが、そのような方に向けて、下記の記事では自身のいびきの危険度を簡易的にセルフチェックできる方法を紹介しているため、ぜひご一読ください。
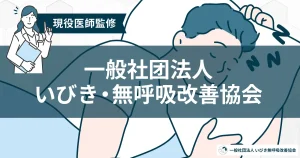
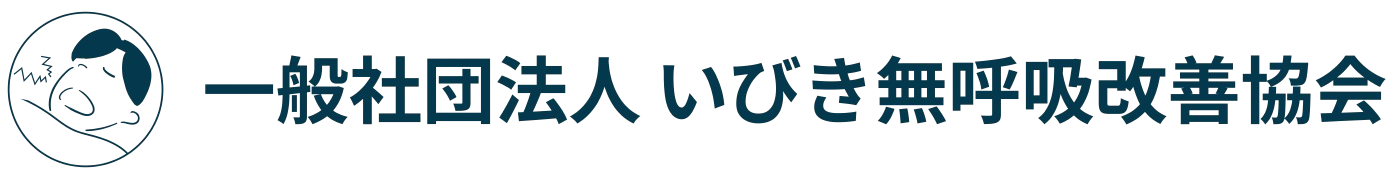
コメント