- 自分のいびきは鼻いびきと喉いびきどっち?
- 鼻いびきと喉いびきで原因や治療法は違う?
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
いびきは鼻いびきと喉いびきの2つに大別でき、いびきの生じる原因やいびきの音、対処法もそれぞれ異なります。
いびきの改善のためには、自身のいびきの原因を見極め、その原因にあった適切な対処を行うことが重要です。
そこで、この記事では鼻いびきと喉いびきの音の違いや原因、対処法を解説します。この記事を読むことで、自身のいびきの原因に合った適切な対処法を把握でき、いびきの解消を目指すことができます。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
鼻いびきと喉いびきの音の違いとは?
鼻いびきと喉いびきの違いは、音の高さや大きさです。
鼻いびきは主に鼻腔の狭窄で生じるため、そこを通過する空気は狭いところを通過することで「スースー」「ヒューヒュー」といった比較的高い音のいびきをかきます。
一方で、喉いびきの場合、原因のほとんどは舌根沈下であり、舌が気道を圧迫することで「ガーガー」「ゴロゴロ」など、低い唸り声のようないびきをかきます。
また、喉いびきの場合は舌根沈下によって一瞬呼吸が完全に止まり、その後「ガガッ」という大きな音のいびきをかくこともある点が鼻いびきとの違いです。
鼻いびきと喉いびきの特徴と原因とは?
「いびき=呼吸する際に、気道が狭窄していることで生じる気道粘膜の振動音」であり、狭窄部位によって鼻いびきと喉いびきの2つに大別できます。
鼻いびきと喉いびきとでは、それぞれいびきの特徴や原因は異なります。それぞれの違いを理解し、自身のいびきがどっちのいびきか確認しましょう。
鼻いびきの場合
鼻いびきとは、主に鼻腔が狭窄することによって生じるいびきであり、ただでさえ口腔よりも狭い鼻腔がさらに狭くなった状態で空気が通過するため、比較的高くて小さい音のいびきが鳴るのが特徴的です。
また、鼻いびきの場合はあくまで鼻腔の狭窄であり、舌根沈下などを認めないため、鼻腔の閉塞によって呼吸が止まりそうな場合は口呼吸に移行するだけで、完全に呼吸が止まってしまうことは稀です。
他の特徴として、鼻腔の狭窄が本態であるため、鼻いびきを認める方は覚醒時においても鼻づまりや鼻閉感、もしくは鼻汁などを伴います。
鼻いびきの主な原因は耳鼻科疾患であり、具体的にはアレルギー性鼻炎・鼻茸・慢性副鼻腔炎・鼻中隔湾曲症・感冒・花粉症などが挙げられます。
また、これらの病気に罹患した状態で過剰に飲酒すると、鼻粘膜が浮腫を引き起こし、さらに鼻いびきが悪化する可能性も高まるため、注意が必要です。
喉いびきの場合
喉いびきとは、主に咽頭部や喉頭部の気道が狭窄することで生じるいびきであり、鼻いびきよりも大きく、低音のいびきが鳴る点が特徴的です。
また、鼻いびきの場合は、鼻腔を介しての呼吸が困難でも口呼吸で補えますが、喉いびきの場合、鼻腔を介しても口腔を介しても、最終的に流入した空気が気道の狭窄によって気管に流入しにくい状態のため、程度が悪化した場合は一時的に呼吸が止まってしまう可能性があります。
また、口呼吸が主の場合、吸気時に下顎が後下方に移動することで、舌の後方に位置する気道は狭窄しやすくなり、喉いびきが生じやすくなります。
そのため、喉いびきの背景に口呼吸を認めることが多く、起床時に口腔内の乾燥が目立つことも特徴の1つです。
喉いびきの原因は主に扁桃肥大・アデノイド・舌根沈下・肥満・巨舌・小顎などが挙げられ、中でも舌根沈下はアルコールの過剰摂取や睡眠薬の常用、仰向け寝など、さまざまな要因で生じやすいです。
鼻いびきを治すための対処法3選
鼻いびきを治すためには、基本的には原因に合わせて鼻づまりや鼻腔の狭窄を改善させる必要があります。
鼻中隔湾曲症や重度の鼻茸などが原因の場合、物理的に鼻腔が閉塞しており、セルフケアでの改善は困難なため、医療機関での治療が必要不可欠ですが、多くの場合は下記のようなセルフケアで改善可能です。
それぞれ詳しく解説します。
点鼻薬・蒸気吸入などで鼻づまりを改善する
鼻いびきを治すための対処法として、点鼻薬・蒸気吸入などで鼻づまりを改善することがおすすめです。鼻いびきの多くの原因はアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎、花粉症などによって鼻粘膜に炎症が生じ、浮腫や鼻汁の増加を認め、鼻が詰まるためです。
そこで、抗ヒスタミン薬やステロイドを含む点鼻薬を使用することでアレルギー反応を抑制したり、鼻粘膜の血管収縮作用や抗炎症作用を持ち合わせるため、鼻粘膜の浮腫や鼻汁の漏出を抑制でき、鼻づまりを改善できます。
さらに、加湿加温された蒸気を吸入することで鼻粘膜の血行が促進し、鼻づまりの原因となる鼻汁や痰を柔らかくする効果が期待できるため、やはり鼻いびきの解消に役立ちます。
点鼻薬や蒸気吸入はどちらも市販で簡単に購入できるため、鼻づまりを伴ういびきを認める方はぜひ一度試してみると良いでしょう。
なお、原因が鼻中隔湾曲症や重度の鼻茸の場合、点鼻薬や蒸気吸入では十分な効果は得られず、改善が見込めない可能性があるため、原因の特定も治療する上では重要です。
枕や寝姿勢を工夫する
鼻いびきを治すための対処法として、枕や寝姿勢を工夫することも重要です。実は普段使用する枕や寝姿勢はいびきの発症に大きく関わっており、逆に言えば枕や寝姿勢を工夫するだけでもいびきを改善できる可能性があります。
例えば、枕の高さが高すぎる、具体的にいえば高さ7cm以上の場合、頚部が過度に屈曲してしまい、気道が狭窄することでいびきをかきやすくなります。また、柔らかすぎるマットレスの使用も腰が沈み、結果として頚部の過度な屈曲を招くため、注意が必要です。
次に、鼻いびき解消のためには寝姿勢も重要です。向けで寝る場合、鼻汁や鼻粘膜の腫脹は左右の鼻で同程度生じるため、左右両方の鼻腔が狭窄しやすくなります。
一方で、横向きで寝る場合は重力に伴ってより地面に近い方の鼻で鼻汁や鼻粘膜の腫脹が生じるため、逆の鼻では通気性が改善する可能性があり、鼻いびきを解消できる可能性があります。
どちらも簡単に実践できる方法のため、ぜひこれを機に試してみると良いでしょう。
生活習慣を見直す
鼻いびきを治すための対処法として、生活習慣を見直すことも重要です。生活習慣は気道の状態にも大きく影響するため、結果として鼻いびきが生じる原因にもなり得ます。
例えば、過剰なアルコールの摂取は、アルコールの血管拡張作用によって鼻粘膜の浮腫、鼻汁の増加につながるため、鼻いびきが生じやすくなる原因です。
また、過剰な塩分摂取や喫煙も気道の浮腫を引き起こすため、アルコール同様にイビキをかきやすくなります。
さらに、暴飲暴食など繰り返したり、深夜に夜食を食べてしまうような生活習慣を繰り返している場合、肥満に陥りやすくなり、気道周りの脂肪が増えることで気道が狭窄しやすくなるため、やはりいびきをかきやすくなります。
また、注意すべきは生活習慣だけではありません。就寝中に過剰にエアコンをかけてしまうと、乾燥した空気が鼻から流入し、鼻汁が固まったり、鼻粘膜における炎症を引き起こして鼻いびきが起こりやすくなってしまうため、就寝環境を整えることも重要です。
喉いびきを治すための対処法3選
喉いびきを治すためには、咽頭部や喉頭部における気道狭窄の原因を解明し、その原因に合わせて適切な対処法を選択することが重要です。
セルフケアでも改善できる場合と、原因によってはセルフケアでは改善困難で、医療機関で専門的な治療を行う必要があることもあります。
喉いびきを治すための対処法を3つ紹介します。
舌や喉の筋肉を鍛える
喉いびきを治すための対処法として、舌や喉の筋肉を鍛えることがおすすめです。
気道はさまざまな骨や軟骨・靭帯・筋肉で形成されていますが、加齢によって舌や咽頭の筋力が低下したり、肥満などによって周囲から強く気道が圧迫されてしまうと、狭窄して喉いびきをかきやすくなります。
舌や喉の筋肉を鍛えることで気道の形状を維持できるようになるため、喉いびきの改善・予防が目指せます。
具体的には、下記のようなトレーニングがおすすめです。
- あいうべ体操:「あー」「いー」「うー」「べー」と口に形を順番に変えて動かす
- 舌の体操:舌を上下左右前後方向に動かす
あいうべ体操は、声を出しても出さなくても、口を「あー」「いー」「うー」「べー」の発音の形に動かし、これを繰り返し行うことで舌や顔面筋、咽頭部や喉頭部の筋肉を刺激でき、筋力の維持・向上を目指すことができる運動です。
また、舌を上下左右前後方向に動かすことで舌の筋力を維持・向上でき、喉いびきの原因となる舌根沈下を予防することができます。
CPAPやマウスピースなどの医療機器を使う
喉いびきを治すための対処法として、CPAPやマウスピースなどの医療機器を使うこともおすすめです。
CPAPやマウスピースなどの医療機器を装着することで、咽頭部や喉頭部における気道狭窄を予防することができ、それによって喉いびきの改善が目指せます。
CPAPを用いることで、呼吸する際(特に吸気時)に気道に陽圧がかかり、気道の閉塞を防ぐことができるため、喉いびきを改善させることができます。また、患者個々人の骨格に合わせたマウスピースを作製・装着することで、下顎を前方に固定できるため、舌根沈下による喉いびきの予防・改善に有用です。
実際に、どちらの治療法も睡眠時無呼吸症候群の診療ガイドラインで強く推奨されており、特にCPAP療法は中等度〜重度の睡眠時無呼吸症候群に対する治療法の第一選択となっています。
なお、これらの治療は行うためには、どちらも医療機関で睡眠時無呼吸症候群の診断・重症度判定に必要不可欠なPSG検査(ポリソムノグラフィ)と呼ばれる特殊な検査を実施する必要があるため、耳鼻咽頭科や呼吸器内科の受診が必要となります。
レーザー治療や手術を検討する
喉いびきを治すための対処法として、原因疾患によってはレーザー治療や手術を検討する必要もあります。
上記で紹介したような「喉の筋力トレーニング」や「CPAP・マウスピース」などの治療法は、可逆性のある閉塞が原因の場合には有効ですが、物理的に気道が閉塞して元に戻らないような状態には有効ではありません。
例えば、喉に巨大なアデノイドや扁桃肥大が形成された場合、これらが自然経過で縮小することは考えにくく、CPAPやマウスピースを導入するよりも、手術でアデノイドや扁桃肥大を切除する方が治療として適切です。
また、生まれつきの顔面や顎の骨格によって気道が狭くなりやすい人に対しても、CPAPやマウスピースでは骨格そのものを変えることは困難であり、自然に気道の狭窄が解除されることはないため、根治的な改善のためには額顔面形成術と呼ばれる手術を行うこともあります。
これらの手術の適応については医師の専門的な判断が必要となるため、まずは医療機関を受診し、いびきの原因を精査することが重要です。
鼻いびき・喉いびきが出る方の改善事例を紹介
鼻いびきや喉いびきは原因も多岐に渡り、その原因によって改善方法や改善の経過も大きく異なります。そこで、ここでは実際にあった鼻いびき・喉いびきが出る方の改善事例を3つ紹介します。
自身のいびきと似た経過であれば、いびきの改善のヒントにもなるため、ぜひ参考にしてください。
20代男性:市販薬で鼻いびきが改善した事例
20代男性のAさんはこれまで大きな病気もなく、日々健康に過ごしているサラリーマンですが、毎年春になると花粉症による鼻づまりを認め、年々増悪傾向でした。
例年通り花粉症に伴う鼻づまりに苦しんでいたところ、家族からは寝ている時に「ヒューヒュー」高いいびきが聞こえると指摘され、それとともに熟睡感が得られなくなったり、起床時の眠気を自覚するようになっていました。
放置していたところ、集中力の低下や日中の眠気によって仕事に支障をきたすようになったため、花粉症の改善のために市販の点鼻薬を購入したところ、比較的即効性のある効果が得られたそうです。
点鼻薬によって鼻汁の漏出が軽減し、鼻の通気性も顕著に改善した結果、その日を境に鼻いびきや起床時、日中の眠気も改善されたそうです。
市販の点鼻薬といえど、即効性のある効果が得られ、睡眠の質の向上や、仕事への集中力の向上など、多くのメリットを得られたため、もっと早くに治療すればよかったと感じたそうです。
30代男性:手術療法で改善した事例
30代男性のBさんはバリバリ仕事をこなす営業職で、日々多忙な毎日を過ごしていました。今までこれといった病気に罹患したことはありませんでしたが、以前からなんとなく鼻閉感を認めており、徐々に症状が増悪傾向でした。
同居する彼女から「夜いびきがうるさくて眠れない」と言われたことにショックを受け、鼻づまりによっていびきが起きていると考えたことから、鼻づまり解消のために市販の鼻腔拡張テープを購入しました。
しかし、鼻腔拡張テープ使用後も思ったような改善が得られず、むしろ症状がさらに悪化し、寝ている間に口呼吸が増えたせいか、起床時に口腔内の乾燥も目立つようになったそうです。
そこで、近隣の耳鼻咽喉科を受診して精査したところ、ただの鼻づまりではなく鼻中隔湾曲症を認めると診断され、症状改善のために手術を行うことになりました。
術後1週間程度経過したあたりから、これまで自覚していた鼻閉感が急速に改善し、明らかに鼻の通気性が向上したそうです。それと同時に、鼻いびきも改善したことで彼女の睡眠を守ることもできるようになり、もっと早くに医療機関を受診すればよかったと感じたそうです。
60代女性:ダイエットで改善した事例
60代女性のCさんは加齢とともに徐々に体重が増加傾向にあり、ここ数年で体重は10kg以上増加し、健康診断でも血圧や血糖値の値が高いと指摘されるようになっていました。
体重が70kgを超えたあたりから、夫からは「凄まじい大きな音のいびきをかくようになった」と指摘されるようになり、夜中に時折呼吸が止まっていることを心配されたそうです。
ネットで調べたところ、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと知り、医療機関を受診したところ、肥満によって睡眠時無呼吸症候群を発症している可能性が高く、それが血圧や血糖値にも影響していると言われたそうです。
そこで、普段の食事内容や運動習慣を見直し、減量に励んだところ、3ヶ月で10kg近くの減量に成功し、体重も60kg台に戻すことができました。その結果、いびきの音も軽減し、血圧や血糖値も以前より落ち着いたことから、普段の生活習慣がいかに睡眠や健康にとって重要か、再認識できたそうです。
【まとめ】いびきのタイプ別に原因や治療法を見つけよう
この記事では、喉いびきと鼻いびきの音の違いや原因、対処法について詳しく解説しました。
鼻腔の狭窄による鼻いびきと、咽頭部や喉頭部の狭窄によって生じる喉いびきでは鳴る音も異なり、その原因によって取るべき対処法も異なります。
しかし、どちらのいびきであっても長期間放置すれば、睡眠中に十分な酸素を取り込めなくなってしまい、身体は持続的な低酸素状態に陥ることで、高血圧や糖尿病、不整脈などの心血管疾患、脳血管障害の発症リスクが増大することが知られているため、早期に原因を特定し、原因に合った適切な対処法を選択することが重要です。
しかしながら、自身のいびきの危険度がわからず、つい放置してしまう方も少なくありません。
そこで、下記の記事では、自身のいびきの危険度を簡易的にセルフチェックできる方法について詳しく解説しているため、いびきを認める方はぜひご一読ください。
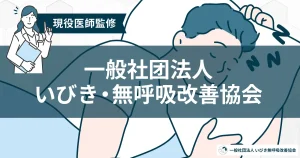
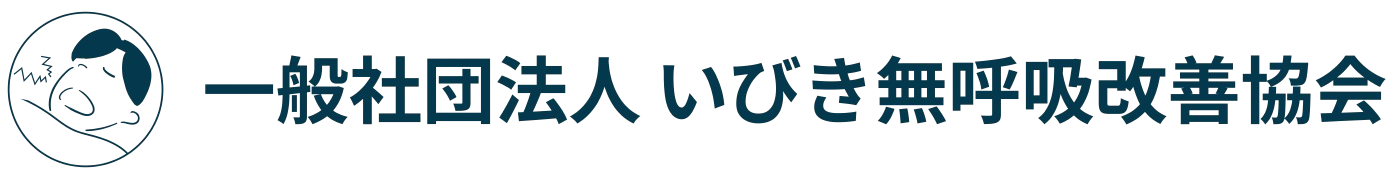
コメント