- 起きているのにいびきのような呼吸が出るのはどうして?
このような疑問や悩みをお持ちの方も少なくないでしょう。
いびきとは気道の狭窄によって睡眠中に生じる粘膜の振動音ですが、何らかの原因で気道が高度に狭窄すると、睡眠中でなく覚醒時の呼吸でも同様の振動音が生じる可能性があります。
放置すれば睡眠の質の低下やさまざまな健康被害のリスクが上がるため、注意が必要です。
この記事では、起きているのにいびきのような呼吸が出る原因や放置した場合のリスク、対処法など詳しく解説します。この記事を読むことで、起きている時に生じるいびきのような呼吸を改善でき、健康や睡眠を守ることができるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
起きているのにいびきのような呼吸が出るのはなぜ?原因とは?
そもそもいびきとは、何らかの原因によって気道が狭窄し、睡眠中の呼吸によって粘膜が振動することで生じる振動音です。
しかし、気道の狭窄が高度の場合、睡眠中でなくても粘膜が振動し、いびきのような呼吸が出る可能性があります。
その原因として、下記のような要因が挙げられます。
それぞれについて詳しく解説します。
鼻づまりやアレルギーによる通気障害
起きているのにいびきのような呼吸が出る原因の1つが、鼻づまりやアレルギーによる通気障害です。
ヒトは通常、口呼吸ではなく鼻呼吸が主であり、鼻腔内は鼻粘膜や軟骨・骨などの構造物によって複雑に形成されています。
何らかの疾患を発症してこれらの構造に変化が生じてしまうと、鼻腔は容易に狭窄し、そこを通過する空気が乱流を形成し、気道の粘膜を振動させる可能性があります。
例えば、感冒に伴う鼻詰まりやアレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、鼻茸、鼻中隔湾曲症などの耳鼻科疾患が主な原因です。
特に、感冒に伴う鼻詰まりやアレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎の場合、鼻粘膜の炎症に伴う浮腫によって鼻粘膜が肥厚するだけでなく、鼻粘膜の毛細血管の拡張に伴い大量の鼻汁を分泌するため、鼻汁による鼻腔の狭小化や閉塞の可能性もあります。
一方で、鼻茸や鼻中隔湾曲症が原因の場合は、粘膜の肥厚や鼻中隔の湾曲によって物理的に鼻腔を閉塞させ、自然な改善が見込めない可能性もあるため、注意が必要です。
喉や気道の形状・筋力低下
起きているのにいびきのような呼吸が出る場合、喉や気道の形状に変化をきたしていたり、咽頭部の筋力が低下している可能性があります。
上気道の咽頭や喉頭は、粘膜や筋肉、骨、軟骨など、さまざまな組織で形成されており、鼻腔と同様に何らかの原因でこれらの構造に変化が生じると、気道が狭窄し、起きているのにいびきのような呼吸が出る可能性があります。
例えば、咽頭部や喉頭部の粘膜にガンが生じた場合や喉頭蓋と呼ばれる軟骨が炎症によって腫脹した場合、もしくは加齢によって咽頭部や喉頭部の筋力が低下した場合など、正常な気道の解剖を維持することができず、いびきのような呼吸の原因となるため、注意が必要です。
また、気道を形成する筋肉、骨、軟骨などの組織は周囲の組織からの圧迫からも気道を守っていますが、例えば肥満などによって首周りの脂肪が増加すると、その重みによって気道が圧迫され、やはりいびきのような呼吸音の原因となります。
ぜんそく・慢性気管支炎など呼吸器疾患
起きているのにいびきのような呼吸が出る場合、ぜんそくや慢性気管支炎などの呼吸器疾患を発症している可能性があるため、注意が必要です。
咽頭部や喉頭部からさらに末梢には気管や気管支・肺胞と呼ばれる下気道が存在し、気管や気管支は周囲を靭帯や軟骨・筋肉・粘膜などによって囲まれて形成されています。
喘息は気管や気管支の粘膜で慢性的な炎症が生じ、ちょっとした刺激にも非常に過敏になってしまう病気です。
粘膜の炎症によって気道は狭窄し、さらに何らかの刺激によって気管支平滑筋の攣縮を招くことで、気管が高度に狭窄し、呼吸音が「ヒューヒュー」と笛のような音になってしまいます。
慢性気管支炎も病態は喘息とかなり類似していますが、喘息の原因がハウスダストなどのアレルギーによる炎症であるのに対し、慢性気管支炎では喫煙や大気汚染などの原因によって気管支に炎症が生じる病気です。
どちらの疾患も気道を狭窄させ、覚醒時においてもいびきのような呼吸をきたす可能性があります。
無呼吸症候群の覚醒時症状
起きているのにいびきのような呼吸が出る場合、睡眠時無呼吸症候群の覚醒時症状を発症している可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群とは、何らかの原因で気道が狭窄し、睡眠中に低呼吸(睡眠中、呼吸の気流が30%以上低下し、10秒以上持続する状態または、動脈血酸素飽和度がベースラインから3%以上低下するか、覚醒反応を伴う状態)、もしくは無呼吸(10秒以上、呼吸が完全に停止する状態)の頻度が増加することで十分な酸素を吸い込むことができなくなる病気です。
睡眠中は舌の筋肉が弛緩しやすく、特に仰臥位の場合は重力の影響によって舌が後方に落ち込みやすく、舌後方に位置する気道が狭窄します。
そのため、睡眠時にこそ無呼吸や低呼吸になりやすいわけですが、気道の狭窄があまりにも高度の場合、覚醒時に舌が弛緩していなくても、十分に気道の開通が得られず、いびきのような呼吸音が出る可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群は脳に十分な酸素が届かなくなることで、睡眠の質の低下やさまざまな健康被害のリスクが増加するため、早期発見・早期治療が重要です。
心疾患や神経疾患による影響
起きているのにいびきのような呼吸が出る場合、心疾患や神経疾患による影響によって正常な呼吸音が得られず、いびきのように聞こえている可能性があり、注意が必要です。
心疾患や神経疾患は、どちらも睡眠の有無に関わらず呼吸音や呼吸様式に影響を与えることが知られています。
例えば、何らかの原因で心不全になると心臓は血液をうまく全身に駆出することができず、肺にも血液が鬱滞することで肺が水浸しになります。
その結果、吸気時に空気が肺胞に到達する際、肺胞に溜まった水と空気がぶつかることで水泡音が聞こえることがあるのです。
さらに、心不全の急性期には喘息と似たような喘鳴が生じることもあり、これがいびきのように聞こえる可能性もあります。
また、脳梗塞やパーキンソン病など、何らかの神経疾患を発症すると、舌の筋肉がうまく機能しなくなり、寝ている状態でなくても舌根が沈下し、気道が狭窄する可能性があります。
どちらの病態であっても、起きているのにいびきのような呼吸が出る可能性があり、原因疾患によっては命に関わる可能性もあるため、注意が必要です。
起きているのにいびきのような呼吸を放置した場合のリスク
「起きているのにいびきのような呼吸を放置した場合、どのようなリスクがあるの?」
このような不安を抱える方も少なくないでしょう。
起きているのにいびきのような呼吸を認める場合、高度な気道狭窄や何らかの疾患を発症している可能性があります。
放置すれば、下記のようなリスクを伴うため、早期発見・早期対策に努めることが重要です。
それぞれのリスクについて解説します。
睡眠の質低下による日中の倦怠感
起きているのにいびきのような呼吸を放置した場合、睡眠の質低下による日中の倦怠感や眠気に襲われる可能性があり、注意が必要です。
起きているのにいびきのような呼吸を認める場合、それだけ気道が狭窄している可能性が高いため、睡眠時は舌が弛緩することでさらに大きないびきをかいている可能性や、低呼吸・無呼吸状態に陥っている可能性があります。
その結果、脳には十分な量の酸素が届かなくなってしまうため、睡眠時間を確保しても脳が十分に休むことができません。
さらに、高度な気道の狭窄によって吸気時に胸腔には過剰な陰圧がかかり、それが脳にも影響して睡眠の質が低下してしまうことが知られており、中途覚醒(睡眠途中で起きてしまうこと)が増加することも知られています。
これらの結果、睡眠の質は大幅に低下し、起床時の倦怠感や日中の眠気など生じる可能性があります。
我慢できないほどの日中の眠気が生じて、交通事故や転倒転落を引き起こすことで命の危険性が増加することも知られており、注意が必要です。
低酸素状態による健康リスク
起きているのにいびきのような呼吸を放置した場合、低酸素状態によってさまざまな健康リスクが高まる可能性があります。
いびきのような呼吸を認める場合、覚醒時であっても睡眠中であっても、気道が狭窄している可能性が高く、取り込める空気や酸素の量が低下している可能性が高いです。
この状態が長期間続くと、身体や脳は持続的な低酸素状態に見舞われ、そのストレスで交感神経系が持続活性化してしまうため、脈拍増加・血圧上昇・血糖値増加など、さまざまな生理機能の変化が生じます。
いびきの代表的な疾患である睡眠時無呼吸症候群の場合、長期的な交感神経系の活性化によって高血圧・糖尿病・心房細動・心不全・脳血管障害の発症リスクが有意に上昇することが知られています。
特に心房細動・心不全・脳血管障害は日常の身体活動に大きく制限がかかったり、最悪の場合は命に関わる可能性もある病気のため、注意が必要です。
病気の早期発見が遅れる危険性
起きているのにいびきのような呼吸を放置した場合、そのいびきの原因となっている何らかの病気の早期発見が遅れる危険性があります。
いびきのような呼吸音が聞こえる状態を危険視する人は少なく、多くの場合、初期には放置しがちな症状ですが、それは危険です。
起きているのにいびきのような呼吸を認める場合、先述したようにさまざまな原因疾患が考えられ、中には早期発見が予後に関わるような病気もあります。
特に、咽頭がんや喉頭がんなどの悪性腫瘍、喘息、心不全、脳血管障害、睡眠時無呼吸症候群などの病気は、どれも発見が遅れれば命に関わるような病気であり、いかに早期発見できるかが予後にとって重要です。
また、鼻中隔湾曲症や鼻茸などの耳鼻科疾患も、放置すればいびきが悪化し、結果として睡眠時無呼吸症候群を合併するリスクが高まるため、いびきの原因を特定するためにも、早期に医療機関を受診しましょう。
起きているのにいびきのような呼吸がある場合の対処法
起きているのにいびきのような呼吸がある場合、上記で示したように放置すればさまざまな健康被害・睡眠への悪影響をもたらすため、早期に対処する必要があります。
ここでは、具体的な対処法を4つ紹介します。
耳鼻咽喉科での検査
起きているのにいびきのような呼吸がある場合、まずは耳鼻咽喉科で検査を受けることがおすすめです。
いびきの原因はさまざまですが、多くの場合、鼻腔や咽頭・喉頭部など、上気道の狭窄が原因で生じているため、その領域の疾患を専門とする耳鼻咽喉科であれば適切な診断を受けられる可能性が高いです。
耳鼻咽喉科では、鼻腔ファイバーによる鼻腔内の観察・咽頭ファイバーによる咽頭部や喉頭部の観察・頭部CTやMRIによる画像検査など、さまざまな方法で上気道の狭窄の原因を解明します。
また、睡眠時無呼吸症候群の診断や重症度判定のためには、耳鼻咽喉科や呼吸器内科などで主に実施されている「PSG終夜(睡眠ポリグラフ検査(Polysomnography))検査」が必要不可欠です。
この検査では、被験者の脳波、眼球運動、心電図、筋電図、呼吸状態、いびき、血中酸素飽和度などを一晩中入院施設でモニタリングし、睡眠1時間あたりの無呼吸と低呼吸の合計回数であるAHI(Apnea Hypopnea Index)を測定します。
このように、さまざまな専門的な検査によっていびきの原因を正確に診断できるため、まずは耳鼻咽喉科の受診を検討しましょう。
アレルギーや鼻炎の治療
起きているのにいびきのような呼吸がある場合、アレルギーや鼻炎の治療を行うのもおすすめです。
アレルギーや鼻炎によって鼻腔や咽頭、気管などの粘膜では浮腫が生じやすく、また多量の鼻汁分泌が生じるため、気道が狭窄しやすくなって覚醒時や睡眠時のいびき様呼吸を招きます。
鼻炎に対しては一般的に点鼻薬や抗アレルギー剤の内服、喘息に対しては一般的に生活指導や吸入ステロイド薬の外用が主です。
一方で、これらの治療はあくまでアレルギーの原因であるアレルゲンが体内に侵入し、その際の過剰なアレルギー反応を抑制するための治療であり、アレルゲンに過剰に反応してしまう体質そのものを改善しているわけではありません。
そこで、近年ではアレルギー疾患に対する根治療法として、アレルゲンに体を慣れさせ、過剰な免疫反応が起こらないようにする「脱感作療法」も注目されています。
これらの治療によっていびきの改善が得られる可能性がある一方で、原因がこれらの疾患でない場合は無駄な治療となってしまうため、まずは原因疾患を特定することが重要です。
生活習慣の見直し
起きているのにいびきのような呼吸がある場合、生活習慣の見直しもおすすめです。
いびきのような呼吸を認める場合、多くの例で肥満が背景に隠れている可能性が高く、頚部に過剰に蓄積した脂肪によって気道が圧排され、通常の呼吸音もいびきのように聞こえてしまいます。
そのため、肥満予防のためにも普段から規則正しく、バランスの良い食事摂取を心がけ、暴飲暴食を控え、1週間に最低でも3日は1日30分以上の有酸素運動を心がけましょう。
また、過剰な飲酒や喫煙も起きているのにいびきのような呼吸を認める原因となるため、控えるべきです。
飲酒や喫煙は気道に炎症・浮腫をもたらし、気道を狭窄させます。
さらに、飲酒には筋弛緩作用があるため、舌根沈下を引き起こしいびきをかきやすくなります。
以上の理由からも、起きているのにいびきのような呼吸を認める方は、医療機関を受診する前にまずは自身の生活習慣を見直し、問題点があれば是正しましょう。
必要に応じた呼吸リハビリや器具の使用
起きているのにいびきのような呼吸がある場合、必要に応じて呼吸リハビリや器具の使用も検討しましょう。
いびきの原因となる病態に対して適切な呼吸リハビリや器具を用いることで、気道が開通していびきを改善できる可能性があります。
特に慢性気管支炎や喘息などの呼吸器疾患によって気道が狭窄し、イビキ様の呼吸音を認める場合、気道が狭くて呼気時に空気を排出しにくくなっているため、呼気時に口をすぼめて気道に圧をかけ、気道を広げるようにして息を吐く口すぼめ呼吸を行うことで、呼吸が楽になります。
また、睡眠時無呼吸症候群では吸気時に気道が狭窄し、空気の流入が低下、もしくは完全に閉塞してしまうことが問題となるため、「CPAP」と呼ばれる特殊な器具を用いて、呼吸の際に一定の陽圧を気道にかけることで気道の閉塞を防ぎます。
呼吸リハビリや器具の使用は、何より病態にあった適切な方法を選択することが重要であるため、まずは医師に相談してしっかりと治療計画を立てることが重要です。
実際にあった「起きているのにいびきのような呼吸」の体験談
起きているのにいびきのような呼吸を認める場合、その原因や改善方法は人によって千差万別です。
そこで、ここでは実際にあった「起きているのにいびきのような呼吸」の体験談を3つ紹介します。
40代男性:生活習慣の見直しで改善した事例
40代男性のAさんはここ数年仕事が多忙で、不規則な食事や睡眠、運動不足が続き、体重が急激に増加傾向でした。
体重の増加とともに、家族からは睡眠中のいびきを指摘され、起きている時もいびきのような呼吸を認めるようになったそうです。
それとともに、起床時の倦怠感や夜間の中途覚醒、日中の眠気など、睡眠の質の低下を自覚したため、近くのクリニックを受診したところ、肥満による気道狭窄の可能性を指摘されました。
そこで、医師から生活習慣の見直しを指示され、普段の食事内容や食習慣を見直し、夜間の暴飲暴食を控えたそうです。
また、休日は積極的に体を動かし、ウォーキングを継続したところ、半年で15kgの減量に成功し、体重減少とともにいびき症状も改善したそうです。
日中の眠気や起床時の倦怠感も改善し、日々の生活習慣がいかに睡眠や健康にとって重要か認識できたそうです。
20代女性:市販の薬で改善した事例
Bさんは特にこれまで大きな病気にかかったこともなく、健康な20代の女性ですが、春になると花粉症で例年鼻詰まりに悩まされていました。
特にその年の花粉症はひどく、鼻呼吸をすると強い鼻詰まりによって起きているのにいびきのような呼吸を認めるようになったそうです。
そこで、鼻詰まり解消のためにドラッグストアで市販の点鼻薬を購入し、使用したところ、比較的早期に鼻詰まり症状が改善しました。
鼻詰まり改善によって鼻の通気性は向上し、いびきのような呼吸音も無くなったそうです。
50代男性:CPAP療法で改善した事例
50代男性のCさんは以前から睡眠中のいびきを家族に指摘されていましたが、年々いびきの程度も悪化傾向であり、ついには起きている時にもいびきのような呼吸音が聞こえるようになったそうです。
それと同時に、夜間に途中で起きてしまったり、日中に激しい眠気に襲われて仕事が手につかなくなる日もあったため、近くの病院の睡眠外来を受診したそうです。
そこで、PSG検査など実施したところ、重度の睡眠時無呼吸症候群と診断され、CPAP療法を行うこととなりました。
最初はCPAPの駆動音やマスクのフィットに違和感がありうまく寝れませんでしたが、慣れてくると快眠を得られ、また夜間も熟睡できるようになり、日中の強い眠気も感じなくなったそうです。
【まとめ】起きているのにいびきのような呼吸が出る原因・対処法
この記事では、起きているのにいびきのような呼吸が出る原因・対処法、実際の体験談などについて紹介しました。
起きている時でもいびきのような呼吸音が出る場合は、何らかの耳鼻科疾患や睡眠時無呼吸症候群、喘息などの呼吸器疾患や心不全・脳血管障害など、さまざまな病気が隠れている可能性があります。
放置すれば命の危険性のある病気も含まれており、何よりも早期の原因検索と、その原因にあった適切な対処や治療を行うことが重要です。
一方で、自分のいびきやいびきのような呼吸音がどれだけ危険なものか、自分では判断できず放置してしまう方も少なくありません。
そこで、下記の記事では自身のいびきの危険度をセルフチェックできる方法について詳しく解説しているため、ぜひこれを機にご一読ください。
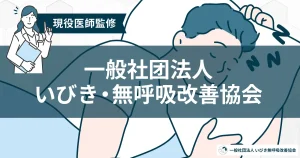
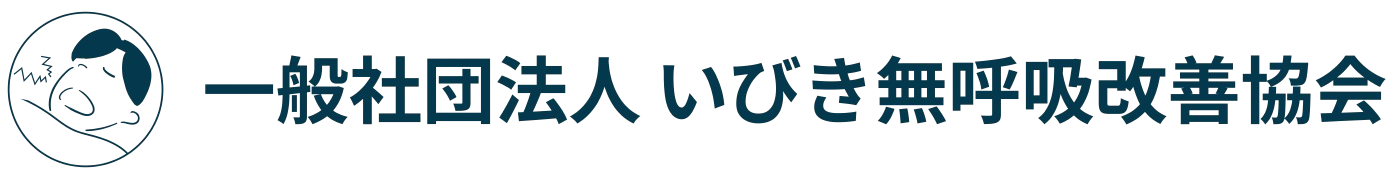
コメント