- 口を閉じてるのにいびきをかくのはなぜ?
- 口を閉じてるのにかくいびきの対策は?
このような疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
いびきとは、呼吸によって流入する空気が狭くなった気道を通過する際の振動音であり、口を閉じていても喉の奥や鼻腔が狭い場合はいびきをかく可能性があります。
この記事では、口を閉じてるのにいびきをかく原因や実際の体験談、対策法について詳しく解説します。
この記事を読むことで口を閉じてるのにかくいびきに対して早期に予防・対策でき、より質の高い睡眠を得ることができるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
口を閉じてるのにいびきをかくのはなぜ?原因とは?
いびきは睡眠中の呼吸によって空気が気道を通過する際、気道が狭いことで鳴る気道粘膜の振動音です。そのため、たとえ口が閉じていても、鼻呼吸で鼻腔が狭い場合や、喉の奥の気道が狭い場合はいびきをかきます。
具体的に、口閉じてるのにいびきをかくのは下記のようなケースです。
それぞれについて詳しく解説します。
鼻づまりや鼻中隔湾曲などの鼻のトラブル
鼻づまりや鼻中隔湾曲などの鼻のトラブルを認める場合、口を閉じてるのにいびきをかく可能性があります。
本来、ヒトは睡眠中は口呼吸よりも鼻呼吸を行う生き物であり、鼻汁などによって通過する空気が適切に加湿加温され、また空気中の塵なども粘膜で回収されるため、より清潔で気道に優しい空気を吸い込むことができるのです。
一方で、口呼吸を行う場合は乾燥した汚い空気をそのまま吸い込んでしまうため、気道の乾燥・炎症の原因となります。
しかし、鼻炎による鼻づまりや、鼻腔を形成する骨が湾曲する鼻中隔湾曲、鼻腔内にポリープが形成される鼻茸、鼻粘膜の慢性的な肥厚を伴う肥厚性鼻炎などを発症することによって鼻腔が狭小化すると、鼻呼吸の際に空気が通過する気道が狭くなっていることで、いびきが生じる可能性が高まります。
また、狭窄が高度になると鼻呼吸では息苦しく、口呼吸の割合が増加し、さらに気道の炎症を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。
舌の落ち込み・舌根沈下
舌の落ち込み・舌根沈下を認める場合、口を閉じてるのにいびきをかく可能性があります。
口は閉じていても、口腔内の舌が弛緩してしまうと舌は後方に落ち込んでいき、そのさらに後方に位置する気道が舌に圧迫されることで狭窄してしまうのです。
舌が落ち込む、いわゆる舌根沈下を引き起こす要因としては、下記のような要因が挙げられます。
- 睡眠薬の内服:筋弛緩作用によって舌が弛緩し、後方の気道に落ち込んでしまう
- 就寝前のアルコール摂取:筋弛緩作用によって舌が弛緩し、後方の気道に落ち込んでしまう
- 過剰な疲労;疲労によって全身の筋肉が弛緩しやすくなり、後方の気道に落ち込んでしまう
- 高度な肥満:舌に脂肪が沈着して、気道がより狭窄しやすくなる
- 加齢による舌の筋肉の衰え:加齢によって舌の筋肉が萎縮し、後方の気道に落ち込んでしまう
仮に口を閉じていても、鼻腔から流入する空気は舌後方の気道を通過するため、舌根沈下によっていびきが生じる可能性があり、注意が必要です。
肥満や筋力低下による気道の狭まり
肥満や筋力低下による気道の狭まりも、口閉じてるのにいびきをかく原因の1つです。
気道は鼻腔や口腔、咽頭部、喉頭部を形成するさまざまな組織、筋肉、軟骨、骨などによって構成されており、その周囲には脂肪が沈着しています。
肥満によって首まわりの脂肪沈着が高度になると、外側から気道が圧迫されることで気道が狭小化するため、いびきの原因となります。
また、加齢によって気道周囲の筋組織の筋力が低下すると、脂肪による圧迫をより受けやすくなるため、いびきをかきやすく、注意が必要です。
特に肥満はいびきの最大のリスクであり、肥満度を表す指数であるBMI(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))が高ければ高いほど、いびきのリスクが上昇することが知られています。
BMIが25kg/m2以上の方は特にいびきのリスクが高まることが知られており、BMIは身長と体重だけで簡単に計算できるため、ぜひ一度セルフチェックしてみると良いでしょう。
睡眠時無呼吸症候群
口を閉じているのにいびきをかいてしまう場合、睡眠時無呼吸症候群を発症している可能性があるため、注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群とは、何らかの原因で気道が狭窄することで睡眠中の低呼吸(10秒以上の気流低下が30%以上持続し、動脈血酸素飽和度がベースラインから3%以上低下した場合、もしくは覚醒反応を伴う場合)、もしくは無呼吸(10秒以上の呼吸停止)の割合が増加する病気です。
睡眠時無呼吸症候群を発症するといびきのみならず、睡眠の質の低下や夜間の中途覚醒増加、日中の激しい眠気など、さまざまな症状をきたし、日常生活に大きな影響を及ぼします。
また、長期的に睡眠時無呼吸症候群を放置すると、身体が持続的な低酸素状態に陥り、そのストレスによって高血圧や糖尿病・脳血管障害や心疾患の発症リスクが増大することが知られており、早期発見・早期対策が肝要な病気です。
口を閉じているのにいびきが出る方の体験談
ここでは、口を閉じているのにいびきが出る方の体験談を3つ紹介します。
それぞれのケースで置かれている状況や背景、いびきの原因や改善方法など異なるため、ぜひ自身の状況と照らし合わせながらご一読ください。
10代女性:鼻中隔湾曲症が原因となったケース
10代のAさんは大学1年生で、部活動と学業両方に励む至って健康な女性です。元々小児アレルギーやアレルギー性鼻炎を既往に持ち、風邪を引くと必ず鼻つまりが起きる体質でした。
以前から睡眠中の鼻息で音が鳴っていると家族に指摘されていましたが、年々その音が酷くなっているとの指摘を受け、自身でも時折そのいびきの音で夜中に起きてしまうようになったため、近隣の耳鼻科を受診しました。
耳鼻科ではいびきの原因として鼻腔が狭くなっている可能性が疑われ、スコープによる鼻腔の観察やレントゲン撮影など実施したところ、鼻粘膜の肥厚は軽度しか認めませんでしたが、鼻中隔が激しく湾曲しており、鼻中隔湾曲症の診断に至りました。
精査した結果、根本的な治療には手術が必要であるとの診断に至り、待機的に鼻中隔矯正術が実施されました。
結果として、本人も術前との違いを自覚できるほど鼻の通気性の改善を認め、家族からも鼻息や鼻いびきが聞こえなくなったと言われたそうです。
夜中に途中覚醒することもなくなり、起床時のスッキリ感も向上したため、いびきをきっかけに鼻中隔湾曲症を発見・治療できてよかったと感じられているようです。
30代男性:生活習慣の乱れが原因となったケース
30代男性のBさんは、バリバリの営業マンで会社員として日々多忙な時間を過ごしていました。夜遅くまで仕事の予定で埋まっており、その後に会社の同僚やお客さんと会食する機会も多く、就寝直前まで暴飲暴食したり、過剰にアルコール摂取してそのまま寝てしまう夜も少なくないような状況だったそうです。
ある日、同居する妻から「飲酒した日の夜は必ずいびきがうるさく、迷惑」と指摘され、初めていびきを自覚しました。連日そのような日を繰り返しているうちに、夜寝ているにも関わらず朝の目覚めが悪く、倦怠感や日中の激しい眠気で仕事が手につかなくなるようになったため、異変を感じて近隣の病院を受診しました。
医師に症状や生活習慣を伝えたところ、就寝直前の飲酒や喫煙によって気道が浮腫み、睡眠中に十分な酸素を摂取できていない可能性があると指摘されました。
そこで、まずは生活習慣の改善を指導され、極力夜遅くまで飲酒や喫煙は控え、飲酒するにしても少量に留めるように注意したところ、妻からもいびきが改善したと褒められたそうです。いびきの改善とともにスッキリ眠れるようになり、朝の倦怠感や日中の眠気も改善されました。
まさか普段の生活習慣がここまでいびきや睡眠の質に影響すると考えていなかったため、これを機に知ることができてよかったと感じたそうです。
50代男性:肥満によって睡眠時無呼吸症候群を発症したケース
50代男性のCさんは20〜30代の頃は比較的スリムな体型でしたが、加齢とともに徐々に太りやすくなっていき、50代に入ってからは特に生活習慣を変えたわけでもないのに、体重が2年で10kg以上増加してしまいました。
またそれとともに、夜中に途中で覚醒する機会も増え、朝起きた時の倦怠感や日中の激しい眠気に襲われる機会も増えたそうです。
ネットで検索したところ、肥満に伴う睡眠時無呼吸症候群の可能性があるとのことで、スマホで就寝中のいびきを録音したところ、自分でも驚くような大きな音のいびきをかいており、驚いたそうです。
すぐに近隣の呼吸器内科を受診したところ、専門の医療機関で詳しい検査が必要と言われ、紹介先の病院でポリソムノグラフィ検査を実施したところ、重症の睡眠時無呼吸症候群の診断に至りました。
医師からは肥満解消のための生活習慣の是正と、CPAP療法を指示され、CPAP装着したところ、朝の倦怠感や日中の眠気は著明に改善を認めたそうです。
放置すれば命の危険性もあったと医師から言われたため、大事に至る前に自身で検索して早期に発見できたことに安堵したそうです。
口閉じてるのにいびきが出るときの対処法・予防策
ここまで、口を閉じているのにいびきをかく原因や実際の体験談について解説しましたが、いびきは放置すると睡眠の質の低下や、それに伴う日中の生活への影響、さらに長期的にはさまざまな健康被害をもたらす可能性もあります。
そこで、事前の予防や早期対策が肝要であり、具体的には下記の3つの方法がおすすめです。
それぞれについて詳しく解説します。
寝姿勢・枕の高さを見直す
口を閉じているのにいびきをかく場合、就寝環境や寝具の見直しが重要です。自身の生活習慣や体型、骨格などの問題以外にも、就寝環境や使用している寝具はいびきの発症に大きく関わるためです。
例えば、睡眠中の姿勢が仰向けの場合、重力に伴って舌が後方の気道に落ち込みやすく、気道が狭窄しやすくなるため、いびきをかきやすいことが知られています。そのため、睡眠中は横向きで寝ることでいびきの改善が期待できます。
さらに、柔らかすぎるマットレスの使用や高すぎる枕の使用は頭部と体幹の高低差を生み、頚部の過剰な屈曲を招くことでいびきのリスクを増大させるため、注意が必要です。
ある程度反発感のあるマットレスの使用や、どんなに高くても7cm以上の高さの枕の使用は控えるべきです。
他にも、寝室が乾燥していると気道に炎症を起こしやすく、炎症によって気道が浮腫むといびきをかきやすくなるため、寝室の湿度にも注意する必要があります。
鼻呼吸の改善に役立つグッズ・ストレッチ
口を閉じているのにいびきをかく場合、鼻呼吸の改善に役立つグッズの使用やストレッチがおすすめです。
先述したように、口を閉じているのにいびきをかく場合、何らかの原因で鼻腔が狭窄している可能性が高く、グッズを用いて鼻腔を拡張させることで症状が改善される可能性があります。
鼻腔拡張テープ、ノーズクリップ、ナステントなど、比較的安価に市販で購入できるグッズも多いため、ぜひチェックしてみるとよいでしょう。
一方で、いびきの原因が鼻腔の狭窄ではない場合、思ったような効果が得られない可能性もあるため注意が必要です。
また、口の表情筋や舌を積極的に動かす「あいうべ体操」は、「あ~」「い~」「う~」「べ~」と口を動かすことで口腔表情筋が鍛えられ、口が自然と開くのを予防することで鼻呼吸の促進につながります。
どちらも比較的容易に実践可能で、即効性も期待できるため、口を閉じているのにいびきをかく人はぜひ一度試してみると良いでしょう。
睡眠外来での検査と治療法
口を閉じているのにいびきをかき、上記で紹介したようなセルフケアでも改善できない場合は、睡眠外来で検査を行い、症状に見合った適切な治療法を実践することが重要です。
口を閉じているのにいびきをかく場合、鼻中隔湾曲症や鼻炎などの耳鼻科疾患、もしくは睡眠時無呼吸症候群などを発症している可能性あり、症状の程度次第ですがセルフケアが困難であることも多いため、医療機関での精査が重要です。
睡眠外来ではいびきの原因の解明や、いびきの程度を調べる検査として「PSG(ポリソムノグラフィー)検査」を実施し、病状を把握します。
何らかの耳鼻科疾患を認める場合は耳鼻科的な治療を、睡眠時無呼吸症候群であれば程度に合わせて減量、装具療法や体位療法、CPAP療法などが選択されます。
原因を見誤って不適切な治療法を選択してしまうと、症状が一向に改善されないばかりか、むしろ増悪していく可能性もあるため、セルフケア困難な場合は必ず医療機関の受診を検討しましょう。
口を閉じていてもいびきが出る場合は病気のサイン?
口を閉じていてもいびきが出る場合、何らかの病気の可能性があります。また、いびきを放置すればそれによって新たな病気のリスクが高まる可能性もあるため、早期発見・早期治療が重要です。
ここでは、口を閉じていても認めるいびきへの対応としてよくある疑問を2つ紹介します。
こんな症状があればすぐに医療機関へ
口を閉じていてもいびきが出る場合、ただのいびきとたかを括って、医療機関への受診に気が乗らない方も多いでしょう。また、自身のいびきの程度が医療機関に受診すべき程度なのか自信を持てず、そのまま放置してしまう方も少なくありません。
しかし、程度の重いいびきを放置すると睡眠の質が低下したり、身体が持続的な低酸素に陥り、さまざまな健康被害を及ぼす可能性が上がるため、注意が必要です。
そこで、下記のような症状を認める方はすぐに医療機関に受診しましょう。
- 睡眠中、明らかに無呼吸の時間がある
- 朝起きた時に頭痛や倦怠感を毎朝のように認める
- 日中に過度な眠気に襲われ仕事や学業が手につかない
- ここ最近、著しく集中力が低下した
- 検診で高血圧や糖尿病などを指摘されるようになった
上記のような症状を認める場合、日中の過度な眠気によって交通事故や転倒・転落を引き起こす可能性もあり、また身体が持続的な低酸素状態に陥るとそのストレスで高血圧や糖尿病、さらには心血管疾患や脳卒中の発症リスクも増大するため、命の危険性を伴います。
上記症状を認める場合は、早急に医療機関を受診して精査しましょう。
受診すべき診療科はどこ?
上記のような症状を認めた場合、「病院には行くけど、何科に受診さればいいの?」と疑問を抱く方も少なくないでしょう。
結論から言えば、まずは近隣の耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。
いびきの原因はさまざまですが、どのような原因であっても気道を狭窄させていることに変わりありません。そのため、気道周囲の組織を専門とする耳鼻咽喉科であれば、より的確な診断・治療を実施できる可能性が高いです。
ただし、睡眠時無呼吸症候群を発症している場合、診断のために必要な検査であるPSG検査は入院が必要なため、一般的な耳鼻咽頭科のクリニックでは対応できない可能性が高いです。そのため、大きな病院の耳鼻咽頭科や呼吸器内科、睡眠外来などを紹介される可能性もあります。
初診時点では原因は誰にもわからないため、まずは耳鼻咽頭科を受診し、ある程度診断がついたら、その診断に特化した診療科でさらに専門的な治療を受けるのが治療の流れとして最適です。
【まとめ】口を閉じていてもいびきが出る原因を知って正しく対処しよう
この記事では、口を閉じていてもいびきが出る場合の原因や対処法、実際の体験談などについて詳しく解説しました。
いびきは開いた口から出るイメージが強いですが、実は口を閉じていてもいびきが出る可能性があり、多くの場合は何らかの耳鼻科疾患を発症している可能性があります。
また、耳鼻科疾患以外にも生活習慣の乱れ、不適切な寝具の使用、睡眠時無呼吸症候群の発症など、原因は多岐に渡ります。
原因に関わらず、放置すれば、通常のいびき同様に日中の眠気や頭痛・倦怠感などさまざまな症状をきたす原因となるため、注意が必要です。
さらに、長期的には高血圧や糖尿病、不整脈などの心疾患や脳血管障害などの発症リスクを増大させる可能性もあるため、気になる方は医療機関を受診して精査しましょう。
自身のいびきの危険度がわからない、という方は、下記の記事でいびきの危険度のセルフチェック方法を詳しく解説しているため、ぜひご一読ください。
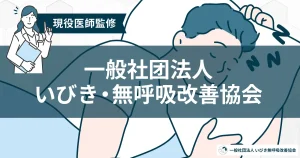
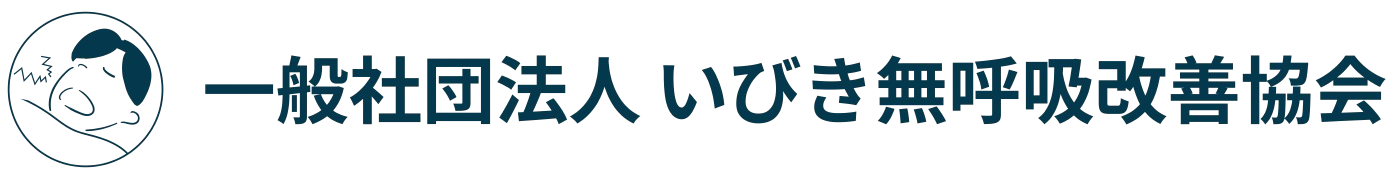
コメント