- 最近口臭を指摘されたけど、いびきが原因って本当?
- いびきが原因の口臭の対処法は?
このような疑問やお悩みをお持ちの方も少なくないでしょう。
実はいびきと口臭には密接な関連性があり、いびきをかく方は口臭が強くなる可能性があるため、注意が必要です。
一方で、両者に密接な関連性があるからこそ、いびきを改善させることで、同時に口臭を改善させられる可能性もあります。
この記事では、いびきで口臭が強くなる原因や同時に改善する方法、実際の体験談を詳しく解説します。この記事を読むことでいびきと口臭を同時に改善でき、睡眠や口臭に関わるお悩みを解消できるようになるため、ぜひご一読ください。

2009年に群馬大学医学部医学科を卒業以降、関東圏の循環器病院で勤務。現在は、横浜市神奈川区にある「Myクリニック本多内科医院」の院長を務める。担当は内科・循環器内科。いびき、睡眠時無呼吸症候群のプロとして日々臨床に取り組む。累計、300人以上のいびき、睡眠時無呼吸症候群の患者を担当。
一般社団法人 いびき無呼吸改善協会
いびきで口臭が強くなる原因と関係性
冒頭でも述べたように、いびきと口臭には密接な関連性が認められており、いびきをかく人は口臭が強くなってしまう可能性が高まります。
いびきで口臭が強くなる原因は主に下記の3つであり、それぞれ個別に関与するわけではなく、複合的に関与して口臭の悪化につながるため、注意が必要です。
それぞれについて詳しく解説します。
口呼吸による口内の乾燥
いびきで口臭が強くなる原因として、口呼吸による口内の乾燥が挙げられます。
ヒトは通常、睡眠中は鼻呼吸をすることで、気道に流入する空気が鼻粘膜や鼻汁によって加温加湿され、より気道に優しい空気を吸い込めるようにしているのです。
しかし、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎・鼻中隔湾曲症などによって鼻粘膜が腫脹したり、鼻汁が増加して鼻呼吸が困難になると、睡眠中に口呼吸の割合が増加してしまいます。
口呼吸の場合、吸気時に下顎が後下方に移動するため、後方に位置する気道が狭窄しやすくなり、いびきをかきやすくなる上に、気道に流入する空気が鼻呼吸と異なり加湿・加温されないため、口腔内が乾燥してしまいます。
その結果、本来口腔内の細菌を洗い流す働きを持つ唾液の分泌量が低下し、細菌が増加することで、細菌が口腔内の食残(食べ残し)を分解する過程で発生するメチルメルカプタンや硫化水素・ジメチルサルファイドなどの異臭ガスがより多く発生し、口臭が強くなるのです。
喉や舌の振動による炎症
いびきで口臭が強くなる原因として、喉や舌の振動による炎症も挙げられます。
「いびき=気道の粘膜の振動音」であり、何らかの原因で狭くなった気道に、呼吸によって空気が流入した際に喉や舌の粘膜が強く振動することで生じる振動音をいびきとして認識しています。そのため、より大きいいびきをかいている人ほど、喉や舌の粘膜では強く振動が生じているのです。
一方で、そのような状態が長く続くと、粘膜細胞には炎症が生じ、その反応によって局部の血管拡張や組織液の貯留が生じ、より細菌が繁殖しやすい土壌を形成してしまいます。
その結果、口腔内の常在菌が多く炎症部位に溜まってしまい、口の中の食べかすや食残のタンパク質を分解することで異臭ガスが発生し、口臭が強くなります。
また、いびきの原因がそもそも副鼻腔炎や扁桃腺炎、慢性鼻炎など、何らかの細菌感染によって引き起こされている場合、喉や舌の振動による炎症が生じる前からすでに気道に炎症が生じているため、より口臭が強くなる可能性もあり、注意が必要です。
アルコールや食生活の影響
いびきで口臭が強くなる原因として、アルコールや食生活の影響も挙げられます。
過剰なアルコール摂取や食生活の乱れは、気道狭窄に伴ういびきを引き起こしやすく、また下記のようなメカニズムで口臭を強くさせる可能性があります。
- 肥満やアルコールの筋弛緩作用による気道狭窄で口呼吸が増加
- 食残の増加
- ニオイの元となる成分の摂取
- 逆流性食道炎の発症
過剰なアルコール摂取や食生活の乱れは、肥満やアルコールの筋弛緩作用による気道狭窄によっていびきが生じやすくなり、吸い込める空気量が減少するため、より多くの空気を吸うために口呼吸の割合が増加して口臭が強くなるのです。
また、食生活の乱れは口腔内の食残が増加したり、ニラやネギ・アルコールなどの過剰摂取はニオイの元となる成分が吸収されて最終的に肺から排泄されるため、呼気と共に体外に排出されることで口臭が悪化します。
さらに、過剰なアルコール摂取や食生活の乱れは逆流性食道炎(胃の内容物が食道に逆流してしまう病気)を引き起こし、胃液が食道に逆流することによって口臭が強くなる可能性があります。
いびきと口臭を同時に改善する方法
いびきは一緒に暮らす家族やパートナーの睡眠を妨害し、自身の睡眠の質の低下やさまざまな健康被害をもたらすため、早期に改善すべきです。また、いびきによって口臭が強くなれば周囲の人から不快感を抱かれてしまいます。
いびきと口臭を同時に改善するためには、いびきと口臭の共通の原因(口呼吸・乾燥・生活習慣) にアプローチする必要があり、具体的な方法を4つ紹介します。
生活習慣や睡眠環境を見直しする
いびきと口臭を同時に改善するためには、生活習慣や睡眠環境の見直しが重要です。生活習慣や睡眠環境はいびきの発症に強く影響し、同時に口臭が強くなる原因にもなるため、これらを見直すことで両方の改善が見込めます。
暴飲暴食や乱れた食習慣、過剰なアルコール摂取や喫煙、睡眠薬の常用など、どれも気道の狭窄を招く原因となり、いびきや口臭の原因にもなるため、控えるべきです。
また、高すぎる枕や柔らかすぎるマットレスの使用も頚部の過剰な屈曲を招き、気道が狭くなることでいびきをかきやすくなるため、自身の身体にフィットした寝具を使用することが重要です。結果的に、多量の空気を吸い込むために口呼吸が増えてしまうため、口腔内の乾燥、さらには口臭の悪化を招きます。
他にも、寝室の湿度や温度もいびきや口臭対策には重要であり、寒冷・乾燥していると気道に炎症が起こりやすく、いびきや口臭の原因となるため、エアコンや加湿器を利用して適切な湿度や温度を保つことが重要です。
口腔ケアを徹底する
いびきと口臭を同時に改善するためには、口腔ケアを徹底することも重要です。口腔ケアを怠ると、食事摂取後の食べ残しや歯の汚れが蓄積し、そこに炎症や細菌の繁殖が起こりやすくなります。
その結果、歯周病や舌苔などの歯科疾患を発症し、細菌が繁殖すれば口腔内の炎症や細菌による異臭ガスの発生が生じることで、いびきや口臭が悪化しやすくなります。
そのため、下記のような口腔ケアを徹底することが重要です。
- 歯磨き
- 専用ブラシでの舌磨き
- デンタルフロス
- マウスウォッシュ
- 寝る前の水分補給
これらの口腔ケアを徹底することで、食べ残しや歯の汚れの蓄積を予防し、炎症や細菌の繁殖を予防することができます。
また、これらの口腔ケアは頻度や力の入れ方も重要で、あまりにも高頻度に行ったり、過剰な力を入れて炎症を起こしてしまうと、むしろ口腔内の炎症や細菌の繁殖を起こしやすくなってしまうため、1日1〜2回に留め、軽く優しく、小刻みに口腔ケアを行うようにしましょう。
いびき対策グッズを使う
いびきと口臭を同時に改善するためには、いびき対策グッズの使用もおすすめです。先述したように、いびき=気道が狭窄している状態であり、吸気時に吸い込める空気量が減少しているため、より多くの空気を吸い込むために口呼吸の頻度が増加します。
その結果、いびきの増悪や、口腔内の乾燥に伴う口臭の悪化が同時に引き起こるため、市販グッズでいびき対策を行うことでいびきと口臭の同時改善が見込めます。
おすすめのいびき対策グッズは主に下記のようなグッズです。
- 口閉じテープ
- 鼻腔拡張テープ
- ノーズクリップ
- マウスピース
- 抱き枕
口閉じテープは口呼吸の割合を減少させ、鼻腔拡張テープやノーズクリップは鼻腔を拡張させることで鼻呼吸を促進させ、やはり口呼吸の割合を減少させます。
また、マウスピースを装着することによって下顎を前方に固定できるため、口呼吸の吸気時における下顎の後下方への移動を抑制でき、いびきの改善に寄与します。
さらに、仰向け寝は舌根沈下が起こりやすく、いびきが最も出やすい体位ですが、抱き枕を使うことで自然と横向き寝になるため、舌根沈下が起こりにくくなり、いびきや口臭の改善に有用です。
医療機関で相談する
いびきと口臭を同時に改善するためには、医療機関で相談することもおすすめです。
いびきが起きる原因は副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎・鼻中隔湾曲症などの耳鼻科疾患、扁桃肥大やアデノイド、舌が大きい、顎が小さい、肥満、生活習慣の乱れなど多岐に渡り、その原因によって対処法も異なります。
もし原因に合った対処法を実践できない場合、いびきは改善することができず、その結果、口呼吸が増えてしまえば口腔内が乾燥し、口臭の悪化につながります。そのため、まずは近隣の医療機関に相談し、いびきの原因を精査することが重要です。
いびきや口臭の主な原因は鼻腔・咽頭部・喉頭部における何らかの異常や病変の可能性が高いため、まずは耳鼻咽喉科に受診すると良いでしょう。
特に、鼻中隔湾曲症やアデノイド、睡眠時無呼吸症候群などの疾患を認める場合、セルフケアでの改善は困難であり、医療機関での特殊な治療や手術が必要となることも少なくないため、セルフケアでも改善困難な場合は早期に医療機関を受診するようにしましょう。
実際に「いびき・口臭」で悩んでいた方の体験談と改善事例
いびきやそれに伴う口臭は原因によって改善方法もさまざまであり、人によって原因や改善に至るまでの経過も異なります。そこで、ここでは実際に「いびき・口臭」で悩んでいた方の体験談と改善事例を3つ紹介します。
それぞれのエピソードを知ることで、自身のいびき・口臭改善の糸口になる可能性もあるため、ぜひご一読ください。
50代男性:生活習慣の見直しで改善した事例
50代男性のAさんは多忙なサラリーマンで、仕事が夜遅くまでかかってしまい深夜にドカ食いしてしまったり、付き合いで飲み歩くことも少なくありませんでした。50代に入ってからもほとんど毎日のようにそのような食生活を続けていたところ、体重が一気に10kgほど増加し、それと同時に大きないびきをかくようになったそうです。
さらに、いびきの悪化とともに自分でも自覚できるほど口臭が悪化し、妻は「旦那の口臭で部屋が臭い」と友人に相談するほどだったそうです。
これにショックを受けたAさんは、できる限り規則正しい食事摂取を意識し、深夜までの飲酒を控え、朝晩の口腔ケアも重点的に行い、いびきや口臭改善のために生活習慣の見直しを実践しました。
その結果、1ヶ月後には口臭がかなり軽減し、2ヶ月経過時には体重が8kgほど低下したことでいびきもかなり改善したそうです。妻からも「ようやく隣で安眠できるようになった」と声をかけられ、Aさん自身も妻との生活に自信を取り戻すことができたそうです。
20代男性:手術療法で改善した事例
20代男性のBさんは部活動に励む学生で、日々規則正しい食生活を送り、飲酒も月に1〜2回付き合いで飲む程度でした。しかし、以前から認めていた鼻閉感が徐々に悪化傾向であり、それとともに同棲する彼女からは「夜いびきがうるさくて眠れない」と指摘されるようになったそうです。
さらに、いびきをかくようになってから、朝起きてからの口腔内の乾燥や口臭の悪化を自覚するようになり、人前で話すのが恥ずかしいと感じるようになったそうです。
ネットで調べたところ、鼻詰まりがいびきや口臭の原因となることを知り、市販の鼻腔拡張テープを購入しましたが、一向にいびきや口臭は改善せず、むしろ悪化傾向であったため、最終的に近隣の耳鼻咽頭科を受診しました。
耳鼻咽頭科では問診や診察、CT検査が実施され、最終的にいびきや口臭の原因は鼻中隔湾曲症と診断され、1ヶ月後に手術を行う運びとなりました。術後2週間でいびきは著明に改善を認め、それと同時に以前までの口臭も解消されたため、人前で堂々と話せるようになったそうです。
40代女性:市販のいびき対策グッズで改善した事例
40代女性のCさんは専業主婦であり、規則正しい生活習慣を送ってはいるものの、毎日夜は飲酒し、40代に入ってからは体重も増加傾向でした。
寝室は乾燥しやすい環境にあり、以前から起床時の口渇感を認めていましたが、体重増加とともにその症状は悪化し、夫や子供からは「いびきがうるさく、口も臭い」と指摘されたことに大変ショックを受けたそうです。
ネットで調べたところ、口臭は寝室の乾燥が原因であることを知り、早速加湿器を購入したところ、口臭や口渇感は若干の改善を認めたものの、いびきは改善しませんでした。
そこで、さらに調べたところ、抱き枕を使って横向き寝することで、いびきを改善できると知り、早速抱き枕を購入して実践したところ、いびきの改善を認めました。
それと同時に、起床時の口渇感・口臭も改善を認め、ようやく家族とも安心して会話できるようになったそうです。その後、体重増加もいびきの原因となると知り、ダイエットを行ったところ、仰向け寝でもいびきはかかなくなったそうですが、加湿器は現在でも使用して寝ているそうです。
いびきと口臭がひどい場合は病気のサイン?
いびきと口臭がひどい場合、ほとんどの場合は生活習慣の改善や就寝環境の見直しなどのセルフケアで改善を目指せます。しかし、中には何らかの病気を発症し、それによっていびきや、いびきに伴う口臭が引き起こされている可能性があるため、注意が必要です。
そこで、ここではいびきと口臭の原因となる病気を3つ紹介します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性
いびきと口臭がひどい場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症している可能性があり、注意が必要です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、何らかの原因で気道が狭窄し、睡眠中に換気量が50%以上低下したり、10秒以上完全に呼吸が停止してしまう病気です。
睡眠中に脳は十分な酸素を得ることができず、睡眠時間を確保していたとしても、睡眠の質の低下によって起床時の倦怠感や日中の激しい眠気、さらには口呼吸による口臭の悪化など、さまざまな症状が出現します。
さらに、この病気の怖いところは長期間放置することで身体が持続的な低酸素状態に陥ることです。
持続的な低酸素状態は身体にとって大きなストレスとなり、交感神経が刺激されることで高血圧・糖尿病・心不全や心房細動などの心血管疾患・脳血管障害などの重篤な疾患の発症リスクを増大させることが知られています。改善のためには医療機関での専門的な検査・治療が必要であり、疑わしい場合は早期に医療機関を受診しましょう。
慢性鼻炎や副鼻腔炎の可能性
いびきと口臭がひどい場合、慢性鼻炎や副鼻腔炎を発症している可能性があり、注意が必要です。慢性鼻炎や副鼻腔炎を発症すると鼻粘膜の腫脹や鼻汁の増加に伴い鼻呼吸が困難となり、口呼吸の割合が増加することでいびきや口臭の悪化につながります。
また、細菌が副鼻腔に蓄積してしまう副鼻腔炎では、副鼻腔から出た膿が口腔に流れ込むことで直接的に口臭を悪化させる可能性もあります。
どちらもセルフケアでの改善は困難であり、医療機関での抗生剤内服、ネブライザー療法などが選択されますが、症状が重い場合は最悪の場合手術療法が必要です。
手術療法では、鼻詰まりの原因となる肥厚した鼻粘膜を切除したり、細菌の蓄積した副鼻腔を開放し、換気を改善させることで細菌の繁殖を抑制します。
鼻詰まりや鼻汁の増加、口呼吸の割合が増加することで生じる、より低く大きな音のいびきなどを認める場合は、上記疾患を疑い、耳鼻咽喉科を受診すると良いでしょう。
胃腸トラブルや逆流性食道炎の可能性
いびきと口臭がひどい場合、胃腸トラブルや逆流性食道炎の可能性もあります。
摂取した食事は食道→胃→十二指腸→小腸→大腸という順に消化・吸収され、最終的に肛門から排泄されますが、急性胃炎や腸炎などの胃腸トラブルや逆流性食道炎(胃から食道に胃酸が逆流してしまう病気)を発症すると、胃の蠕動時に内容物が十二指腸に進まず、食道側に逆流してしまいます。
その結果、胃酸が胃から口側に込み上げてしまい、酸っぱい匂いの口臭が生じる原因となるため、注意が必要です。
この場合、いびきと口臭に直接的な関係はありませんが、そもそも逆流性食道炎は過食や過度なアルコール摂取、肥満、就寝直前の食事など、乱れた食生活が原因となることが多く、いびきのリスク要因と共通しているため、間接的にいびきが同時に生じる可能性があります。
胃腸トラブルや逆流性食道炎を発症している場合、口臭以外にも便秘や下痢、嘔気・嘔吐、腹痛などさまざまな消化器症状をきたす可能性が高いため、これらの症状を認める場合は消化器内科に受診すると良いでしょう。
【まとめ】いびきと口臭の原因と対処法
この記事では、いびきと口臭の原因と対処法、実際の体験談などについて詳しく解説しました。
いびきをかく人は口腔内が乾燥しやすく、また気道に炎症も生じやすくなることで、口腔内の細菌が繁殖しやすい環境を形成してしまうため、口臭が悪化します。
口臭が強いと人前で話すことが恥ずかしくなったり、自分に自信を持てなくなります。
また、いびきは睡眠の質の低下やさまざまな健康被害を及ぼす可能性もあるため、口臭を同時に改善するためにも早期に改善すべきです。
そのための第一歩として、自身のいびきの危険度を自覚することが重要であり、下記の記事ではいびきの危険度を簡単にセルフチェックできる方法を詳しく解説しているため、ぜひご一読ください。
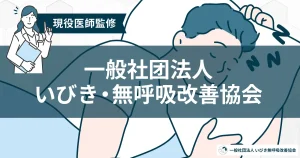
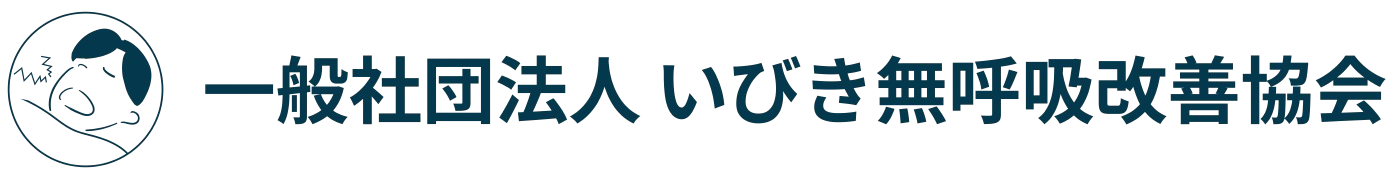
コメント